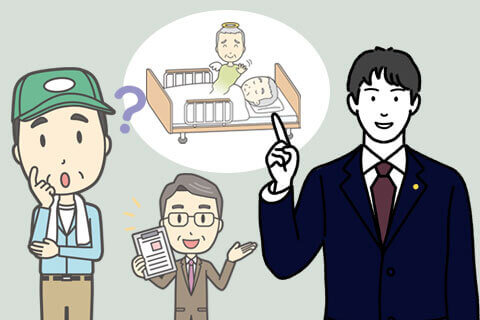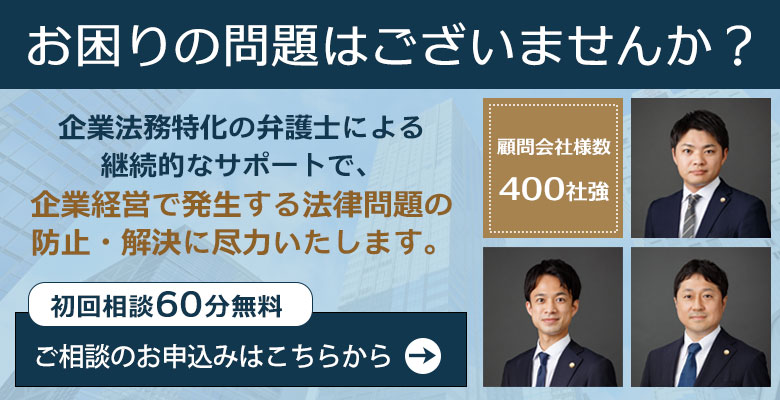Q. 最近、身寄りのいなかった従業員が亡くなりました。その従業員は身寄りがなかったこともあり、社長の私がいろいろ気にかけていました。葬儀の際に、葬儀社の方から、特別縁故者という制度があることを聞きました。今まで聞いたことがなかったのですが、どのような制度なのでしょうか?
A. 特別縁故者の制度とは、故人に相続人がいなかった場合でも、家庭裁判所で特別縁故者と認められると、相続人以外の方が相続財産の全部または一部を取得できる制度です。
1 特別縁故者に対する相続財産分与の制度とは?
相続人がいなかった故人(配偶者や子、兄弟等がいない人だけでなく、相続人がいてもその相続人全員が相続放棄をした場合も含みます。)が亡くなられた際、その遺産はどうなるのでしょうか?
誰も取得する人がいなかった場合は、最終的には国庫に帰属します。
ただ、民法958条の2では、家庭裁判所は、故人と生計を同じくしていた者、故人の療養看護に努めた者その他故人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができると規定されています。
このように家庭裁判所により、故人と特別の縁故がある特別縁故者と認められると、相続財産の全部又は一部(金銭に限らず不動産等も取得可能です。)を受け取ることができます。

2 どのような者が、特別縁故者として認められるのでしょうか?
過去の審判例では、例えば、故人の子の妻、叔父や従兄弟のような親族で認められたケースがあります。
また、非親族でも、勤務先の代表取締役、内縁関係にあった者、元教え子なども、故人の生前に長期にわたりその生活を支えた等として特別縁故関係が認められたものもあります。
また、個人ではありませんが、地方公共団体や母校の大学、お寺、老人ホーム、出所後補導援護をした公益法人、特別介護施設などの法人も、特別縁故者として認められているケースがあります。
3 判断の際に考慮される要素はどのような要素でしょうか?
では、特別縁故者として認められるためには、どのような事情が考慮されるのでしょうか。過去の審判例では、以下のような項目が考慮されていますが、これに限らず様々な要素が考慮され、家庭裁判所が判断するとされています。
故人の意思
例えば、その者に遺産を遺したいというメモ等が残っている。
自然的血族関係の有無
叔父・叔母や従兄弟といった血族関係も考慮されます。
生前における交際の程度
故人と生計が同一であった場合や内縁関係にあった場合が典型です。
故人が精神的・物質的に庇護恩恵を受けた程度
生前、故人の療養看護を行っていたり、物心両面で長期にわたり故人を支えていた場合なども考慮されます。
死後における実質的供養の程度
故人の葬祭一切を行ったりした場合が典型です。
4 具体的な請求の方法はどのようにすればよいでしょうか?
まず、故人の相続財産について、家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
選任された相続財産清算人は、故人の相続財産を調査・換価等をした上で、債権者がいる場合はその支払いを行うなど清算を行います。
清算後に残った財産がある場合は、特別縁故者に該当すると考える者は家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行います。
そして、家庭裁判所の審判により特別縁故者として認められた者は、相続財産の全部又は一部を取得することができます。
そして、最後に残った財産があれば、国庫に帰属することとなります。
5 まとめ:悩んだらまずは専門家に相談
現在、高齢化社会の進展により、亡くなられた方に身寄りがいないケース等にも遭遇することがあるかと思います。
生前や死後に、故人と関係が深かったり、故人のために貢献をされた方は、家庭裁判所に申立てをして相続財産の分与を受けることができる可能性があります。なお、分与を受けた場合は、相続税等の納税義務が生じることにも注意が必要です。
もし、可能性があると思われる場合は、専門家に相談されることも有用です。