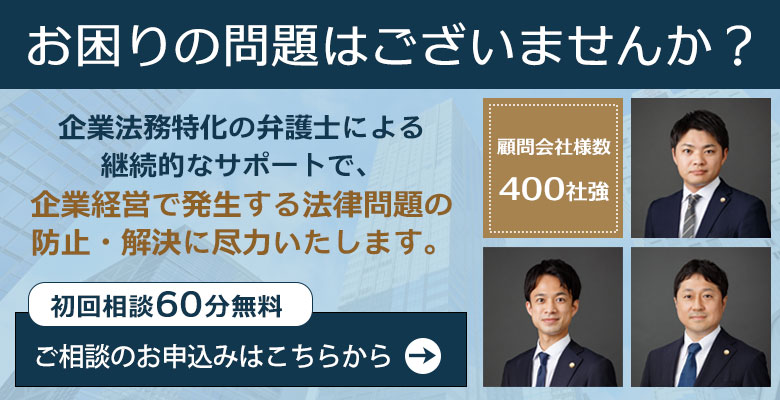社員の能力に問題がある場合や、経営状況が悪化している場合など、「このまま雇用を続けるのは難しい」と感じる場面は、どの企業にも起こり得ます。しかし、問題社員だからといって即座に解雇するのは現実的にはハードルが高く、対応を誤ればトラブルや訴訟に発展するおそれもあります。
そこで多くの企業が選択しているのが、従業員と話し合いを重ねて合意のもとで退職してもらう「退職勧奨」という方法です。これは、解雇に比べて法的リスクを抑えながら雇用関係を解消できる手段とされています。
ただし、退職勧奨の進め方を誤ると、「退職を強要された」と受け取られかねません。会社都合退職の扱いや退職金の支払い、面談記録の残し方など、細かな対応が不十分なまま進めてしまうと、やはりトラブルにつながるリスクがあります。
本記事では、退職勧奨を検討している企業の経営者や責任者の方に向けて、基本的な流れや押さえるべきポイント、円滑に合意を得るための工夫、そして弁護士に相談すべきタイミングについて、わかりやすく解説します。
目次
1. 退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が従業員に対して「退職してほしい」と提案し、双方が納得のうえで退職に合意する手続きです。これは、一方的に雇用を打ち切る「解雇」とは異なり、従業員の同意があってはじめて成立します。円満な形で雇用関係を解消する際によく利用されます。
ただし、進め方を誤ると、「強引に辞めさせられた」と受け止められるおそれがあります。実際に、退職を強要したことで、慰謝料を請求されたり、労働審判・訴訟に発展したりするケースも見られます。円滑な合意形成を目指すには、慎重かつ丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
なお、退職勧奨によって従業員が退職した場合、原則として「会社都合退職」として取り扱われます。会社都合退職であれば、自己都合退職よりも失業保険の給付開始が早く、給付日数も長くなるなど、従業員にとって一定のメリットがあります。こうした制度上の違いを丁寧に説明し、従業員の理解と納得を得ることが、スムーズな合意形成につながります。

2. 会社にとっての退職勧奨のメリット・デメリット
退職勧奨は、法的なリスクを抑えながら、従業員とできるだけ円満に雇用関係を終わらせる方法として利用されています。ただし、進め方を誤ると想定外のトラブルにつながることもあるため、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが大切です。
2.1 退職勧奨のメリット
退職勧奨の最大のメリットは、解雇のように一方的に雇用を打ち切るのではなく、従業員との話し合いによって合意のうえで退職を進められる点にあります。あくまで双方の合意を前提としているため、あとから「不当解雇だ」と訴えられるリスクを大幅に抑えることができます。
一方、解雇の場合は、法的に有効と認められるためのハードルが高く、最終的には裁判所の判断に委ねられることになります。このような点からも、法的なリスクを抱えながら進めざるを得ないのが実情です。
その点、退職勧奨は明確な合意が成立すれば、その正当性が後から争われるリスクが大幅に下げられます。結果として、長期化しがちな法的トラブルを回避しやすくなるのが大きな利点です。
また、進め方に配慮すれば、従業員との感情的な対立を避けることも可能です。こうした対応は、社内の雰囲気の悪化や、他の従業員への悪影響を防ぐ意味でも重要なポイントとなります。
さらに、仮に解雇できるだけの明確な理由がない場合でも、丁寧に対話を重ねることで退職への合意を得られるケースがあります。このように、柔軟な対応が可能な点も、退職勧奨ならではのメリットといえるでしょう。
2.2 退職勧奨のデメリット
一方で、退職勧奨にはデメリットもあります。
最大の弱点は、話し合いである以上、従業員が退職に同意しなければ雇用を終了できない点です。必要に応じて面談を重ねる必要もあり、時間も手間もかかります。
また、従業員に納得してもらうために、退職金を上乗せしたり解決金を支払ったりする提案をするケースもあります。これによって、会社側に当初の予定以上の経済的負担が生じることも珍しくありません。
さらに注意すべきなのは、従業員が退職を望まない意思をはっきり示しているのに、執拗に退職を迫ってしまうと「退職強要」と受け取られ、不法行為責任を問われるおそれがあることです。
また、本来であれば懲戒解雇に相当するような重大な問題行為があった場合に、退職勧奨だけで終わらせてしまうと、社内でのけじめがつかず、他の従業員のモチベーションや秩序に影響を及ぼす可能性もあります。
そして、どうしても同意が得られない場合には、最終的に解雇を検討せざるを得ないケースもあります。ただし、解雇は慎重に進めないと、結果的に長期の裁判に発展したり多額の金銭を支払うことになったりするリスクがあります。
退職勧奨の進め方や交渉のポイントを誤らないためにも、弁護士の助言を受けながら進めることをおすすめします。
3. 退職勧奨の前に会社が検討すべき事項
退職勧奨を適切に進めるためには、事前の準備が欠かせません。対応を誤れば、従業員との信頼関係が損なわれるだけでなく、思わぬトラブルに発展するリスクもあります。
では、実際に退職勧奨を行うにあたって、会社はどのような点に注意し、何を事前に整理しておくべきなのでしょうか。
ここでは、事前に検討しておきたい重要なポイントを解説していきます。
3.1 退職勧奨の要否と対象者の選定
退職勧奨を検討する際には、まず本当に退職を勧める必要があるのかどうか、そして実施するのであれば誰を対象とするのかを慎重に見極める必要があります。選定を誤れば、従業員との信頼関係の悪化や法的トラブルを招くリスクがあるため、安易に進めるべきではありません。
ここで重要となるのが、「会社がこれまでにどのような対応をしてきたのか」という点です。
たとえば、勤務態度や能力に問題があり、これまでにも複数回にわたって注意・指導を行ってきた従業員であれば、その経緯や評価内容を整理し、「なぜ退職を勧めるのか」を客観的に説明できる状態にしておくことが大切です。過去の指導履歴があれば、本人もある程度の問題意識を持っており、話し合いが前向きに進む可能性があります。
一方で、会社側がこれまでに十分な指導や改善の機会を与えてこなかった場合には、突然の退職勧奨に本人が納得せず、かえって反発やトラブルにつながるおそれがあります。このようなケースでは、退職を求める前に、まずは業務改善に向けたフィードバックや注意喚起のステップを踏むべきかどうかも含めて検討する必要があります。
このように、対象者の選定にあたっては、表面的な問題だけでなく、それまでの経緯や本人の受け止め方、今後の対応方針までを含めて整理しておくことが、退職勧奨を円滑に進めるうえで不可欠です。
3.2 雇用保険の離職理由
退職勧奨によって従業員が退職する場合、雇用保険上の離職理由は原則として「会社都合退職」となります。これは、失業給付の給付日数や待機期間の面で、従業員にとって自己都合退職より有利な取り扱いです。そのため、離職理由の記載を誤らないことが重要です。
離職理由は、会社が作成する「離職票(離職証明書)」の内容をもとにハローワークが判断します。特に「離職理由欄」では、「事業主からの働きかけによるもの」の中の「希望退職の募集又は退職勧奨」を選ぶのが一般的です。
また、離職票には従業員本人が記入する欄もあり、会社の記載内容に異議がある場合は「異議あり」として意思を表示できます。その場合、ハローワークが会社・本人双方の主張や資料を確認し、最終的な判断を行います。
万が一、実質的には会社都合退職であるにもかかわらず、会社側が「自己都合退職」で処理してしまうと、従業員との信頼関係が損なわれ、訂正対応に追われるおそれもあります。離職票の作成時には、本人との認識のずれがないよう丁寧に確認し、説明責任を果たすことが求められます。
なお、退職勧奨による退職者が発生したことが助成金の受給に影響する場合もありますので注意が必要です。
3.3 退職時期
退職時期についても、あらかじめ検討しておきましょう。
特に問題行動の多い社員の場合は、他の従業員への悪影響を避けるため、できるだけ早期に退職してもらう方が望ましいケースもあります。ただし、従業員にも生活や再就職準備の事情があるため、あまりに一方的なスケジュールはかえって反発を招きます。
合意が前提である以上、従業員の都合にも一定の配慮をしながら、現実的な退職時期をすり合わせていくことがポイントです。
3.4 有給休暇の扱い
退職日が決まったら、残っている有給休暇の扱いについても検討が必要です。
従業員が退職勧奨に応じた場合でも、退職までに有給休暇をすべて取得したいと希望されることは珍しくありません。法的にも、従業員が希望すれば退職日まで原則として取得を認める必要があります。
また、退職までに消化しきれない分については、法律上のルールではありませんが、会社と従業員の合意で「買い取る」ことが可能です。ただし、実際の処理は、就業規則や退職金規程などの社内ルールを踏まえて決める必要があります。
従業員への説明をあいまいにすると後からトラブルになるため、買い取り額や計算方法、支払い時期も含めてあらかじめ明確に伝えておくと安心です。
3.5 退職金
退職勧奨を進めるうえで、退職金の扱いは従業員の同意を得るための重要なポイントとなります。金額や支給条件によって、退職への納得度が大きく左右されるため、事前にしっかりと準備しておく必要があります。
まず確認しておきたいのは、退職金の支払いは、法律上の義務ではないという点です。ただし、雇用契約書や就業規則、退職金規程などに定めがある場合や、過去に支給した慣行がある場合には、それに従って金額を算出する必要があります。したがって、最初に退職金規程や関連ルールを確認し、法的な支払義務の有無や基準となる支給額を把握しておきましょう。
そのうえで、合意形成をスムーズに進めるために、「上乗せ退職金」や「解決金」「特別退職金」など、規程とは別に追加の金銭を提案するケースもあります。金額の設定にあたっては、過去の支給実績や他の従業員との公平性に配慮しつつ、会社として無理のない範囲で判断することが大切です。
また、金銭の提案を行う際には、支給額の根拠や支払い時期・方法をあいまいにせず、可能な限り明確に伝えるようにしましょう。条件が不透明なままだと、「話が違う」と不信感を招き、退職後にトラブルになることもあります。
3.6 再就職の支援
円満に退職してもらうために、再就職支援を提案する方法もあります。
たとえば、厚生労働省の「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」の制度では、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、外部の職業紹介事業者に再就職支援を委託した場合や、求職活動のための休暇を与えた場合に、条件を満たせば助成金を受け取ることができます。
支援内容を従業員に示すことで、退職後の不安を和らげ、合意形成が進みやすくなるケースもあります。制度を活用する際は、厚生労働省の最新情報を確認し、要件や手続きに漏れがないようにしましょう。
3.7 退職勧奨を断られた場合の対応
退職勧奨は、あくまでも従業員の同意があってはじめて成立するものです。そのため、話し合いが難航した場合でも、何度も繰り返して強く迫るような対応は避けなければなりません。行き過ぎた説得は、違法な「退職の強要」と受け取られ、トラブルに発展するおそれがあります。
話し合いが平行線をたどる場合には、最終的に懲戒処分や解雇を検討する場面もあり得ますが、その場合は法律上の有効性が後で問題になるため、証拠や手続きの正当性が重要になります。
いずれにしても、紛争を防ぐためには、弁護士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
4. 退職勧奨の流れ
退職勧奨を行う際は、事前に十分な準備を整えたうえで、どのように切り出すか、どの条件をどの順序で話し合うか、そして最終的に合意を文書化するまでの流れを把握しておくことが重要です。
ここでは、退職勧奨を進める際の一般的な流れを、3つのステップに分けてわかりやすく解説します。
4.1 対象者との交渉
まずは対象者との話し合いを行います。
ここでは、これまでの勤務状況や指導歴をもとに、なぜ退職を勧めるのかをできるだけ具体的に説明し、対象者に納得してもらうことが重要になります。企業側の一方的な事情を押しつけるだけではなく、相手が疑問や不安を抱えているポイントを把握し、できる限り質問に答える姿勢が求められます。
また、従業員が「退職を強制された」と受け取られないように、無理な説得や高圧的な発言は避けるべきです。従業員側が退職の意思がないことを明確に表明しているにもかかわらず、退職勧奨を続けることも避ける必要があります。やむを得ず複数回にわたる面談になることもあるので、記録を残しておくと後のトラブル防止につながります。
4.2 退職条件の決定
従業員が退職に応じる意思を示した場合には、具体的な条件を詰めていきます。たとえば、退職日、有給休暇の消化方法、退職金や解決金の金額、離職票の扱い(会社都合退職か自己都合か)などを合意していきます。
この段階で、従業員が退職後の生活に不安を感じないように、再就職支援制度の提案やハローワーク手続きのサポートなどを説明するのも有効です。
また、条件の決定内容は口頭だけでなく書面で整理し、従業員が内容を理解できるようにしておくことが重要です。
4.3 退職合意書の締結
退職条件について話し合いがまとまったら、口約束だけで終わらせず、「退職合意書」などの書面を作成しておくことが大切です。合意書には、退職日や退職理由、退職金や解決金の額、支払い方法、有給休暇の取り扱いなど、決まった内容を具体的に盛り込みます。内容をあいまいにせず、従業員にきちんと説明し、十分に理解したうえで署名・押印してもらうことが重要です。
具体的な合意書の内容や条項の例については、後のトラブルを防ぐためにも、弁護士と相談しながら慎重に作成することをおすすめします。
5. 退職勧奨を成功させるポイント
退職勧奨は解雇に比べて法的リスクが低い方法とはいえ、進め方を誤ると「退職強要」と判断されるおそれもあります。従業員と穏やかに合意し、後のトラブルを防ぐためには、いくつかのポイントを意識しておくことが大切です。
5.1 従業員への指導、懲戒処分の適切・公平な運用
勤務態度や能力不足などを理由に退職を勧める場合、これまでにどのような指導や評価を行ってきたかが問われます。何の説明もなく突然退職を促されれば、従業員は納得できずトラブルに発展しかねません。
日頃から指導を行い、改善の機会を与えてきたという事実をきちんと示せるようにしておくことが大切です。注意指導書や面談記録、人事評価のデータを残し、後からでも客観的に証明できる状態にしておきましょう。
特に懲戒処分は恣意的に行われると公平性を欠きます。他の従業員と比べても一貫性があるか、社内規程に沿って運用されているかを確認することが重要です。
5.2 従業員への適切な説明内容・説明方法の検討
退職勧奨を行う際は、伝え方や説明内容に十分な配慮が必要です。どれだけ事情があっても、一方的に「辞めてほしい」とだけ告げれば、高圧的だと感じさせてしまいます。
まず前提として「解雇」ではなく、退職勧奨であること、そしてなぜ退職勧奨をするのか、どの点が問題とされているのかを、これまでの経緯を踏まえて具体的に説明するようにしましょう。感情的な表現や責め立てるような言葉は避け、相手の立場を尊重する姿勢を示すことが大切です。
相手の質問や疑問には正面から向き合い、話し合いの記録を残しておくことで、後の行き違いも防げます。
5.3 従業員が納得できそうな退職プランの検討
退職勧奨は従業員が応じてくれなければ成立しません。そのため、辞める側にも納得できる条件を提示することが必要です。
実際には、通常の退職金に一定の上乗せをしたり、解決金として別途支払ったりする方法がよく用いられます。有給休暇をすべて取得させる、再就職支援を用意するなどの配慮も、従業員にとっては安心材料になります。
厚生労働省の「労働移動支援助成金」などを活用し、外部の職業紹介事業者と提携する企業も増えています。単に「辞めてほしい」と伝えるだけでなく、「会社としてできる最大限の対応」を示すことで、退職後の不安を和らげ、話がまとまりやすくなります。
5.4 発言内容に注意すること
面談の場での言葉選びにも十分な注意が必要です。「辞めないなら降格する」「辞めないと他の人に迷惑がかかる」といった強圧的な発言は、退職勧奨ではなく退職強要と受け止められるおそれがありますし、仮に合意ができても後に有効性が問題になる場合もあります。後に問題となる発言をしないよう事前に弁護士と十分検討し、話し合いはあくまでも合意が前提であることを繰り返し伝えましょう。
「最終的に決めるのはあなたです」と一言添えるだけでも、強制ではないことが相手に伝わりやすくなります。言葉だけでなく態度にも冷静さを保ち、感情的にならないことが大切です。
5.5 事実上退職を強要するような行動を控えること
退職勧奨は、あくまで従業員が自分の意思で合意する形で進めるものです。しかし、やり方を誤ってしまうと、退職強要とみなされる危険があります。
従業員が退職勧奨に応じないからといって、執拗に呼び出して長時間にわたる説得を繰り返したり、何度も面談に呼びつけて精神的に追い詰めるようなやり方は避けるべきです。話がまとまらなかった場合は、相手に考える時間を与え、結論を急がせないようにしましょう。
また、退職に応じさせる目的での不当な配置転換や出向も、違法と判断されるリスクがあります。たとえば、事務職の従業員を突然倉庫業務に出向させて肉体的に負担の大きい作業を命じたり、草むしりや雑用だけを割り当てて他の仕事を与えないような対応は、退職に追い込むための不利益取り扱いだとみなされかねません。1人だけを個室に隔離し、会社の業務と関係ない仕事をさせるといったケースも同様です。
こうした行為は、従業員の自由な意思に基づく退職とは認められず、後にトラブルになった際に退職の有効性が問題になったり、会社が不法行為責任を問われたりする可能性があります。
退職勧奨の進め方で行き詰まった場合、強引な方法をとるのではなく、弁護士などに相談しながら冷静に進めることが、結果的に会社を守ることにつながります。
5.6 従業員が録音している前提で話すこと
最近はスマートフォンなどで面談を録音する従業員が増えています。録音データは後で証拠として使われることも多いため、どの場面でも「録音されているつもり」で発言する習慣をつけておくことが大切です。発言の前後を切り取られても誤解されないよう、話の流れを整理しながら冷静に進めましょう。
また、会社側でも面談の日時や内容を必ず記録に残し、必要であれば録音も検討しましょう。
5.7 対応は2人以上で行うこと
退職勧奨の面談は、複数人で行うことが基本です。上司1人だけで従業員と面談すると、「言った・言わない」の問題が起きたときに証明が難しくなります。
人事担当者や上司など、立場の異なる人が同席すれば、公正な手続きであったことを後から説明しやすくできます。同席者がいることで、従業員にとっても一方的に圧力をかけられる場ではないと感じてもらいやすくなります。

6. 退職勧奨についてのよくあるご質問
ここでは、退職勧奨について、企業の担当者が特に疑問に思いやすいポイントをQ&Aで整理します。
6.1 退職勧奨と解雇の違いは何ですか?
退職勧奨と解雇の最大の違いは、「従業員の同意が必要かどうか」にあります。
退職勧奨は、会社が退職を促し、それに対して従業員が合意することで初めて成立します。
一方、解雇は従業員の同意がなくても、会社が一方的に労働契約を終了させられる手続きです。その分、法的な要件が厳しく、これらを欠いた場合には、不当解雇と判断されて無効となり、賃金請求や職場復帰、損害賠償などの法的責任を問われる可能性もあります。
このように、解雇には高い法的ハードルがある一方で、退職勧奨は従業員の合意を前提とするため、適切に行えばトラブルに発展するリスクを比較的抑えやすい方法といえます。
6.2 退職勧奨はどのような場合に認められますか?
退職勧奨は、従業員が自由な意思で退職に合意できる状況であれば、原則として認められます。従業員に勤務態度や能力などの問題がある場合はもちろん、会社の経営判断や人員整理の必要性に基づいて退職勧奨を行うことも可能です。
ただし、退職勧奨は「合意による退職」である以上、その合意が真に自由意思に基づいていたかどうかが重要な判断基準となります。たとえば、「退職しなければ解雇する」と繰り返し迫ったり、怒鳴る・机を叩くといった威圧的な態度をとったり、人格を否定するような発言を行った場合には、従業員の意思が実質的に制限されたとみなされ、違法な退職強要と判断される可能性があります。
適法に退職勧奨を進めるためには、従業員が冷静に判断できる環境を整えたうえで、丁寧な説明と対話を通じて、本人の納得を得るプロセスが欠かせません。
6.3 退職勧奨で合意に至った場合、合意書を作成した方がよいですか?
トラブル防止のためにも、退職合意書などの書面を作成することを強くおすすめします。
退職勧奨は「従業員の合意による退職」が前提であり、厳密には書面の作成は法律上の義務ではありません。しかし、どのような書面を作成すべきなのかは状況にもよりますが、少なくとも従業員側の退職の意思が明らかとなる書面の作成自体はほぼ必須です。
口頭だけでは「言った・言わない」の争いに発展するおそれがあり、実務上は非常にリスクが高くなるからです。後に「解雇された」と従業員側から主張されるケースも珍しくありません。
退職の条件について合意に至った場合には、「退職合意書」を作成し、内容をきちんと説明したうえで従業員から署名・捺印をもらうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
7. まとめ:退職勧奨で悩んだら弁護士に相談
退職勧奨は、従業員の合意を前提とする手続きだからこそ、進め方を誤れば「退職の強要」と受け取られ、その有効性に疑問が生じ、慰謝料請求や訴訟に発展するリスクがあります。話し合いの流れや条件の伝え方など、企業側が注意すべきポイントは少なくありません。
従業員との話し合いが難航しそうな場合や、対応に不安がある場合には、早めに弁護士に相談することで、トラブルの回避や冷静な対応につながります。退職勧奨の進め方や条件設計、合意書の作成まで、法的リスクを踏まえたサポートを受けることができます。
よつば総合法律事務所には、人事労務分野に詳しい弁護士が複数在籍しており、企業の実情に即した対応を行っています。退職勧奨の進め方でお悩みの際は、どうぞお気軽にご相談ください。