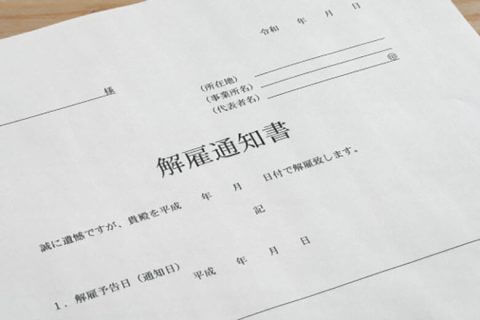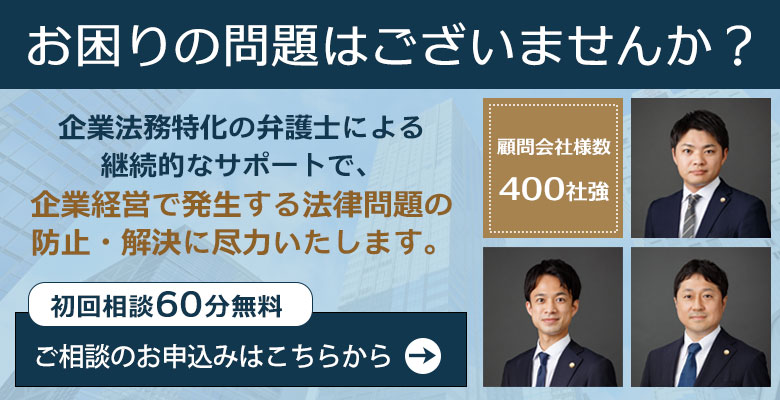従業員を解雇しなければならない状況は、どの会社にとっても避けたいものです。しかし、業務態度の悪化や繰り返される無断欠勤など、やむを得ず解雇を選ばざるを得ないこともあります。そんなときに見落としがちなのが、解雇通知書の作成方法と渡し方です。
口頭で伝えたつもりでも、後から「聞いていない」と争われるケースは少なくありません。手続きや内容が不十分だと、解雇が無効と判断されて思わぬ損害が発生することもあります。
この記事では、会社側の立場で知っておくべき解雇通知書の基本知識や他の通知書との違い、作成時のポイント、トラブルを防ぐためのコツを弁護士がわかりやすく解説します。
「どこまで理由を書けばいいのか」「手渡しと郵送のどちらがいいのか」など、解雇通知書について悩んだときのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 解雇通知書とは
解雇通知書とは、会社が従業員を一方的に解雇するときに、その事実を文書で通知する書面です。法律で作成が義務付けられているものではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも書面で解雇を通知しておきましょう。
特に日本の労働法では、解雇について使用者側に厳しい条件が課されています。解雇を無効とされないためには、従業員に対して適正な手続きを取ったことを客観的に証明できるようにしておく必要があります。
その証拠のひとつが解雇通知書です。解雇を通知した事実、時期、方法などを明確に残しておくことで、後の労働審判や裁判でも有効な証拠になります。
1.2 解雇予告通知書と解雇通知書の違い
解雇通知書と似た書面に「解雇予告通知書」があります。
解雇予告通知書とは、労働基準法で使用者に義務付けられている「少なくとも30日前に解雇を予告するか、または解雇予告手当を支払う」というルールを履行するための書面です。
一方で、一般的にいう解雇通知書は、実際に従業員を解雇することを伝える書面であり、法令で交付が義務付けられているわけではありません。
つまり、次のように整理すると分かりやすいでしょう。
- 解雇予告通知書:「〇月〇日付で解雇します」と、一定の予告期間前に通知するもの。
- 解雇通知書:解雇する当日や直前に通知するもの。
厳密に両者を区別せずに「解雇通知書」と呼んでいるケースが多いとは思います。また解雇予告通知書で解雇日が明確になるのが通常であるため、別途追加で解雇通知書を出さない場合も珍しくありません。
後々「言った、言わない」で争いにならないよう、適切なタイミングで適切な書面を作成しましょう。
1.3 解雇理由証明書と解雇通知書の違い
解雇通知書や解雇予告通知書と混同しやすいものに「解雇理由証明書」があります。
これは、労働者が会社に対して「解雇理由を書面で証明してください」と求めた場合に、会社が発行しなければならない書面です。
つまり、両者には次のような違いがあります。
- 解雇通知書(解雇予告通知書):会社が一方的に渡すもの。解雇の事実と基本情報を通知する。
- 解雇理由証明書:労働者の請求があって初めて作成するもの。解雇理由を記載する。
解雇理由証明書を請求された場合、理由をあいまいにすると後の無効主張につながりかねません。法的トラブルを防ぐためにも、通知書と証明書の使い分けを正しく理解し、慎重に作成することが重要です。

2. 解雇通知書の記載事項
解雇通知書には、何を書くべきかが法律で決まっているわけではありません。もっとも、後で「無効」と争われないために最低限、次の項目を必ず盛り込んでおきましょう。
① 解雇する従業員の氏名
誰に対する解雇かを特定するのは基本です。解雇する従業員の氏名は正確に記載しましょう。
② 会社名と代表者名
どの法人が解雇するのかを明記することで、労働契約の当事者関係を明確にできます。代表者名を併記するのも有効です。
③ 解雇通知書の作成日
解雇通知書の作成日を入れておくと、いつ会社が最終的に解雇を伝えたかを客観的に証明できます。後から「伝えられていない」と争われるのを防ぐためにも、必ず作成日を記載しましょう。
④ 解雇する日付(解雇の効力発生日)
従業員との雇用契約がいつ終了するかを明確に示すために、解雇の効力発生日を具体的に記載します。解雇日があいまいだと、退職日をめぐる争いが起こりやすくなります。
また、別途解雇予告通知書を交付している場合、内容と整合性が取れているか確認することも重要です。
⑤ 解雇の意思表示と法的根拠
「貴殿を〇年〇月〇日付で解雇します」といった明確な意思表示を記載します。あいまいな表現はトラブルのもとです。
また、解雇の理由をどの程度記載するかはケースバイケースですが、最低限、普通解雇なのか、懲戒解雇なのか法的根拠があいまいな内容は避ける必要があります。
3. 解雇通知書作成時のポイント
解雇通知書は、単にひな形に沿って作成したものを渡せば済むというものではありません。解雇は従業員の雇用を一方的に打ち切る行為であり、労働法上も厳しく制約されています。
だからこそ、通知書を作成する前に必ず確認しておくべきポイントがあります。
3.1 合意による退職の可能性を検討しましたか?
解雇は、会社にとって大きな決断です。基本的に解雇は最終手段とされているため、まずは従業員と話し合い、合意退職にできないかを検討することが重要です。
合意退職となれば、後から解雇の有効性を争われるリスクを大幅に減らせます。そのためには、退職金を一定額上乗せする、離職票の理由を会社都合とするなど、従業員にとってのメリットを提示しながら話し合いを進めるのが一般的です。
話し合いがまとまった場合には、必ず退職届や退職合意書を作成し、署名・日付入りの書面を残すことがトラブル防止につながります。
3.2 解雇が有効か検討しましたか?
合意による退職が難しく、最終的に解雇するしかないと判断したときは、解雇が有効かどうかを慎重に検討しなければなりません。
労働契約法では「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないときは無効」とされています。法的なハードルが高いため「勤務態度が悪い」「無断欠勤が多い」などの理由だけでは、解雇が正当と認められないことが多いのが実情です。
解雇を有効とするには、問題行為の事実が客観的に証明できるかどうかが大きなポイントとなります。たとえば、勤務状況の記録、注意指導のメモ、始末書などを残しておく必要があります。また、従業員に改善の機会を与えたかどうかも重要です。
口頭での注意だけでなく、書面で指導し、それでも改善されない場合に限って解雇を検討するという段階的なプロセスが不可欠です。さらに、同じような問題があった他の従業員に対してはどのように対応したのかという公平性も確認しておくべきです。
3.3 解雇通知書を渡す前に専門家に相談しましたか?
解雇の有効性を確認するには多くの法的ポイントを総合的に判断する必要があります。だからこそ、解雇通知書を渡す前には専門家に相談することを強くおすすめします。労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談すれば、就業規則との整合性や証拠の整理、予告手当の計算方法まで客観的にチェックできます。
もし後で従業員が弁護士に相談し、「不当解雇だ」と争われた場合でも、適切に準備した通知書があれば会社側が不利になるリスクを減らすことができるかもしれません。
解雇は会社にとっても従業員にとっても大きな問題です。だからこそ、安易に一人で判断せず、合意退職の可能性の検討から有効性の確認、専門家への相談まで慎重に進めることが、最終的なトラブル防止につながるのです。
4. 解雇通知書を渡す流れ
解雇通知書を渡すときは、単に書面を作って終わりではなく、「確実に届いた」ことを後から証明できる形で通知することが大切です。もし「渡されていない」「知らなかった」と主張されると、解雇自体の有効性を争われる原因になります。
① 面談して書面を手渡す方法
もっとも基本的なのは、従業員と面談を行い、その場で解雇通知書を直接手渡しする方法です。このとき大切なのは、渡した事実を証明できるようにしておくことです。通知書のコピーを準備して、従業員に受領日と受領の署名・押印をしてもらいましょう。別途受領証を用意して署名をもらう形でもかまいません。
こうした手続きを踏んでおかないと、後になって「受け取っていない」と言われたときに証明が難しくなり、不要な争いにつながる恐れがあります。
② 郵送で通知する方法
もし従業員がすでに出勤していない場合や、面談での手渡しを拒否された場合には、郵送による通知を検討します。この場合は、配達証明付きの内容証明郵便を使う方法が一般的です。これにより、どの内容の通知をいつ送ったのかを証明できます。
仮に受け取り拒否をされたとしても、法律上は「通常到達すべきときに到達したものとみなされる」可能性がありますが、念のため、別途普通郵便での通知も併せて実施するのがお勧めです。

5. 解雇通知書のよくあるご質問
解雇通知書について、会社側が迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。実際の現場でトラブルになりやすいところをしっかり確認しておきましょう。
5.1 そもそも解雇通知書は必要ですか?
法律上、解雇通知書を必ず書面で交付しなければならないという規定はありません。
ただし、実際には口頭だけで伝えると「言った、言わない」の争いが起こりやすくなります。解雇は従業員にとって非常に重要な意思表示です。後のトラブルを防ぐためにも、最終的な解雇の意思は必ず書面で通知するのが安全です。
5.2 解雇理由は書いた方がよいですか?
法律上、会社は従業員から求められた場合には「解雇理由証明書」を発行する義務があります。ただし、解雇通知書に必ず詳細な理由を記載しなければならないという決まりはありません。
とはいえ、具体的な理由を何も示さずに通知すると、後で従業員から「解雇理由が不明確だ」と主張され、不当解雇をめぐるトラブルに発展する可能性があります。
一方で、通知書に必要以上に理由を詳しく書きすぎると、かえって反論を招きやすい場合もあります。
そのため、実際にどこまで理由を記載すべきかは、会社の状況や解雇の理由によって変わってきます。
トラブルを避けるためにも、解雇理由をどう書くか迷ったときは弁護士に相談することをおすすめします。
5.3 解雇通知書は手渡しする必要がありますか?
手渡しが法律上の絶対条件というわけではありません。しかし、解雇の意思表示が「確実に従業員に届いた」ことを証明できなければ後でトラブルになります。そのため、基本は面談で手渡しし、受領証にサインをもらう方法が一番確実です。
もし従業員が出勤していなかったり、手渡しを拒んだりする場合は配達証明付きの内容証明郵便で送付する方法が有効です。
5.4 従業員が解雇通知書の受領を拒否した場合はどうすればよいですか?
従業員が手渡しでの解雇通知書の受領を拒否するケースは珍しくありません。しかし、「解雇の意思表示が確実に届いている」と認められれば、効力自体が失われることはありません。
そのためには、内容証明郵便を使って送付し、「いつ、どのような内容を送ったか」を証明できるようにしておきましょう。もし心配な場合は、普通郵便を併用して送付する方法も有効です。複数の手段を組み合わせることで、「届いていない」と言われるリスクをさらに減らすことができます。
5.5 試用期間中の従業員にも解雇通知書は必要ですか?
試用期間中の従業員であっても、通常の解雇の場面と同様の理由から、解雇通知書を交付することをおすすめします。
試用期間中の解雇も「解雇」である以上、「勤務態度が著しく不適格」「適性がない」などの客観的な理由が必要です。
また、試用期間中でも雇用契約は成立していますから、予告義務が発生する時点か否かにかかわらず、解雇の意思表示があったことは明確にしなければなりません。
試用期間だから口頭で十分と考えず、必ず書面を交付してトラブルを防ぎましょう。
6. まとめ:解雇通知書で悩んだら弁護士に相談
解雇通知書は、従業員にとっても会社にとっても大きな影響を及ぼす大切な書面です。手続きを誤ると、「解雇が無効になる」「高額の未払い賃金を請求される」といったトラブルに発展する可能性もあります。
「どこまで理由を書くべきか」「渡し方はこれで問題ないか」など、迷うポイントは企業ごとに異なります。だからこそ、解雇通知書の作成や渡し方で不安がある場合は、労働問題に詳しい弁護士に早めに相談することをおすすめします。
よつば総合法律事務所では、多数の企業様と顧問契約を締結しています。実際に当事務所にご相談いただくことで、「たった一度の相談で悩みがクリアになった」と言っていただけるケースも少なくありません。初回のご相談は無料です。
「解雇通知書をどうすればよいか不安」
「社員とのトラブルをこじらせたくない」
そんなときは、お一人で抱え込まずにぜひお気軽によつば総合法律事務所までご相談ください。皆様が早期に納得のいく解決ができるよう、全力でサポートいたします。