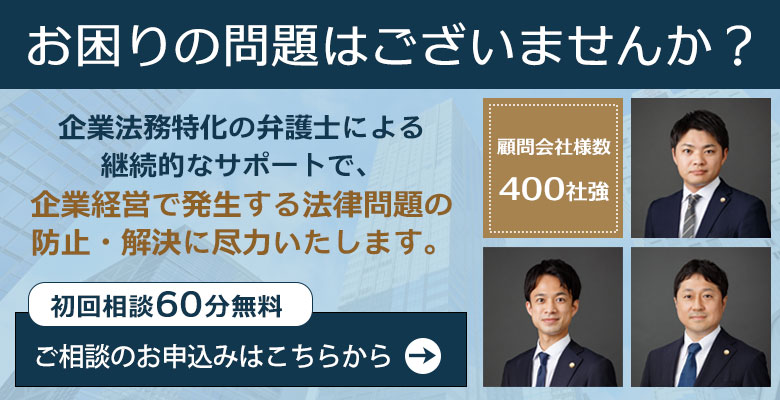株主代表訴訟とは、取締役や監査役などが会社に損害を与えたと株主が考えたときに、会社に代わってその責任を追及する裁判手続です。会社法に基づく制度であり、一定の条件を満たす株主であれば誰でも提訴が可能です。
会社が不祥事を起こした際は、株主による代表訴訟が話題になることがあります。株主代表訴訟は会社にも役員にも大きな影響を与えるものですが、短期間に迅速かつ的確な判断を求められる難しさがあります。
この記事では、株主代表訴訟の基本や訴訟の流れ、提訴請求や訴訟を受けたときに会社がとるべき対応をわかりやすく解説します。
さらに、よつば総合法律事務所が実際に解決した株主間紛争の事例も紹介しますので、自社の対応を検討する際の参考にしてください。
目次
1. 株主代表訴訟とは?
株主代表訴訟は、役員(取締役・監査役・執行役など)が職務上の義務に違反して会社に損害を与えたときに、株主が会社や監査役に代わって役員の責任を追及する訴訟です。
法律上、役員は会社に対して以下の義務を負っています。
- ① 善良な管理者の注意をもって職務を行う義務(善管注意義務)
- ② 忠実に職務を執行する義務(忠実義務)
- ③ 法令や定款を守る義務
役員がこれらの義務に違反して会社に損害を与えた場合、会社に対してその損害を賠償する責任を負います。
責任追及は、本来は会社や監査役が行います。しかし、役員同士の馴れ合いや力関係から責任追及が行われないこともありえます。そのような場合に、株主が会社のために訴訟を提起できる制度が株主代表訴訟です。
経営陣に一定の緊張感を与え、不適切な経営行為によって会社に損害が生じることを防ぐ目的があります。

2. 株主代表訴訟を起こすための要件
株主代表訴訟は、誰でも自由に起こせるわけではありません。会社法で定められた以下の要件を満たす必要があります。
① 条件を満たした株主であること
株主代表訴訟を提起できる株主は、公開会社(上場会社)か非公開会社かによって異なります。
公開会社の場合は、6か月以上継続して株式を保有している必要があります。ただし、定款によって保有期間を短縮できます。
保有期間の要件があるのは、株主代表訴訟のためにだけに株式を取得した株主が濫用的に訴訟提起することを防ぐためです。
非公開会社の場合は、株主であれば誰でも提訴できます。
非公開会社では、株式の譲渡は取締役会又は株主総会での承認が必要です。濫訴目的の株主は排除できるため、保有期間要件はありません。
なお、公開会社・非公開会社を問わず、訴訟の間は株主である必要があります。
② 不正な目的でないこと
株主代表訴訟は会社の利益を守るための制度です。株主や第三者が不正な利益を得る目的や、会社に損害を与える目的で提訴することは認められません。
③ 代表訴訟で追及できる責任内容であること
株主代表訴訟の対象とできる訴えは、会社法に定められており、役員等に対する責任追及が典型例です。
利益供与を受けた株主に対する利益返還請求や、不公正な払込金額で株式を引き受けた者に対する差額支払請求なども対象となります。
④ 法令で定める書面による提訴請求を行うこと
株主代表訴訟は、会社が役員等への責任追及を怠っている場合に、株主が会社に代わって訴訟を提起する制度です。そのため、株主は、まずは会社に対して「役員等に対し、その責任を追及する裁判を起こして欲しい」と請求しなければならないのが原則です。これを提訴請求といいます。
提訴請求は、書面のほか、メール送信などでも可能です。電話やFAXは認められていません。
提訴請求には、次の内容を記載しなければなりません。
- (1) 提訴請求の名宛人
- (2) 被告となるべき者
- (3) 請求の趣旨・請求を特定するために必要な事実
提訴請求の名宛人は、どのような機関設計の会社か、誰の責任を追及するかによって異なります。
たとえば、監査役がいる会社で、取締役の責任を追及した場合、提訴請求は監査役を名宛人とします。監査役の責任を追及したい場合は、(代表)取締役を名宛人とします。
3. 株主代表訴訟の流れ
ここでは、株主代表訴訟の大まかな流れをご紹介します。
3.1 ① 提訴前の請求(提訴請求)
株主代表訴訟を起こすには、まずは会社に対して提訴請求をする必要があります。
提訴請求から60日以内に会社が責任追及の訴えを提起しないとき、株主は裁判所に自ら訴えを提起できるようになります。
ただし、60日を待っていたのでは会社に回復することができない損害が生じるおそれがあるときは、提訴請求をせずに株主代表訴訟を提起できます。会社の役員に対する損害賠償請求が時効で消滅してしまうような場合です。
3.2 ② 会社において責任追及等の訴えを提起するかの検討
提訴請求を受け取った会社は、役員等に対して責任追及の訴えを起こすか否かを決定します。
訴えを起こさないと決めた場合で、株主からその理由を求められたときは、その理由などを書面等で回答しなければなりません。
3.3 ③ 裁判所への提訴
提訴請求から60日以内に会社が訴訟を提起しないときは、株主は、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に訴えを提起します。
提起の際は、請求額にかかわらず、一律1万3000円の手数料(印紙代)を裁判所に納めます。請求額に応じて手数料が変わる通常の損害賠償請求訴訟と比べると、負担は軽めです。
また、訴えを提起した株主は、会社に対して訴訟提起の事実を通知(訴訟告知)する義務があります。これにより、会社も訴訟の存在を認識でき、必要に応じて対応を検討することができます。
3.4 ④ 会社の訴訟関与
株主代表訴訟は、株主が役員等を訴える裁判であり、会社は原則として当事者になりません。
しかし、役員等を訴えるべきは本来会社であるため、会社は、原告である株主側に当事者として参加することができます。他方で、役員等に責任がないと考える場合は、被告である役員側をサポートするために裁判に参加することもできます。
訴訟告知を受けた会社は、その旨を公告するか、株主に通知する義務があります。非公開会社では公告はできず、各株主に通知しなければなりません。
通知を受け取った株主は、代表訴訟を提起した原告側に当事者として参加することができます。
3.5 ⑤ 裁判の終了
裁判は、基本的に和解か判決によって終了します。
和解による終了
株主代表訴訟であっても、株主と役員等との間で和解をすることができます。
会社が和解の当事者でない場合、裁判所は会社に対し、和解の内容を通知し、かつ、和解に異議があるときは2週間以内に異議を述べるべき旨を催告します。
期間内に会社が異議を述べたときは和解の効力は会社には及ばず、異議を述べなかったときは会社にも和解の効力が及びます。
判決による終了
判決の場合は、株主の勝訴・敗訴にかかわらず、その効力が会社にも及びます。
株主が勝訴した場合、つまり役員等の責任が認められた場合、役員等の損害賠償は会社に対して行われます。代表訴訟を行った株主に対して金銭が支払われるわけではありません。
ただし、勝訴した株主は、会社に対し、相当な範囲の弁護士費用や調査費用を請求することができます。
一方で、株主が敗訴し、かつ悪意で訴えを起こしたと認められた場合には、会社に対して損害賠償義務を負うことがあります。
4. 株主代表訴訟の具体例
ここでは話題になった株主代表訴訟をいくつかご紹介します。
① TOYO TIRE代表訴訟
TOYO TIRE(旧東洋ゴム)は、子会社の製品が国の基準に適合していなかったにもかかわらず、出荷停止の判断をしませんでした。
株主は、経営陣の判断が会社の信用を毀損したとして、会社に対して提訴請求をしたものの、会社が応じなかったため、経営陣に対して損害賠償を求めて株主代表訴訟を提起しました。
大阪地裁は、令和6年1月26日、出荷停止の判断をしなかった経営陣の責任を認め、約1億円の損害賠償を命じました。
② 世紀東急工業代表訴訟
世紀東急工業は、価格カルテルにより、公正取引委員会から約29億円の課徴金納付命令を受けました。株主は会社に対し、経営陣の責任追及を求めて提訴請求をしたものの、会社がこれに応じなかったため、株主代表訴訟を提起しました。
東京地裁が経営陣の責任を認めたため、経営陣が控訴し、会社も訴訟に参加しました。しかし、東京高等裁判所も令和5年(2023年)1月26日、カルテルは会社ぐるみで行われたものであるとして、経営陣に対して約18億円の支払いを命じました。
経営陣らは最高裁に上告しましたが、最終的に和解が成立しています。
③ 積水ハウス株主代表訴訟
報道でも大きく取り上げられ、ドラマにもなった、積水ハウスが地面師グループから土地の購入代金をだまし取られた事件です。
積水ハウスの株主は、稟議書の決済に経営判断のミスがあったなどとして、経営陣に対して55億円の損害賠償を求める株主代表訴訟を提起しました。
東京高等裁判所は、令和4年(2022年)12月8日、経営陣の責任を否定しました。会社の規模や体制等からすれば、部下の報告を信頼したとしても経営判断に誤りはないことなどが理由です。
5. 株主から提訴請求を受けた会社がとるべき対応
株主から提訴請求を受け取った場合、会社はこれを漫然と放置するのではなく、内容の適法性や責任追及の必要性について慎重に調査・検討し、適切な対応を取る必要があります。
5.1 提訴請求に応じるかどうか検討
まず、提訴請求が会社法で定められた要件(代表訴訟を提起できる株主であるか、提訴請求に必要な事項が記載されているかなど)を満たしているかを確認します。
また、不正な利益を図る目的や、会社に損害を与える目的の提訴でないかも検討すべきです。
そのうえで、株主が主張する役員等の責任の有無について、次のような観点から実態を調査・評価する必要があります。
- 社内資料・議事録の確認
- 関係者へのヒアリング
- 弁護士への相談、法的評価
- 証拠書類の保存
役員間の私的な関係性に左右されて請求を退けたと判断されると、監査役や他の取締役もその判断に対して任務懈怠責任を問われる可能性があります。そのため、判断は客観的かつ誠実に行うことが不可欠です。
5.2 提訴請求に応じる場合の対応
会社が提訴請求に応じると判断した場合、速やかに責任追及等の訴えを提起する必要があります。会社法では、提訴請求から60日が経過すると株主自身が株主代表訴訟を提起できるようになるため、その前に責任追及等の訴えを提起するのが望ましいといえます。
また、訴えを提起した際には遅滞なく公告するか、株主に通知することが必要です。非公開会社では公告はできず、株主への通知が必須なので注意しましょう。
この義務を怠ったり、虚偽の公告・通知を行った場合は、100万円以下の過料が科されることがあります。
5.3 提訴請求に応じない場合の対応
提訴請求から60日以内に会社が責任追及等の訴えを提起しない場合において、株主から理由の開示を求められたときには、遅滞なく当該訴えを提起しない理由を書面または電磁的方法で通知する必要があります。
通知には、次の内容を記載します。
- 会社が行った調査の内容(判断の基礎となる資料を含む)
- 被告となるべき者の責任や義務の有無についての判断と理由
- 責任があると判断したにもかかわらず訴えを提起しない場合はその理由
通知を怠ったり、虚偽の内容を通知した場合も、100万円以下の過料が科されることがあります。
さらに、会社は株主代表訴訟が提起されることを見据え、証拠保全や今後の訴訟対応の準備を進めるべきです。

6. 株主代表訴訟が提起された場合に会社がとるべき対応
株主代表訴訟が実際に提起された場合、会社は他人事として静観するのではなく、自社の立場や今後の経営に及ぼす影響を踏まえ、慎重かつ戦略的な対応が求められます。
ここでは、代表的な3つの対応策について解説します。
6.1 濫用的な提訴への対策を検討
株主代表訴訟は、会社や株主全体の利益を守るための制度ですが、会社に嫌がらせをする目的や、特定の株主や第三者の利益を図るためだけに提起される濫用的な提訴も存在します。
このような訴えに対しては、会社や被告役員は適切な防御策を講じることができます。
① 権利濫用の主張
株主代表訴訟が、株主や第三者の不正な利益を図る目的や、会社に損害を与える目的で提起された(権利の濫用にあたる)と認められる場合、その請求は却下されます。
会社は、訴訟がこのような目的で提起されたと判断したときは、裁判において権利濫用であると主張し、請求を却下するよう求めることができます。
なお、不当な株主代表訴訟によって会社が損害を被った場合、会社は株主に対して損害賠償請求をすることもありえます。
② 担保提供命令の申立て
被告役員は、株主が悪意で訴訟を提起したと疎明(一応の確からしさを示すこと)できる場合、裁判所に担保提供命令を申し立てることができます。
裁判所が担保提供を命じた場合、株主は担保金を納める必要があります。担保金が払われない場合、裁判所は訴えを却下することができます。
担保提供命令は、訴訟が濫用的と認定され、株主に損害賠償義務が生じた場合の支払い確保を目的とするものであり、濫用的な提訴を牽制する有効な手段となります。
6.2 共同訴訟参加や補助参加を検討
株主代表訴訟が提起された場合、会社はそのまま静観するのではなく、訴訟に参加して自社の立場を明確にすることができます。この「訴訟参加」には大きく分けて2種類があります。
株主側への参加(共同訴訟参加)
会社は役員に責任があると考える場合、原告である株主の側に立って共同訴訟参加することができます。役員の責任を追及すべきは本来会社であるからです。共同訴訟参加によって、訴訟活動に直接関与し、証拠提出や主張立証を行えるようになります。
もっとも、株主代表訴訟に至ったということは、提訴請求には応じないと会社が判断したことになります。会社が原告株主に共同訴訟参加するケースはあまり想定できないでしょう。
役員側への参加(補助参加)
会社が「役員等の責任はない」と考える場合、被告である役員等を支援する形で補助参加することもできます。
監査役設置会社や指名委員会等設置会社では、補助参加には監査役等の同意が必要となる点に注意しましょう。
6.3 和解通知への異議申立てを検討
株主代表訴訟において和解をする場合で、会社が和解の当事者でないときには、裁判所から会社に対して和解内容が通知されます。
会社は、通知を受けてから2週間以内に書面で異議を述べなければならず、期間内に異議申立てをしなかった場合は、会社が和解を承認したものとみなされ、和解の効力が会社にも及びます。
したがって、会社としては次のような点を考慮して迅速に対応する必要があります。
- 和解内容が会社に及ぼす経済的負担
- 役員等の責任追及の可否や企業統治への影響
- 将来の再発防止策や株主との関係への波及効果
- 企業イメージやステークホルダーへの説明可能性
会社が訴訟に参加しない場合でも、訴訟の経過は常に把握しておき、和解案が提示された際に速やかに社内で協議・判断できる体制を整えておくことが重要です。
7. よつば総合法律事務所の株主間紛争の解決事例
よつば総合法律事務所が解決した株主間紛争の事例をご紹介します。
他にもたくさんの株主間紛争の取扱い実績があります。悩んだら、まずは一度お問い合わせください。
8. まとめ:株主代表訴訟は弁護士に相談
株主代表訴訟は、会社に代わって株主が役員等の責任を追及する強力な制度であり、適切に対応しなければ企業経営に大きな影響を及ぼしかねません。株式の保有要件や書面による提訴請求、会社が60日以内に対応する義務など、会社法で定められた手続きを正しく理解し、迅速に行動することが重要です。
また、株主代表訴訟が提起された場合には、濫用的な訴えへの対応や、会社としての訴訟参加、和解通知に対する異議申立てなど、状況に応じた判断が求められます。これらの判断を誤ると、経営陣自身が任務懈怠責任を問われるリスクもあるため、慎重かつ戦略的な対応が欠かせません。
株主から提訴請求の通知が届いたとき、あるいは訴訟が提起されたときは、できるだけ早い段階で企業法務に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、請求内容の精査や社内調査のサポート、訴訟対応方針の立案、株主との交渉まで一貫して支援することが可能です。
よつば総合法律事務所では、株主代表訴訟や株主間紛争に関する豊富な解決実績があります。経営者・役員の皆さまは、トラブルが大きくなる前にぜひご相談ください。