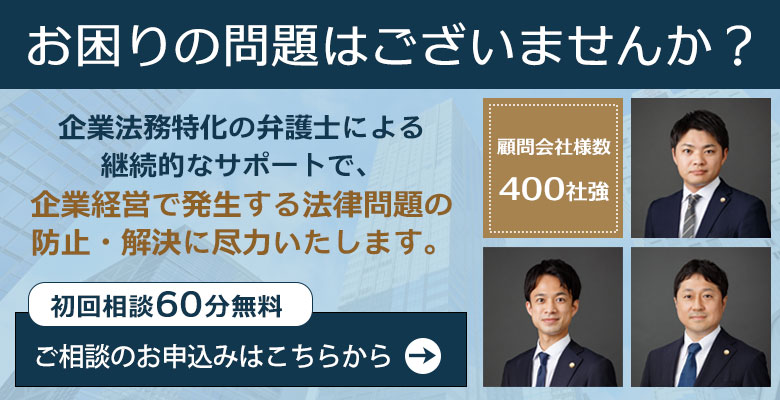従業員による横領は、会社に大きな損害を与えるだけでなく、社内の信頼関係や企業の信用をも揺るがす深刻な問題です。対応を誤れば「解雇無効」や「不当な処分」と争われ、二次被害につながるおそれもあります。
本記事では、横領が疑われたときの初動対応から、事実が確定した場合の損害賠償請求・懲戒解雇・刑事告訴の手続き、さらに再発防止策まで、経営者や管理職が押さえておくべき実務対応を弁護士が解説します。
1. 従業員の横領が疑われる場合の対応
従業員の横領が疑われる場合には、まずは落ち着いて、事実確認と証拠の確保から進めましょう。結論を急ぐと不適切な対応となってしまうことがあります。
1.1 客観的な証拠を集める
横領の疑いが生じた場合、最初に着手すべきは客観的な証拠の収集です。証拠が不十分な状態で懲戒処分や刑事告訴に踏み切ると、逆に不当解雇や名誉毀損などのリスクを招く可能性があります。
また、被害額の立証が困難となり、損害賠償請求に不利に働くことも少なくありません。
対応の基本は、「人の記憶より物品や金銭の記録」を優先することです。関係資料、履歴、記録媒体などを時系列で整理・蓄積し、事実関係を明確にすることが重要です。
基本的な証拠整理の流れ
証拠は、次の順序で整理すると効率的です。
① 会計・資金に関する記録の整理
まずは出納帳、仕訳帳、伝票、銀行明細、入出金データなど、会計や資金の動きを示す記録を時系列で整理します。最も客観性が高く、初動の基礎資料となります。
② 操作・承認に関する記録の確認
次に、レジや会計ソフトの操作ログ、承認履歴、権限設定の変更記録など、操作や承認の履歴を時系列で把握します。これにより、関係者の関与状況や意思決定の経緯を裏付ける手がかりを得られます。
③ 在庫や現物に関する管理記録との照合
在庫台帳、棚卸差異の記録、在庫移動の履歴、現物点検メモなどを突き合わせて整合性を確認します。金銭の動きと物の動きをリンクさせ、事実関係を明確にします。
④ 施設や端末の記録で補強
最後に、防犯カメラ映像、入退室ログ、社内端末のアクセス履歴、メール送受信記録などを確認し、証拠の抜けを補います。これにより客観的証拠の一貫性と信頼性が高まります。
通報から調査を始める場合
内部通報などを契機として調査を開始する際は、次の事項を具体的に整理・記録することが重要です。
- 誰が(行為者)
- いつ(発生日・期間)
- どこで(場所・部署など)
- 何を(対象物・不正内容)
- いくら(金額・数量)
- どのような手口で(方法・経路)
推測や伝聞情報については、事実情報と混在させず、別に分けて整理することが重要です。
また、調査中であることが対象従業員に伝わると、証拠隠滅や口裏合わせといったリスクに直結するため、調査メンバーの人選や、聴取対象者の順序については慎重に検討する必要があります。
手口ごとの裏取り
横領行為は一見単純に見えても、実際には多様かつ巧妙な手口で行われることがあります。一般的な証拠や通報内容の整理に加え、典型的な手口ごとに以下のような裏取りを行うことが有効です。
① 経費水増し型
- 領収書の真正性(実在の店舗か、改ざんの有無)を確認
- 支出が業務上必要であるかの妥当性を検討
- 同一内容の二重計上がないかを精査
② 売上取消し型
- 売上取消ログとレジ内現金残高との突合
- 日計表との整合性確認
- 繰り返し発生している傾向がないか分析
③ 集金着服型
- 顧客別の回収予定一覧と実際の銀行入金状況を比較
- 差額・未入金分の明確化
- 関連する伝票や受領記録の裏付け確認
④ キックバック型
- 取引先への照会の実施(価格・数量の妥当性を確認)
- 見積から発注、検収までの流れを精査
- 関連メール、チャット等のやりとりを保全
⑤ 外部関与が疑われるケース
- 振込先マスタ等の更新履歴を確認
- 社外協力者との通信・接触履歴を調査(メール・通話・訪問など)
- IT部門との連携でアクセス権限の範囲も確認
あわせて、次の証拠管理ルールを徹底することが、後日の法的対応における証拠能力の確保につながります。
- 領収書・請求書等の原本を確保し、スキャン控えを作成
- 取得者、取得日時、取得方法を記録
- 電子的記録について改ざん防止の保全処理
電子データの取り扱いに注意
電子データは、改ざんの有無を立証できるかどうかが証拠能力を左右します。取得方法や保管状況に不備があると、証拠価値が失われるリスクが高いため、取得から保管・分析に至るまで、一貫した適切な対応が求められます。
そのため、次の点を徹底することが重要です。
① 原本の封緘・隔離と複製による分析
調査・分析は複製データを用い、原本には一切手を加えないこと。原本は隔離のうえ保全し、改ざん防止措置を講じます。
② 映像・ログの一括取得と整合性確認
対象期間を明確にしたうえで、ログや映像データは一括で取得します。部分的な取得では情報の欠落や恣意的取得を疑われるおそれがあるため、取得対象の完全性と整合性を確認してください。
③ 取得記録の作成と保存
取得者、取得日時、取得方法、保管先を含めた取得記録を正確に残すことで、証拠の真正性・信頼性を担保することができます。
1.2 本人からの事情聴取
一定の裏づけが揃った段階で、対象従業員への聴取を実施します。聴取は原則として事前に予告せず、呼び出しから実施までの対応を速やかに行うことが重要です。
不必要に警戒心を与えると、証拠隠滅や他の関係者への働きかけ等のリスクが生じるおそれがあります。そのため、対象者への接触時の対応、呼び出しの手順、聴取場所や時間帯の配慮も含め、慎重に計画を立てて実施する必要があります。
聴取前に準備すべきこと
聴取をする前には入念な事前準備が欠かせません。「聴取計画」を用意し、あらかじめ次のことを決めておきましょう。
① 聴取の目的の共有
聴取の目的が「事実確認」であることを確認し、処分決定の場ではない旨を共有する。
② 対象期間の特定
聴取の対象とする行為の期間を設定し、関係資料を準備します。
③ 主要論点の整理
確認すべき論点(例:手口、金額、関与者、資金の流れなど)をリストアップし、質問の方向性を明確にします。
④ 提示予定資料の選定
聴取時に提示予定の証拠資料を整理し、どの部分について説明・確認を求めるかを事前に決めておきます。
⑤ 対応体制の構築
最低でも、質問役と記録役の2名体制とし、役割分担を明確にしておきましょう。
⑥ 記録方法の確認
メモによる記録を基本とし、可能であれば録音も併用します。録音については、社内規程の確認のうえ、冒頭で説明・同意を得ることが原則です。
このように計画的に準備を行うことで、聴取が円滑かつ適正に進行し、後日のトラブルや争点化を防止することが可能となります。
聴取の進め方のポイント
事情聴取の進行で意識したいのは次の3点です。
- ① 任意性を確保し、脅迫的な言動や処分を示唆するような言い回しは避けること
- ② 客観的な証拠をもとに、事実確認を積み上げること(自白に依存しない進行)
- ③ 発言内容と確認された事実を分けて記録し、評価的な表現を用いないこと
対象者が横領の事実を否認する場合は、金額、日時、承認者、使用端末、操作ログなど、具体的な要素ごとに確認を行い、矛盾点を丁寧に整理していきます。
感情的な押し引きは避け、必要に応じて弁護士の同席や追聴取も検討します。
一方、対象者が事実を認めた場合でも、次の項目について一つずつ確認し、記録に残しておくことが重要です。
- いつ
- どこで
- 何を
- いくら
- どんな方法で
- 誰と
加えて、返還の意思とその方法についても確認し、明確に記録します。
後日「言った、言わない」といった争いを避けるためには、本人の自筆による始末書を取得するのが有効です。既製の様式に署名のみを求める形式よりも、本人が作成した文書のほうが、証拠としての信頼性が高まる傾向にあります。
聴取の目的は、事実の確定と、それに基づく今後の対応(損害賠償、懲戒、刑事告訴など)を検討するための材料を整えることにあります。結論は急がず、記録を丁寧に残すことを心がけましょう。
1.3 自宅待機命令
横領の疑いが濃く、追加被害や証拠隠滅、関係者への働きかけが懸念される場合には、対象従業員に自宅待機を命じることがあります。
これはあくまで調査のための一時的な就業制限であり、懲戒処分に該当するものではありません。この点を通知文面で明確にしておくと、後日の紛争を防ぎやすくなります。
就業規則の確認と通知書の記載事項
まず、就業規則に「調査を目的とした自宅待機」に関する明示的な条項が設けられているかを確認してください。該当する根拠条項がある場合は、通知書にその条項番号を明記したうえで、次の事項について具体的に記載する必要があります。
① 自宅待機の性質
調査のための一時的な措置であり、懲戒処分ではないことを明示します。
② 自宅待機の期間
開始日および終了予定日、ならびに延長の可能性があることについても記載しましょう。
③ 禁止事項
自宅待機期間中における禁止事項として、次のような内容などを具体的に記載します。
- 関係者との直接・間接的な連絡
- 社内システム・データへのアクセス、閲覧、複製
- 証憑類(領収書や請求書などの証拠書類)や資料の社外持出し
④ 会社財物の返還
業務用端末、記録媒体、印章、入退室カード、鍵など、会社から貸与された物品の返却を求める旨を明記します。
⑤ 連絡方法
指定された連絡窓口・時間帯・手段(電話、メール等)も明確にしておきましょう。
⑥ 賃金の取扱い
調査目的で自宅待機を命じる場合、会社の都合による休業と判断されるため、原則として賃金は全額支払う必要があります。
懲戒処分として出勤停止を命じる場合とは異なり、安易に無給とすると、後に賃金未払いとして法的な問題に発展するリスクが非常に高いため、慎重な判断が求められます。
⑦ 有給休暇の扱い
本人からの申し出がある場合には取得可能です。ただし、会社側からの一方的な有給休暇指定はできないことに留意しましょう。
なお、上記に該当する規定が就業規則上に明文化されていない場合は、運用上のトラブルを防ぐためにも、事前に規程の整備を検討することが望まれます。
自宅待機命令と同時に行う保全措置
自宅待機命令の発出と並行して、証拠保全およびリスク管理の観点から、以下のような対応を速やかに実施します。
- ① 社内システムに関連するアカウント(VPN、SaaS、承認システム等)の停止
- ② メール、会計システム、ワークフローに関する権限の棚卸と監査ログの保全
- ③ 物理的なアクセス手段(社屋の鍵、ICカード、社用端末等)の回収
- ④ 業務用アプリやクラウドとの自動同期が設定されている私物端末(BYOD)の利用制限(社内規程の範囲内で対応)
- ⑤ 防犯カメラ映像および入退室記録の対象期間分の一括保存(取得漏れや欠落の有無もあわせて確認)
これらの措置は、調査の中立性と安全性を確保するために必要なものであり、可能な限り聴取前・通知前に完了しておくことが望まれます。
なお、社内への情報共有については必要最小限にとどめ、本人のプライバシーに配慮しつつ、職場内での混乱や臆測を招かないよう十分注意することが重要です。
賃金の取扱いと在宅業務の併用
調査を目的とした自宅待機を命じる場合、原則として賃金を支給する運用が安全です。たとえ就業規則上に無給または減額に関する条項が存在していたとしても、実際の適用にあたっては、対象者の事情や具体的な状況に照らして、個別に相当性を検討することが不可欠です。
また、自宅待機中に在宅での業務継続を指示する場合には、次の点に留意する必要があります。
① 情報漏えいの防止策
アクセス権限の制限、私物端末の使用可否、ネットワーク制御などの具体的な対応を講じること
② 証拠保全との両立
在宅業務中であっても、不正調査におけるログ監査体制やアクセス履歴の記録体制を整備しておくこと
これらの配慮を適切に行うことで、企業の権利保護と、対象従業員への適正な対応とのバランスを確保することが可能となります。

2. 横領の事実が確定した場合の対応
調査で横領の事実が明らかになり、十分な証拠がそろったら、会社としては次の3つの対応を検討することになります。
- ① 損害賠償請求
- ② 懲戒解雇
- ③ 刑事告訴
どの手段を選択するか、または複数を併用するかは、被害の内容、従業員の属性、会社の方針等を総合的に踏まえて判断する必要があります。
2.1 損害賠償請求
横領を行った従業員に対しては、損害賠償請求を行うことが可能です。具体的には、横領された金銭や物品の返還、物品が現存しない場合は、その価値に相当する額の賠償を求めることになります。
この場合、すぐに裁判に踏み切るのではなく、まずは話し合いの場を設けることが重要です。なぜなら、従業員が横領に及ぶ背景には、もともと金銭的に困っている事情があることが多く、横領した金銭がすでに使い切られているケースが少なくないからです。
さらに、本人が不動産や預金などの資産を持っていないことも多く、仮に裁判で勝訴判決を得たとしても、実際に回収できない可能性が高いのです。
そのため、分割払いの合意や返済計画の策定を話し合いで取り決め、少しずつでも回収を進める方が現実的な場合が多いといえます。
身元保証人への請求はできるのか?
従業員の親族などとあらかじめ身元保証契約を結んでいる場合には、その保証人に対して損害賠償を請求できる可能性があります。もっとも、請求が常にそのまま認められるわけではなく、契約の有効性や責任範囲についてはいくつかの制限があります。
まず、保証期間については法律で制限が設けられており、契約で期間を定めなかった場合は3年、定めた場合でも最長5年までとなります。自動更新の定めは法律上の効力が認められないため、更新手続きを怠ると、いざ請求しようとしても契約期間が切れていた、という事態になりかねません。
また、保証人が負う責任の範囲について、裁判所は慎重に判断します。会社側の監督体制に不備がなかったか、契約を結ぶ際に注意喚起をしていたか、といった事情が考慮され、責任が限定されることがあります。実際の裁判例でも、全額の連帯責任を認めたものがある一方で、損害額の一定割合に減額されたケースも少なくありません。
さらに、契約書に「連帯保証契約書」などと記載していた場合でも、実質的な内容が身元保証契約に該当すると判断されれば、裁判所は名称にかかわらず身元保証契約として取り扱う可能性があります。契約書の名称ではなく、中身が重視される点にも注意が必要です。
このように、身元保証契約を活用して請求できる場合もありますが、その効力や範囲は制限があるため、請求を検討する際には契約内容や有効期間を丁寧に確認することが重要です。
2.2 懲戒解雇
従業員による横領が事実として認められた場合、会社としては懲戒解雇を検討することが可能です。
ただし、懲戒解雇は労働者にとって最も重い処分にあたるため、その有効性については厳しく判断されます。性急に進めると「懲戒権の濫用」と評価され、無効とされるリスクがあるため、慎重な対応が不可欠です。
就業規則の確認が出発点
まずは就業規則を確認します。懲戒解雇事由に「横領」「着服」「職務上の非違行為」などの記載があれば、その規定に基づいて懲戒解雇を検討できます。明示的な記載がない場合でも、「その他これに準ずる行為」といった包括規定に該当する可能性があります。
一方で、懲戒事由が限定列挙されており、横領に関する記載が一切なければ、懲戒解雇を行うことは困難です。その場合は、普通解雇を検討する必要があります。
普通解雇は懲戒処分とは異なり、信頼関係を根本から破壊した行為として雇用契約を継続できないと判断される場合に行う解雇です。
解雇が無効とされるリスクと実務的なポイント
懲戒解雇・普通解雇のいずれにおいても、その有効性は「解雇権濫用法理」に基づき判断されます。
労働契約法には「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効」と定められており、裁判所はこの規定に沿って厳格に審査を行います。横領の金額や期間、手口の重大性、就業規則の周知状況、調査や事情聴取の適正さ、弁明の機会の有無、他の処分で足りないかどうかなどが、判断のポイントとなります。
解雇が無効と判断されると、法的には「解雇は最初から存在しなかった」と扱われます。その結果、従業員の雇用関係は継続しているとされ、職場への復帰が必要になるほか、解雇から現在までの未払い賃金を遡って支払う義務が発生する可能性があります。
復職にあたっては、業務や職場環境の調整が必要となり、社内の混乱や再発防止対応にも追われるケースが少なくありません。
こうしたリスクを避けるためには、就業規則の内容と運用実績を確認し、聴取記録や証拠を十分に確保しておくことが欠かせません。さらに、弁明の機会をきちんと与えるなど、手続きを適正に進めることが重要です。
また、懲戒解雇に踏み切るか、普通解雇で対応するか、あるいは合意退職や和解を優先するかといった判断は、個別の事案によって異なります。判断を誤れば、後に大きな負担を抱えることになりかねません。可能であれば弁護士に相談し、リスクを事前に把握したうえで慎重に進めることが望まれます
2.3 刑事告訴
従業員による横領が明らかになった場合、会社としては刑事告訴を検討することもできます。業務上預かった金銭や物品を不正に使いこんだり処分したりした場合、刑法が定める「業務上横領罪」(刑法253条)に該当し、10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
会社が被害者として警察などに刑事告訴を行うことは、捜査機関が本格的に捜査を開始する極めて重要なきっかけとなります。
刑事告訴のメリット
刑事告訴には、会社側にとって大きく2つのメリットがあります。
① 賠償の可能性が高まること
メリットの1つ目は、賠償を受けられる可能性が高まることです。刑事事件では処罰の重さが示談の有無によって左右されるため、被告となった従業員は減刑や執行猶予を得るために、会社に対し損害賠償を申し出るケースが少なくありません。
これにより、民事訴訟では得られなかった弁済を回収できる可能性があります。
② 社内の秩序維持と抑止効果
メリットの2つ目は、社内秩序を維持できることです。会社が毅然と刑事告訴に踏み切ったという事実は、他の従業員に対する強いメッセージとなります。
「不正を働けば刑事責任を問われる」という姿勢を明確に示すことで、再発防止やコンプライアンス意識の向上につながります。
告訴にあたっての留意点
刑事告訴を行うには慎重な判断が求められます。捜査機関がすぐに受理するとは限らず、証拠が不十分な場合や被害が軽微と判断された場合には、告訴が受け付けられない可能性もあります。
また、告訴によって事件が公になることで、企業の信用や評判に影響が及ぶリスクも否定できません。
そのため、刑事告訴に踏み切るかどうかは、被害額の大きさ、従業員の地位、再発防止の必要性、回収見込みなどを総合的に検討する必要があります。特に、民事での損害賠償請求との併用をどう設計するか、示談の可能性をどう扱うかは、弁護士の助言を踏まえて進めることが望ましいでしょう。
3. よくあるご質問
従業員による横領が発覚した際、会社としてどのような対応を取るべきか。判断に迷いやすい場面に備えて、特に多く寄せられるご質問を以下にまとめました。
3.1 本人から聴取をする場合、事前に予告すべきでしょうか?
原則として、聴取を事前に予告すべきではありません。
聴取の予定をあらかじめ伝えてしまうと、対象従業員が証拠を隠滅したり、関係者に口裏合わせを働きかけたりするリスクが高まります。そのため、呼び出しから事情聴取までの流れはできるだけスムーズに行うことが望ましいです。
3.2 給与から天引きして返金させることは可能ですか?
原則として、会社が一方的に給与から天引きすることはできません。
労働基準法では「賃金全額払いの原則」が定められており、税金や社会保険料などを除き、会社が一方的に給与を差し引くことは禁じられています。そのため、横領による損害の返済を給与から天引きすることは原則不可能です。
もっとも、本人が自発的な意思に基づいて返済に同意し、その金額や方法について合意が成立している場合は、例外的に給与と損害賠償請求権を相殺できる余地があります。
ただし、ここでいう「同意」が真に自主的であったかどうかは、裁判所で極めて厳しく判断されます。会社からの圧力や暗黙の強制があれば、同意は無効とされ、相殺自体が違法と評価されかねません。
したがって、給与との相殺を行うのであれば、次の2点を意識しましょう
- ① 同意が自発的であると客観的に示せる証拠(合意書や経緯の記録など)を残すこと
- ② 金額や返済方法が合理的な範囲にとどまっていること
実務上は、安易な天引きを避け、十分な説明と同意を経たうえで合意書を作成することが、安全な対応策といえるでしょう。
3.3 横領された金額が少なくても懲戒解雇できますか?
金額が少額であっても、懲戒解雇が有効とされる場合があります。
横領などの金銭的不正に対する懲戒解雇の有効性は「被害金額の大小」だけでなく、業種の性質、行為の悪質さ、従業員に求められる信頼性、そして過去の会社の対応とのバランスなどを総合的に考慮して判断されます。
そのため、仮に数千円や数万円といった少額であっても、職務の性質上重大な信頼違反と評価される場合には懲戒解雇が有効と認定されることがあります。
注意が必要なのは、会社がこれまで横領に対して厳格な対応を取ってこなかった場合です。そのような場合は、過去の処分方針との均衡を欠くとして、少額の横領を理由とする懲戒解雇が無効と判断されるリスクもあります。
結局のところ、少額の横領に対する懲戒解雇の有効性は、個々の事案の内容や業務の特性によって左右されます。「金額が少ないから大丈夫」とも「少額でも必ず懲戒解雇できる」とも言い切れません。判断に迷う場合には、弁護士に相談し、会社の事情に即した最適な対応を選ぶことが安全です。
3.4 横領した従業員を懲戒解雇した場合、退職金を不支給にできますか?
一定の条件を満たせば、退職金を不支給とすることは可能です。
ただし、退職金は「長年の勤続に対する報償」としての性格もあるため、単に懲戒解雇になったからといって、自動的に全額不支給とすることはできません。
退職金を不支給にするためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
① 就業規則や退職金規程に不支給事由が定められていること
退職金制度が会社の規程に基づくものである以上、不支給とする根拠も規程の中に明記されていなければなりません。規定がなければ、たとえ横領があったとしても不支給は難しいとされるのが判例実務です。
② 従業員の行為が「著しい背信行為」といえること
単に規程に不支給事由があるだけでは足りません。横領行為が、それまでの勤続功労を帳消しにしてしまうほど重大な背信行為と評価されることが必要です。業務上横領は通常この要件を満たすとされていますが、実際に退職金の不支給が有効とされるかは、具体的な事案ごとに判断されます。
上記の要件を満たしたとしても、裁判例では退職金の全額不支給を認めず、一定割合を減額したうえで支給するにとどまるケースも少なくありません。退職金を不支給とするかどうかについては、弁護士に相談し、リスクを十分に把握したうえで判断することをおすすめします。
3.5 刑事告訴と損害賠償請求を並行してできますか?
刑事告訴と損害賠償請求は、並行して進めることが可能です。
刑事告訴は、従業員の横領行為について刑事責任を追及し、社会的な制裁を求める手続きです。一方、損害賠償請求は会社が被った経済的損失を回復するための民事的な手続であり、両者は目的が異なるため、同時に進めることに法的な制約はありません。
実務上も、刑事告訴を行うことで捜査機関が動き、横領の証拠が確保される可能性が高まります。その過程で得られた調書や証拠は、民事訴訟においても有力な資料となり、損害賠償請求の立証に役立ちます。また、告訴による心理的なプレッシャーから、従業員が示談や分割返済に応じやすくなるケースもあります。
ただし、刑事手続は警察や検察が主導するため、会社が訴訟戦略を完全にコントロールできるわけではありません。告訴をしたとしても、必ずしも起訴・有罪につながるとは限りません。
そのため、どのタイミングで刑事告訴と損害賠償請求を行うかは、弁護士と相談しながら進めるのが望ましいでしょう。

4. 横領を防ぐための方法
従業員による横領は、一度発生すると回収も処分も難しく、会社に深刻なダメージを与える行為です。だからこそ、発生後の対応に加え、未然に防ぐ仕組みづくりが重要です。
ここでは、会社が取るべき具体的な予防策を解説します。
4.1 横領されないための環境作り
横領は、一度発生すると損失回収も社内の信頼回復も容易ではありません。だからこそ、「問題が起きたら対応する」ではなく、平時から「仕組みで防ぐ」視点が重要です。
次のような土台を整えることで、不正の起きにくい環境を構築できます。
① 職務分掌
入金・出金・承認・記帳・照合をひとりに集中させないことが重要です。特に、小口現金や経費精算は別ルートでの承認を求めるなど、役割分担を徹底しましょう。
② 権限管理の徹底
会計ソフト・ネットバンキング・在庫管理などのアクセス権限は最小限に限定します。また、退職や異動があった際には、入退室・VPN・SaaSアカウントの権限も即時に無効化できる体制を整えましょう。
③ ダブルチェックと痕跡の残る運用
領収書や請求書は原本と電子データを併用して保管し、承認はワークフロー上で記録を残す形に。さらに、銀行残高・日計・在庫などの月次突合をルーチン化しておきます。
差異が出た場合に備えて、「原因の仮説を検討、追加資料収集、再突合」の流れを手順として明文化しておくと、現場の判断がぶれません。
④ ログと可視化
承認・取消・マスタ更新などの操作ログを保存し、定期的な監査を行う体制を持ちましょう。
また、現金・在庫・割引・返品などに関する情報をダッシュボード等で見える化し、管理職にも継続的に共有することで透明性を確保できます。
⑤ 現物の確認システム
在庫の抜き取りを防ぐため、封印シールやランダム棚卸、二人立会の仕組みを導入。
また、社判・印章・ICカード・キャッシュカードなどの重要物品は、台帳に基づいて厳格に管理しましょう。
4.2 身元保証書の作成
横領された金銭の回収可能性を少しでも高めるために、事前に「身元保証書」を作成しておくことが有効です。入社時に従業員に署名を求め、身元保証人を立ててもらうことで、従業員自身に心理的な抑止効果を与えると同時に、不正が発覚した際には保証人に対して損害賠償を請求できる可能性を残すことができます。
ただし、身元保証契約は保証人にとって負担が重いため、法律上は「根保証契約」(ねほしょうけいやく)としていくつかの制限があります。特に注意すべきは次の点です。
① 極度額(上限額)の明記が必須
極度額(賠償の上限額)を契約書に明記しなければ契約が無効となります。したがって、業種や従業員の担当業務に応じて、合理的な上限額を設定することが欠かせません。
② 契約期間の上限と更新管理
次に、契約期間の制限も重要です。契約書で期間を定めなかった場合は3年、定めた場合でも最長5年までとされ、5年を超える記載や自動更新条項は効力を持ちません。したがって、更新を適切に運用する仕組みを会社側で用意しておく必要があります。
③ 保証人の責任は限定的に判断されやすい
身元保証人の責任範囲は裁判例でも限定的に解釈される傾向があります。会社側の監督義務違反や契約時の注意喚起不足があると、保証人の責任は縮小され、結果的に損害額の一部しか認められないケースもあります。
このように、身元保証契約は「横領の抑止策」としては有効ですが、実効性を担保するには契約書の書きぶりや更新管理を厳格に運用することが前提です。採用時や配置転換の際にきちんと再取得するなど、実務に落とし込む工夫が不可欠といえるでしょう。
4.3 就業規則や雇用契約書の見直し
従業員による横領に適切に対応するためには、平時から就業規則や雇用契約書を整備しておくことが欠かせません。
懲戒解雇の根拠は明文化が必須
まず重要なのは、就業規則に懲戒解雇の根拠を明記しておくことです。「横領・着服・背任・不正受領」などの行為を懲戒事由として列挙し、懲戒解雇を含む処分の種類や適用基準を規定しておく必要があります。
さらに、懲戒解雇に至るまでの手続きについても、従業員に弁明の機会を与えることや、事情聴取の方法、証拠収集の流れを明文化しておくことで、処分の有効性を高めることができます。
雇用契約書や誓約書も活用する
就業規則の整備だけでなく、雇用契約書や誓約書においても横領防止に直結する規定を盛り込むことが重要です。たとえば、情報や証憑の持出し禁止、社用端末の適正利用、贈収賄や競業行為の禁止、ログの取得や監査への同意といった条項を明確に定めることで、従業員に対する抑止力を高められます。
これらを契約段階で周知しておけば、違反があった際の対応もスムーズになります。
横領発覚後の対応に備えた規程も必要
横領が発覚した場合に備え、懲戒解雇以外の関連規定も整えておくことが実務的には不可欠です。
調査のために従業員を一時的に就業から外す「自宅待機」の制度については、就業規則に根拠を設け、期間や賃金の取り扱い、禁止事項などを明確にしておくことが望まれます。
さらに、退職金規程についても、横領などの重大な背信行為があった場合には不支給または減額できる旨を定め、その判断基準や割合の考え方をルール化しておく必要があります。
「運用に耐える内容か」が最大のポイント
このように、就業規則、雇用契約書、誓約書、退職金規程、自宅待機規程などを一体として見直すことで、横領を未然に防ぐとともに、発生時の適切な対処が可能になります。
規程は単なる形式ではなく、実際の運用に耐える内容であることが求められるため、弁護士にチェックを依頼し、自社の実態に即した内容へと整備しておくことをおすすめします。
4.4 不正を通報できる窓口の設置
従業員による不正は、周囲が気づいていても声を上げにくいことも少なくありません。小さな組織ほど人間関係が近く、特に管理職など地位のある人が関わっている場合、部下が「指摘すれば自分の評価に響くのではないか」「配置転換などで不利益を受けるのではないか」といった不安から、通報をためらうケースが多く見られます。
こうした状況を防ぐためには、社外の第三者を通報窓口として設けることも有効です。
法律事務所などを通報窓口として指定すれば、通報者の身元や通報事実が社内に漏れるリスクを抑えられ、安心して情報を寄せられるようになります。その結果、不正を早期に発見して適切に対応でき、組織の自浄作用が働きやすくなるのです。
実務上は、次のような工夫が有効です。
- 社内窓口と外部窓口を併用し、通報者が選べるようにする
- 通報者の秘密保持や不利益取扱いの禁止を規程に明記し周知する
- 匿名や時間外でも通報できるメールフォームなどを設ける
- 受付から調査までの基本的な流れをあらかじめ定めておく
完璧な制度を目指すよりも、まず「従業員が実際に使える制度」を整えることが先決といえるでしょう。
5. まとめ:従業員の横領は弁護士に相談
従業員による横領は、会社に金銭的な損害を与えるだけでなく、社内の信頼関係を崩し、組織全体の風土や信用にも深刻な影響を及ぼします。被害金額の大小にかかわらず、対応を誤れば「解雇無効」や「不当な処分」と争われるリスクもあり、結果的に会社が二重の負担を負うことになりかねません。
そのため、発覚直後から適切な手順を踏み、証拠の確保・事情聴取・処分判断・刑事告訴や損害賠償請求などを慎重に進める必要があります。これらは企業だけで対応しようとすると判断を誤りやすいため、企業法務に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
また、従業員の横領は、起きてから対応するだけでなく、未然に防ぐ仕組みを整えることも重要です。内部統制の見直しや通報制度の整備など、平時からの予防策も弁護士とともに取り組むことで、より安心できる経営体制を築くことができるでしょう。