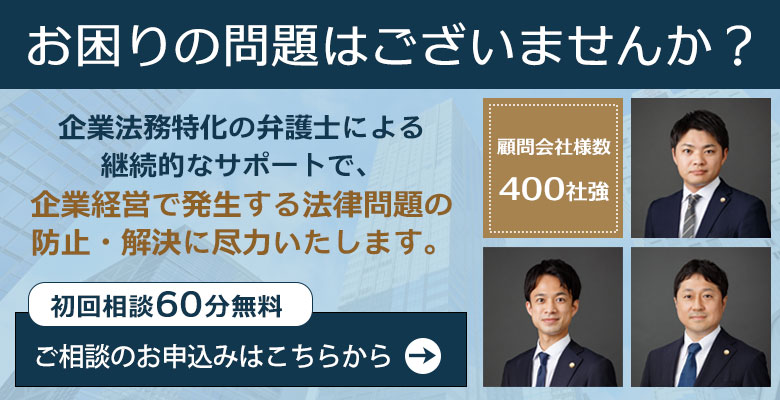企業活動をしていると、一定数、対応に苦慮する「悪質なクレーマー」との関係に悩まされる場面があります。正当なクレームの範囲を逸脱し、執拗な要求や人格を否定する発言、さらには業務妨害が常態化するようであれば、それは「カスタマーハラスメント(カスハラ)」として、明確かつ毅然とした対応が求められる問題です。
このような悪質クレーマーの行為に対して、「どの時点で警察に相談できるのか」「警察は本当に動いてくれるのか」と疑問に思う経営者や担当者の方は多いのではないでしょうか。
警察に相談すべきか否かは、相手の行為がどこまでエスカレートしているか、刑法上の犯罪に該当する可能性があるか、証拠をどれだけ用意できているかなど、いくつかの判断ポイントがあります。
本記事では、悪質クレーマーの被害を警察に相談する際のメリットや、警察が動く可能性のある主な犯罪類型、相談の流れや具体的な準備のポイントまで、企業法務に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
目次
1. 悪質クレーマー対応を警察に相談するメリット
悪質クレーマーによる迷惑行為がエスカレートした場合、警察への相談は非常に有効な手段となります。企業内部だけで対応し続けるには限界があるケースも少なくありません。
ここでは、警察に相談することで得られる具体的なメリットについて解説します。
① その場のトラブルをすぐに鎮静化できる
警察を頼る最大のメリットは、「即効性」です。クレーマーが店内やオフィスで怒鳴ったり、暴れたりしているような状況であれば、110番通報をすれば警察官が現場に急行します。
警察が来るだけで、相手が急に態度を変えたり、その場を離れたりすることも少なくありません。警察がその場に来るという事実自体が、大きな抑止力になるのです。
② 従業員の安全を守れる
悪質なクレームは、内容によっては従業員の精神的なストレスや身体的な被害にもつながります。怒鳴り声、威圧的な態度、執拗な出待ちや電話などが続けば、現場のスタッフは恐怖を感じるようになります。
そうした状況で警察に相談すれば、企業として「従業員の安全を重視している」というメッセージを明確に示すことができます。
③ 法的な判断を仰げる
企業内部では「このクレームはどこまでが許容範囲なのか」「対応しても問題はないのか」と判断が難しいこともあります。特に、相手の言動が「犯罪にあたるのかどうか」という判断は、法的な専門知識がないと迷ってしまうでしょう。
警察に相談すれば、その行為が刑事事件として扱われる可能性があるかどうか、法的観点からの判断を仰ぐことができます。すぐに動いてもらえない場合でも、警察の助言を受けて、今後の対策を練ることが可能です。
④ 記録が残ることで次の一手につながる
警察への相談は、ただの会話では終わりません。相談記録として残ることで、刑事事件化する場合や民事対応をとる場合にも「公的な相談履歴」として活用できます。
さらに、警察に相談することで、証拠としてどういった記録が重要なのか、どのように保存すればよいかなどのアドバイスを受けられることもあります。弁護士と連携しながら証拠を整えるための準備にもつながります。

2. 悪質クレーマーの行為が犯罪になる可能性
悪質なクレームの中には、明らかに刑法上の犯罪に該当する行為も少なくありません。ここでは、クレーマーの行動が該当しうる主な犯罪類型を紹介します。
2.1 不退去罪
不退去罪(刑法130条)とは、正当な理由なく他人の住居や建物にとどまり続けた場合に成立する犯罪であり、企業の店舗やオフィスもその対象に含まれます。たとえば、店員や責任者が「退店してください」と明確に指示したにもかかわらず、顧客がその場に居座って騒動を引き起こすような場合、不退去罪が成立する可能性があります。
よく見られるのが、クレーム対応の流れで「店長を出せ」「謝罪しろ」などと要求し、長時間にわたって居座り続けるケースです。こうした行為が業務を妨げ、他の顧客対応に支障をきたすようであれば、警察に相談すべき深刻な事案となります。
不退去罪は、企業側や警察がクレーマーの退去を促す際の法的根拠ともなる、重要な刑法上の規定の一つです。
2.2 脅迫罪
脅迫罪(刑法222条)は、相手やその家族の生命・身体・自由・名誉・財産などに危害を加えると告げ、相手に恐怖や不安を抱かせる行為を処罰するものです。この「恐怖や不安を抱かせる」状態を、法律上は「畏怖(いふ)」といいます。なお、脅迫罪は暴力を伴わなくても成立し、言葉だけの脅しであっても十分に対象となります。
たとえば、「お前の会社、潰してやる」「社員の個人情報をネットに流すぞ」といった発言は、相手に重大な恐怖心を与えるものであり、脅迫罪として警察に対応を求めることができます。特にこれらの発言が電話や対面で繰り返される場合には、録音や録画を証拠として残すことが重要です。
2.3 強要罪
強要罪(刑法223条)は、暴行または脅迫によって、相手に義務のない行為を無理にさせる行為を処罰する犯罪です。企業の現場では、「担当者を土下座させろ」「契約を今すぐ破棄しろ」といった謝罪や業務外の対応を強く求めるケースが典型例として挙げられます。
金銭の要求がある場合には、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性がありますが、強要罪は金銭の取得を目的とせず、義務のない行為を無理やりさせようとする点が特徴です。企業側が実際に要求に応じたかどうかは関係なく、強制しようとした事実があれば、罪が成立する可能性があります。
暴行や脅迫の程度が軽微であっても、それが継続的・執拗である場合には、強要罪として立件されることもあります。不当な要求が見られた段階で、録音・録画などの証拠を残し、早めに警察や弁護士に相談することが重要です。
2.4 恐喝罪
恐喝罪(刑法249条)は、相手に対して脅しや威圧的な言動を用い、金品や財産上の利益を得ようとする行為を処罰する犯罪です。脅迫罪と似ていますが、脅迫罪が「恐怖を与えるだけ」で成立するのに対し、恐喝罪は「財産的利益の取得」を目的としている点に違いがあります。
また、強要罪との違いは、相手に「何らかの行為を無理にさせる」のが強要罪であるのに対し、恐喝罪は「相手から金品を交付させること」が目的である点です。つまり、恐喝罪は「脅して金銭を得ようとする」ことに主眼があります。
たとえば、「今ここで金を出せば示談にしてやる」「金を払わないとネットに悪評を書き込むぞ」といった発言は、相手の恐怖心を利用して金銭を要求している点で、恐喝に該当することがあります。企業を標的に、店舗運営の弱みや顧客情報への不安につけこんで金銭を要求するケースも少なくありません。
恐喝罪は、脅迫や強要と異なり、「金品の交付を迫る意図」が明確であることが重要なポイントです。そのため、被害が大きくなる前に警察へ相談し、迅速に対応することが求められます。
証拠としては、音声や映像、チャット履歴、振込記録などが有効です。弁護士と連携して証拠資料を整理・提出することで、より確実な法的対応につながります。
2.5 威力業務妨害罪
威力業務妨害罪(刑法234条)は、暴行や脅迫などの「威力」を用いて、他人の業務を妨げる犯罪です。ここでいう「威力」には、暴力だけでなく、大声での怒鳴り声、過度のクレーム電話、執拗な来店行為なども含まれます。
たとえば、来店して「責任者を出せ!」と大声で怒鳴りながらカウンターを叩き、他の客が近づけないような状況を作ると、威力業務妨害に該当することがあります。また、1日数十件にわたる無言電話や罵倒電話も、業務を妨害する「威力」にあたると判断されることがあります。
この罪は、企業側の被害を証拠で証明することができれば、比較的立件されやすい類型でもあります。
2.6 偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪(刑法233条)とは、「人を欺いたり、相手の錯誤を利用したりして業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。暴力や脅しのような“力”ではなく、「嘘や策略」を使って業務を妨げる点が特徴です。
具体的には、企業に対してまったく事実無根のクレームを繰り返すような行為が挙げられます。実際には店舗に行っていないのに、「この店は不衛生だった」「店員の態度がひどい」などと口コミサイトに虚偽の書き込みをした場合、それによって他の顧客が来店を控えるようになれば、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
特に、SNSやGoogleマップの口コミ欄といったオープンな媒体に虚偽情報を投稿されると、影響は一時的なものにとどまらず、「検索結果上の印象」や「ブランドイメージそのもの」にまで傷がつきかねません。閲覧者が「実際にそのようなトラブルが起きた店なのだ」と誤解すれば、長期的な集客や信頼にも重大な悪影響を及ぼします。
企業としては、そうした投稿に対して冷静かつ戦略的に対応することが求められます。まずは該当する書き込みのスクリーンショット、投稿日時、発信元IPといった証拠の保存が重要です。
2.7 名誉毀損罪
名誉毀損罪(刑法230条)は、公然と事実を摘示し、他人の社会的評価を低下させる行為です。事実の真偽にかかわらず、社会的評価を下げる内容であれば処罰の対象となります。
たとえば、「あの店は詐欺をしている」「この会社の従業員は前科者だ」といった投稿は、名誉毀損にあたる可能性があります。企業アカウントへのリプライやGoogleレビュー、匿名掲示板への書き込みなど、さまざまな媒体で行われることがあります。
企業が被害を受けた場合、削除請求とともに刑事告訴を検討することが重要です。
2.8 侮辱罪
侮辱罪(刑法231条)は、具体的な事実を挙げなくても、相手を公然と蔑むような発言をすることで成立する犯罪です。感情的に吐き出される悪口や中傷であっても、相手の人格を否定するものであれば処罰の対象になります。
たとえば、接客中に「お前みたいな無能に対応される筋合いはない」「使えねえ奴」といった発言を繰り返す行為が該当することがあります。SNSやブログなどで「あの店員は頭がおかしい」と書かれるケースも侮辱にあたる可能性があります。
表現の自由とのバランスもありますが、企業として毅然とした対応が求められます。
2.9 暴行罪
暴行罪(刑法208条)は、相手に対して物理的な力を加えることによって成立します。実際にけがをさせなくても、暴力的な接触があれば暴行に該当します。
たとえば、店員に詰め寄って胸ぐらをつかむ、物を店員に投げるなど、身体的接触が軽微であっても暴行として扱われる可能性があります。
現場のカメラ映像や第三者の証言が、重要な証拠となります。
2.10 器物損壊罪
器物損壊罪(刑法261条)は、他人の所有物を壊したり、使用できない状態にすることで成立する犯罪です。企業の財産や顧客の所有物に対する破壊行為も対象になります。
たとえば、怒りに任せてカウンターの備品を投げて壊す、商品棚を倒して壊す、POPや看板を破るといった行為がこれに該当します。また、破壊に至らなくても、レジの電源コードを抜いて強制的にシャットダウンさせる、機器の配線を故意に外す、設定を操作してシステムを動作不能にするなど、意図的に機械を使用不能にする行為も含まれます。
損害額の多寡にかかわらず、物の破損や機能喪失が明確であり、それが故意に行われた場合には、器物損壊罪として立件される可能性があります。
3. 警察に相談した後の流れ
悪質クレーマーによる迷惑行為に対して警察に相談したあと、どのように物事が進んでいくのか、実際の流れはあまり知られていません。ここでは、110番通報や被害届の提出後に警察がどのように対応するのか、そしてその後どのようなプロセスを経るのかをわかりやすく解説します。
3.1 相談・通報の受理
悪質クレーマーによる言動が暴力的・威迫的であり、緊急性が高い場合には、まず110番通報で警察を呼ぶことになります。警察官が現場に急行し、当事者の話を聞いてその場を収めることが最優先されます。
一方で、緊急性が低い、あるいは過去の被害について相談する場合は、所轄警察署の生活安全課等に出向き、状況を伝えます。警察は以下のような点を確認します。
- 被害の具体的内容(暴言・脅迫・業務妨害など)
- 被害が継続的かつ悪質かどうか
- 証拠(録音・録画・通話履歴・メモなど)があるか
- 相手の特定が可能か
この段階では、必ずしもすぐに捜査や逮捕につながるわけではありません。しかし、警察への相談が「記録として残ること」が、今後の対応で大きな意味を持ちます。
3.2 被害届・告訴状の受理
犯罪となる可能性があると判断した場合、警察に相談しながら被害届や告訴状の提出を検討しましょう。
被害届
- 事件性を前提に、被害を申告する手続きです。
- 捜査の開始を促す役割があります。
告訴状
- 被害者の意思で加害者の処罰を求める手続きです。
- 侮辱罪・名誉毀損罪など一部の罪では「告訴」が必要条件になります。
なお、被害届がすぐに受理されない場合もあります。特に被害の立証が難しかったり、犯罪に該当するか判断が微妙な場合、警察側からは「記録として残すが、受理は保留」と言われることもあります。それでも、被害内容と証拠をできるだけ整理して提出することで、実際に受理される確率が高まります。
3.3 捜査と警告対応
被害届が受理されると、警察は相手方への事情聴取を含めた捜査に着手します。ただし、カスハラ案件では、加害者が「ただのクレーム」「誤解だ」と主張することが多いため、証拠の精度と被害者側の説明力が極めて重要です。
捜査段階で、次の対応がとられることがあります。
- 加害者からの事情聴取
- 現場や被害状況の確認
- 店舗・会社への追加ヒアリング
この段階で警察が「刑法違反が濃厚で身柄拘束が必要」と判断した場合、加害者の身柄を拘束するための準備に進むこともあります。しかし、多くの場合、初動では警告や注意にとどまり、そこから再発防止や企業側での対応が促されます。
3.4 検察への送致とその後の流れ
警察の捜査により、犯罪が成立するだけの証拠と判断がそろった場合は、事件は検察に送致されます。この段階では、企業側の協力も引き続き重要になります。
ただし、送致されたからといって必ず起訴されて正式な裁判となるわけではありません。検察官は以下の観点などから起訴・不起訴の判断を行います。
- 犯罪の内容、悪質性、証拠の強さ
- 被害者の被害感情、示談の有無
- 加害者の反省、前科の有無
実際のところ、起訴されるまでには相当な期間を要することも多く、判決が出るまでにはさらに時間がかかります。
3.5 民事手続や再発防止策と並行する意識が必要
「警察に通報したから、もう安心」というわけではありません。むしろ、警察に動いてもらった後のほうが、企業として本格的な対応が求められる段階といえます。
- クレーム対応マニュアルの見直し
- 従業員への教育・研修
- 弁護士と連携して損害賠償請求など民事対応を検討
- 再発時の通報ルールの整備
これらを社内で並行して進めていくことで、組織として悪質クレーマーに対して継続的な対応力を確保できます。

4. 警察への相談のポイント
警察に悪質クレーマーの被害を相談する際、どのように話をすれば動いてもらえるのか不安に感じる方も多いと思います。
実際、警察が動くかどうかは、相談時の情報の整理状況や証拠の有無によって左右されることが少なくありません。
ここでは、警察への相談を効果的なものにするための3つのポイントを解説します。
4.1 事実経緯をまとめて相談する
警察への相談でまず重要なのは、「何が、いつ、どこで、誰に対して、どのように行われたか」という事実関係を、時系列で整理して伝えることです。
特に重要な情報としては、次のような項目があります。
- 発生日時と場所(できるだけ具体的に)
- 被害の内容(どのような言動・行動か)
- 加害者の氏名・特徴(わかる範囲でOK)
- 被害の影響(営業妨害・精神的苦痛など)
たとえば、「○月○日○時ごろ、○○支店のカウンターに来店した50代男性が、30分以上大声で怒鳴り続け、対応した女性職員が泣き出し、接客業務が停止した」という具合に、客観的かつ具体的にまとめることが大切です。
相談前には、可能であれば時系列表やメモ書き、概要資料を用意しておくと、警察官の理解がスムーズになります。
4.2 証拠を整理して相談する
被害の深刻さを裏付けるためには、証拠の存在が欠かせません。警察も「証拠がない状態では対応が難しい」と判断することがあるため、記録に残るものをどれだけ提示できるかがポイントになります。
たとえば、次のような証拠が有効です。
- 音声・映像の録音・録画(防犯カメラ、スマートフォンなど)
- 通話履歴・メールやSNSのメッセージ
- 手書きのメモや日報、ヒヤリハット報告
- 被害者や同席者の証言メモ
- 虚偽の口コミ投稿のスクリーンショット
- 損壊された物の写真や修理費の見積書
証拠が揃っていないときでも、どこに何が残っている可能性があるのかを警察に伝えることで、「後日提出」で対応してもらえる場合もあります。
また、証拠が改ざんされる可能性がある投稿(SNS、Googleレビューなど)は、即時にスクリーンショットを取り、投稿日時がわかる状態で保存しておくのが基本です。
4.3 弁護士の意見をもらってから相談する
悪質クレーマーの言動が、どの犯罪に該当するのかを判断するのは、通常は容易ではありません。また、「犯罪に該当しにくい」と警察が判断すると警察の動きが悪くなってしまうため、弁護士の意見や助言を踏まえて相談することが、結果的にスムーズな対応につながります。
また、弁護士が関与することで次のようなメリットがあります。
- 相談の前に刑法上の構成要件に該当するかの見通しを立てられる
- 警察に提出する書類の作成補助や添削を受けられる
- 警察が動かない場合に、民事訴訟など別の手段を検討できる
- 告訴状を作成してもらえる
さらに、弁護士が同席して警察に相談に行くことで、相手方への心理的なけん制効果にもつながります。法的根拠をもって相談することにより、警察側も「この企業は本気で対応しようとしている」と認識しやすくなるのです。
5. まとめ:警察への相談も選択肢の1つ
悪質クレーマーの対応に追われることは、企業にとって精神的にも経済的にも大きな負担になります。
その言動が常識の範囲を超えて、従業員を脅かし、業務を妨げるようになったとき、それは「単なるクレーム対応」ではなく、刑法上の犯罪行為に近づいている可能性があります。
悪質クレーマーの行為は内容によって、脅迫罪・強要罪・業務妨害罪・名誉毀損罪など、さまざまな罪に該当し得ます。警察に相談することは、決して過剰な対応ではありません。
実際に警察が動いてくれるかどうかは、被害の内容・証拠の有無・相談時の説明などによって変わります。だからこそ、事実を正確にまとめ、証拠を整理し、必要に応じて弁護士のサポートを受けることで、企業として「適切な手続き」によって自社と従業員を守ることが可能になります。
警察への相談は、法的対応の「最後の手段」ではなく、初期段階から選択肢として検討すべき有力な手段の一つです。
従業員を守り、組織を守るために、「泣き寝入り」ではなく「しかるべき対応」を今こそ考えておきましょう。