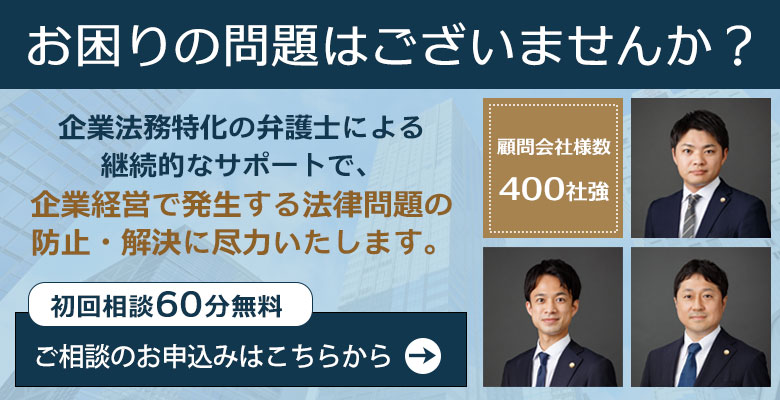従業員による重大な規律違反があった場合、「懲戒解雇」に踏み切るべきかどうかは、企業にとって極めて悩ましい問題です。
たとえ悪質な行為があったとしても、懲戒解雇には厳格な法的要件や適正な手続きが求められ、それらを欠くと「無効」とされてしまうおそれがあります。実際に、復職命令や給与の遡及支払いを命じられ、多額の負担を負うケースも少なくありません。
本記事では、企業が懲戒解雇を検討する際に押さえておくべき要件や手続き、過去の裁判例をもとにした有効・無効判断のポイント、実務上のリスク回避策まで、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
目次
1. 懲戒解雇とは
懲戒解雇とは、従業員が企業の秩序や規律を著しく乱す重大な違反行為を行った場合に、企業が「制裁」として科すことのできる最も重い解雇処分のことです。一般的には、職場での金銭の横領や着服、機密情報の漏えい、長期間の無断欠勤や暴力行為など、重大な違反行為が対象となります。
懲戒解雇処分を受けた従業員には、以下のような重大な不利益が生じることがあります。
- 退職金が不支給または大幅に減額される
- 解雇予告手当が原則として支払われない
- 雇用保険(失業手当)の受給が一定期間制限される
- 再就職活動において経歴上の不利が生じる
このように、懲戒解雇は従業員に極めて深刻な影響を及ぼすため、企業側にも厳格な対応が求められます。

2. 懲戒解雇の要件
懲戒解雇は、従業員にとって非常に重い不利益をもたらす処分です。そのため、会社がこれを有効に行うためには、いくつかの厳格な条件を満たしている必要があります。
具体的には、次の4つの要件がすべて満たされていなければ、懲戒解雇が無効と判断されるおそれがあります。
2.1 就業規則上の根拠があること
懲戒解雇を行うには、あらかじめ就業規則に懲戒解雇の事由が明記されている必要があります。たとえば、「職務命令に違反したとき」「会社の名誉を著しく毀損したとき」「正当な理由なく長期間欠勤したとき」など、具体的にどのような行為が対象となるかが規定されていなければなりません。
また、処分の種類や手続きについても、就業規則で定めておく必要があります。就業規則に定めがない処分は、たとえ内容が正当であっても無効と判断される可能性があります。
2.2 客観的合理性があること
懲戒解雇が有効と認められるには、その解雇に「客観的に合理的な理由」が存在している必要があります。つまり、企業側が、従業員の行為が就業規則に明記された懲戒事由に該当することを具体的な証拠に基づいて証明しなければなりません。
たとえば、「備品の横領があった」「機密情報を漏えいした」といった懲戒解雇の理由となる行為については、その事実が実際に起きたことを客観的に示す証拠が必要です。具体的には、防犯カメラの映像やメール履歴、本人の供述や周囲の証言など、明確な根拠によって事実関係を裏付けなければなりません。
企業の主観的な疑念や、根拠のないうわさレベルの情報だけでは、懲戒解雇の客観的合理性は認められません。
2.3 社会的相当性があること
実際に違反行為があったとしても、それに対して懲戒解雇という処分が重すぎないか、社会的に見て妥当な対応かどうかが問われます。
たとえば、従業員が初めて規律を乱した場合や、事情に一定の合理性が認められる場合には、いきなり懲戒解雇とするのは過剰な処分と評価される可能性があります。
一方で、金銭の横領、業務用データの持ち出し、職場内での暴力行為など、悪質性が高く企業秩序を著しく損なう行為であれば、懲戒解雇の相当性が認められやすくなります。
この判断は、行為の内容や影響、過去の指導歴、本人の反省状況なども踏まえて、社会通念に照らして行うことが重要です。
2.4 適正な手続きであること
どれだけ理由が正当でも、手続きに不備があれば、懲戒解雇は無効とされるおそれがあります。特に重視されるのが「弁明の機会を与えたかどうか」です。
本人に対して、事実関係を説明し、処分の内容について自らの意見を述べる機会を与える必要があります。一方的な通知では足りず、本人が十分に意見を述べられる形式でなければなりません。
また、就業規則に懲戒手続きの流れや決裁方法が定められている場合には、それに従って、調査・審議・通知などの段階を適正に踏むことが求められます。
手続きの正当性を担保するためには、証拠の保全、記録の作成、通知文書の送付なども丁寧に行うべきです。
3. 懲戒解雇の流れ
懲戒解雇を行うには、適切な手順を踏むことが欠かせません。ここでは、懲戒解雇を実施する際の一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。
① 事実関係の調査
はじめに、懲戒解雇の根拠となる事実が本当に存在するかを確認します。
たとえば、勤務態度に問題がある場合は、タイムカードや業務記録、注意指導のメモなどが証拠となります。社内の備品の持ち出しが疑われる場合には、備品管理に関する帳簿、防犯カメラ映像やメールログの履歴などの確認が必要です。
本人立会いの下で従業員の私物やロッカーなどを調べる場合もありますが、プライバシー侵害とならないよう注意が必要です。就業規則その他の明示的な根拠がない場合や調査を必要とする合理的な理由がない場合、手段が過剰な場合などには、違法とされるおそれもあります。
② 懲戒解雇の要件を満たしているかの確認
事実関係の確認ができたら、その事実に基づく労働者の行為が、懲戒解雇の要件を満たしているかどうかを検討します。
具体的には、就業規則に懲戒解雇に関する規定が設けられているかを確認したうえで、問題となっている従業員の行為が、その規定された懲戒事由に該当するかどうかを判断します。
③ 弁明の機会を与える
就業規則上、懲戒解雇を実施する前に本人に対して「弁明の機会」を設ける旨定められている場合は、必ず弁明の機会を付与する必要があります。
就業規則上にそのような定めがない場合であっても、懲戒解雇は重大な処分であり、弁明の機会を与えていないことが不利に判断される可能性が高いため、いずれにせよ、弁明の機会を付与する必要があります。
「弁明の機会の付与」とは、処分の内容や理由について本人の言い分を聞くためのもので、形式的に済ませればよいというものではありません。本人が出席を拒否した場合や意見を述べない場合でも、「機会を設けた」という事実をきちんと記録しておくことが重要です。
④ 懲戒解雇通知書を作成する
懲戒解雇を決定したら、「懲戒解雇通知書」を作成します。通知書の記載内容について法律上の定めはありませんが、後々トラブルにならないよう、最低限以下の内容を盛り込むようにしましょう。
解雇する従業員の氏名
解雇の対象者が特定できるように、氏名は正確に記載します。
会社名と代表者名
労働契約の当事者を明確にするため、会社名と代表者名を記載します。
通知書の作成日
会社がいつ懲戒解雇を通知したかを証明するため、必ず作成日を記載します。
解雇の効力発生日(解雇日)
雇用契約が終了する具体的な日付を明記します。日付が曖昧だと争いになる可能性があります。
解雇の意思表示
「貴殿を〇年〇月〇日付で懲戒解雇とします」のように、明確に記載します。
なお、解雇の理由も基本的に記載すべきですが、どの程度具体的に記載すべきなのかはケースごとに判断が異なりますし、懲戒解雇の理由を後日付け足すことも基本的にできません。
また、懲戒解雇と普通解雇では懲戒解雇の方が法律上のハードルが高いため、懲戒解雇が無効とされた場合に備えて予備的に普通解雇の通知もするか否かを検討する必要があります。
以上のとおり、懲戒解雇の通知には慎重な判断が必要であるため、弁護士に事前に相談して決定することを強くおすすめします。
⑤ 懲戒解雇通知書の交付
懲戒解雇通知書は本人に直接手渡すことが望ましいとされています。受け渡し時には、コピーを取って保管し、可能であれば本人から受領の署名をもらっておくと安心です。
ただし、本人が出社しない、あるいは受け取りを拒否する場合は、内容証明郵便など証拠が残る方法で送付しましょう。
4. 懲戒解雇が有効な場合と無効な場合の具体例
ここでは、実際の裁判例を基に、懲戒解雇が有効と判断されたケースと無効とされたケースの違いを具体的に示します。
4.1 懲戒解雇が有効とされた具体例
ケース1:売上金の長期的着服
乳製品・乳酸菌飲料の販売を手がける会社に勤務していた従業員が、自動販売機の売上金を1年以上にわたって繰り返し着服していた事案です。着服総額は100万円を超えており、被害弁償も行われていませんでした。
行為の継続性や悪質性、金額の多さに照らし、懲戒解雇には十分な合理性があり、社会通念上も相当であるとして、懲戒解雇は有効となりました。
ケース2:配転命令無視と無断欠勤の継続
貨物自動車運送事業などを営む会社に勤めていた従業員が、協力会社の乗務員に対する暴言等の言動を繰り返したため、配転命令を受けました。しかし、配転先での勤務を拒否し、正当な理由なく欠勤を継続したため、会社は懲戒解雇を行いました。
配転命令には業務上の合理性があり、従業員の欠勤は就業規則に違反する無断欠勤に当たるとして、懲戒解雇は有効となりました。
ケース3:金融機関における集金着服
定期預金の集中集金業務に従事していた金融機関の従業員が、顧客から預かった掛金1万円を私的に流用した事案です。会社はこの行為を重大な規律違反ととらえ、懲戒解雇処分としました。
金融機関においては顧客との信頼関係が業務の根幹をなすものであり、その信用を裏切る行為は重大な背信行為にあたるとして、懲戒解雇は有効となりました。
4.2 懲戒解雇が無効とされた具体例
ケース1:セクハラ・パワハラ・不倫などの証拠不十分
パチンコ店を経営する企業に勤めていた従業員が、部下や店舗スタッフに対するセクハラ・パワハラ行為、不倫などを理由に懲戒解雇された事案です。
これらの主張された事実の多くは証拠が不十分で認定できず、また従業員に対して反論の機会を実質的に与えず処分に至ったことから、懲戒解雇は合理性と相当性を欠くとして無効となりました。
ケース2:就業規則の不存在
資産運用コンサルティングを主業務とする合同会社において、就業規則が存在しない状態で懲戒解雇が行われた事案です。
懲戒処分には明文の根拠が必要であり、就業規則が存在しない以上、懲戒権行使の根拠を欠くとして、懲戒解雇は無効となりました。
ケース3:着服の意図が認定できなかった例
バス会社に勤務していた運転手2名が、運賃の一部を着服したとして懲戒解雇された事案です。
運転手1名につき、横領の故意を裏付ける証拠が不十分であると判断し、着服の事実そのものが認定できないことから、懲戒解雇は無効となりました。残る1名は横領の意図が認められるとして懲戒解雇は有効となりました。
5. 懲戒解雇が無効となった場合のリスク
懲戒解雇が無効と判断されると、企業には重大なリスクが生じます。懲戒解雇が無効になることにより、企業と従業員の間に雇用契約が「継続している」ものとみなされるため、次のような対応を迫られることになります。
5.1 従業員を復職させなければいけない
裁判や労働審判で懲戒解雇が無効と判断されると、法的にはその解雇は「最初からなかった」ものと扱われます。つまり、企業と従業員との間の雇用関係は解消されておらず、現在も継続しているということになります。
その結果、会社は当該従業員を職場に復帰させなければなりません。実際には、復職に際して職場環境や業務の調整が必要になることが多く、トラブルや再発防止措置を講じなければならない場合もあります。
5.2 給与をさかのぼって支払わなければいけない
懲戒解雇が無効とされると、企業は「解雇から現在までの間に、本来支払うべきであった給与」について、遡って支払いを命じられることになります。この支払義務は「バックペイ(back pay)」と呼ばれ、解雇後の未払期間が長期化するほど、企業側の負担は大きくなります。
たとえば、従業員が解雇を不服として裁判を提起し、判決までに1年半を要した場合、その期間中の賃金がすべて支払い対象になる可能性があります。加えて、遅延損害金も発生するため、総額が非常に高額になるケースも少なくありません。
6. 懲戒解雇のトラブルを避けるためのポイント
懲戒解雇は、企業が従業員に対して課すことのできる最も重い処分です。その分、法的なハードルも高く、判断を誤ると無効とされる可能性があります。実際に裁判で無効と判断されると、従業員の復職や賃金の支払いといった大きな負担を企業側が負うことになります。
ここでは、懲戒解雇のトラブルを避けるために企業が押さえておくべき実務上のポイントを4つご紹介します。
6.1 安易に懲戒解雇せず事前に十分に検討する
従業員に問題行動があったからといって、すぐに懲戒解雇に踏み切るのはリスクが高いと言えるでしょう。懲戒解雇はあくまで「企業秩序に重大な悪影響を与える行為に対する、最後の処分手段」とされており、他に選択肢がある場合は、まずそちらを検討するのが基本です。
初回の違反行為や改善の余地があるケースでは、口頭注意や始末書の提出、配置転換、より軽い懲戒処分など、懲戒解雇より軽い処分で対応できることも少なくありません。感情論にとらわれることなく、従業員一人ひとりの事情を丁寧に考慮し、客観的に最も適切な処分を選択することが重要です。
6.2 証拠を確保する
懲戒解雇が有効とされるためには、企業側が処分の根拠となる行為を具体的・客観的に立証する必要があります。つまり、「何が起きたのか」「誰が関与したのか」「どれほどの影響があったのか」などを示す記録や証拠を整理しておくことが不可欠です。
たとえば、横領であれば金銭の流れを示す帳簿や入出金記録、業務上の背任であれば社内資料の持ち出し記録や関係者の証言、パワハラであれば録音やメールのやり取りなどが証拠になり得ます。
6.3 就業規則の手続きを確認する
懲戒解雇を行うためには、事前に就業規則を整備し、そこに懲戒処分の種類や処分対象となる具体的な行為、手続きの流れなどを明記しておく必要があります。また、従業員に対してこれらの内容をきちんと周知することも求められます。就業規則の定めが曖昧だったり、従業員への周知が不十分だったりすると、処分自体の有効性が問題となる可能性があります。
さらに、就業規則で決められた手続きを守らずに懲戒解雇を行うことも有効性に重大な影響を与えます。たとえば、「懲戒委員会を開催する」などの手順が規定されている場合には、それらの手続きを省略したり簡略化したりせず、一つひとつ丁寧に実施することが重要です。こうした手続きを形式的なものと軽視せず、適切に実施することで、懲戒解雇の法的な有効性が確保されます。
6.4 弁明の機会を与える
懲戒処分を行う際には、対象となる従業員に対して、事前に事実の確認や本人の言い分を聞く「弁明の機会」を与えることが必要です。これは、企業としての公平性を担保する意味でも、法的に極めて重要な手続きとされています。
弁明の場を設けずに懲戒処分を行った場合や、事実上結論が出たあとに形だけ弁明を受けるといった対応では、「適正な手続が踏まれていない」と判断され、懲戒解雇自体が無効とされる可能性があります。弁明の機会を付与したこと、弁明内容(弁明の機会の付与に応じなかったことを含みます。)、処分理由の明示といった一連の対応を、書面や議事録として残しておくことも重要です。

7. 懲戒解雇についてのよくあるご質問
懲戒解雇は企業にとって重大な処分である一方、その手続きや効果について正確に理解するのは簡単ではありません。ここでは、実務でよく寄せられる疑問や、誤解されやすいポイントについて、Q&A形式でわかりやすく整理します。
7.1 懲戒解雇と普通解雇の違いは何ですか?
懲戒解雇は「企業秩序に対する重大な違反行為に対する制裁」であり、普通解雇は「業務の継続が困難と判断された場合の契約終了手段」です。このように、両者は処分の性質も手続の要件も異なります。
懲戒解雇は、会社が従業員に対して行う最も重い懲戒処分にあたります。そのため、就業規則に懲戒解雇の規定があることが前提であり、処分理由もその規定に明確に該当している必要があります。さらに、弁明の機会を与えることや、社内の懲戒手続きを適正に進めることも求められます。
一方で、普通解雇は、勤務成績の不良や健康上の理由など、従業員側に何らかの事情がある場合に、企業が労働契約を終了させる手段です。懲戒のような制裁目的ではなく、契約関係の終了という意味合いが強いため、就業規則への具体的な明記がなくても可能な場合があります。
このように、両者は性質も要件も大きく異なるため、どちらの解雇に該当するのかを事前にしっかりと判断し、適切な手続きを踏むことが重要です。
7.2 懲戒解雇と諭旨解雇の違いは何ですか?
懲戒解雇と諭旨解雇の大きな違いは、「処分の厳しさ」と「退職の形式」にあります。懲戒解雇は処分の中でも最も重く、強制的に労働契約を終了させるのに対し、諭旨解雇は企業側が退職届の提出を促し、従業員が応じれば退職という形で契約を終了させる「勧告型」の処分です。
諭旨解雇は形式としては自己都合退職に近く見えますが、実際には懲戒処分の一種であり、内容的には「懲戒解雇寸前」の状態と言えます。従業員が退職届を提出しなければ、懲戒解雇に移行することを予定しているケースがほとんどです。
また、両者の違いが最も顕著に現れるのが退職金の扱いです。企業によって異なるものの、諭旨解雇であれば退職金を自己都合退職前提の計算または一定割合支給する規定がみられる一方で、懲戒解雇の場合は不支給または大幅減額とする規定が見られます。
つまり、諭旨解雇は企業秩序への重大な違反行為があるものの、一定の猶予を与える意味合いで退職という形を取らせる処分であり、懲戒解雇ほどの強い経歴上のダメージや不利益を与えずに処理する手段として位置づけられています。
7.3 懲戒解雇では解雇予告手当は支払わなくてもよいですか?
懲戒解雇であっても、原則として解雇予告手当の支払いは必要です。労働基準法では、「労働者を解雇する場合は、30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない」と定められており、この規定は懲戒解雇にも適用されます。
ただし例外として、「労働者の責に帰すべき事由」があると労働基準監督署に認定された場合には、解雇予告や手当の支払いは不要になります。この「責に帰すべき事由」とは、単に就業規則上懲戒解雇に該当するというだけでは足りず、労働者を解雇予告制度で保護する必要がないと言えるほど重大又は悪質な義務違反や背信的行為があったと評価される場合を指します。職場での横領や暴行など、刑法上の犯罪に該当し、企業の信頼や秩序を著しく損なうようなケースが典型です。
こうした場合には、労働基準監督署に「解雇予告除外認定申請書」を提出し、適切な手続きを経ることで、予告手当を支払わずに即時解雇が可能となります。この手続きを怠ったまま手当を支払わずに解雇してしまうと、解雇が無効となり得るリスクが発生し、また労働基準法違反として刑事罰の対象にもなり得ます。したがって、懲戒解雇を即時に行う際には、事前に証拠や経緯を整理したうえで、慎重に進めることが重要です。
7.4 懲戒解雇では退職金は支払わなくてもよいですか?
懲戒解雇の場合でも、必ずしも退職金を不支給にできるわけではありません。懲戒解雇を理由に退職金を不支給・減額するには、次の2点を満たしていることが必要です。
1つ目は、就業規則や退職金規程に、懲戒解雇の場合の退職金の不支給または減額について明確な定めがあることです。企業がこのような措置を講じる際の根拠として必要になります。
2つ目は、懲戒解雇の理由となる行為が、長年の勤務の功労を帳消しにするほどの著しい背信行為に該当することです。たとえば、会社資産の横領や顧客情報の不正持ち出しなどが該当します。単に就業規則違反をしたという程度では、不支給や減額は無効とされる可能性が高くなります。
懲戒解雇だからといって当然に退職金がゼロになるわけではなく、不支給や減額をするには十分な根拠と慎重な対応が必要です。判断を誤れば、訴訟で退職金の全額支給や遅延損害金の支払いを命じられるリスクもあります。退職金の取扱いを就業規則で明記しておくこと、懲戒理由と処分の妥当性をしっかり説明できるよう準備しておくことが重要ですG
7.5 懲戒解雇したことを社内外に公表してよいですか?
懲戒解雇を行った場合、その事実を社内や社外に公表してよいかどうかは、非常に慎重な判断が求められます。公表の方法によっては、名誉毀損にあたるとして損害賠償請求を受ける可能性があるためです。
まず社内への公表については、「社内の規律意識を高める」ことを目的として行うのであれば、一定の範囲で許容される可能性があります。ただし、この場合でも次の点に注意する必要があります。
- 就業規則に公表に関する定めがあること
- 処分の対象となった従業員の氏名を明示しない、事案を抽象化するなどして特定を避けること
- 公表内容は事実に基づいたものに限ること
- 公表態様(表現、公表媒体、期間)などは目的との関係で必要最小限度とすること
- 被害者の二次被害発生のおそれに注意すること
一方で、社外への公表については、さらに高いリスクがあります。懲戒処分は社内規律の問題であるため、通常は社外に発信する必要はありません。社外のホームページなどで公表した結果、名誉毀損やプライバシー侵害と判断されたケースも多く、原則として避けるべきです。
ただし、処分理由が取引先や社会に直接かかわる場合(例:顧客情報の漏洩など)、信頼回復のために必要最低限の事実を、氏名等を伏せたうえで公表することは一定程度許容される可能性もあります。もっとも、社内公表の注意事項にも同様に注意が必要です。したがって、この場合でも、事前に弁護士と相談したうえで判断することが重要です。
懲戒解雇の公表は「誰に・何を・どのように」伝えるかによって、違法となるリスクの有無が大きく変わります。社内外に向けた発信は安易に行わず、就業規則の整備とともに、専門家の助言を踏まえた慎重な対応が求められます。
8. まとめ:懲戒解雇で悩んだら弁護士に相談
懲戒解雇は、企業にとって重大な判断である一方、適切な手続きや根拠が欠けていれば無効とされ、大きな損害につながるリスクもあります。復職や未払い賃金の支払い義務が発生するケースもあり、慎重な対応が求められます。
よつば総合法律事務所では、懲戒解雇を含む労務問題について、企業の実情に応じた実務的かつ迅速なサポートを提供しています。トラブルを未然に防ぐためにも、懲戒解雇でお悩みの際は、お気軽に無料相談をご利用ください。