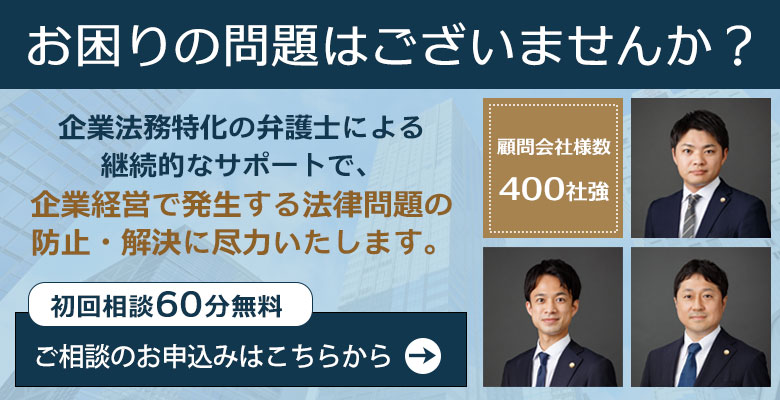会社に突然「労働組合加入通知書」や「労働組合結成通知書」が届いたとき、経営者や人事担当者は大きな不安や戸惑いを感じるものです。これまで労働組合と関わりがなかった企業にとっては、「なぜ通知が届いたのか」「どう対応すればよいのか」と頭を抱えるのも無理はありません。
本記事では、労働組合から通知書が届いた際に経営者・人事担当者がまず押さえておくべき基本的な考え方と、初期対応のポイントを弁護士の視点から解説します。
団体交渉に備えるための実務的な注意点や、してはいけない対応もあわせて紹介しますので、予期せぬ労働組合対応に直面した際の指針としてお役立てください。
目次
1. 労働組合加入通知書とは
「労働組合加入通知書」とは、従業員や元従業員が労働組合に加入した事実を会社に知らせるための書面です。
経営者や人事担当者の中には「社内に労働組合は存在しないのでは」と考える人も少なくありません。近年の労使紛争を担うのは、従来の社内労働組合ではなく、合同労組(ユニオン)と呼ばれる社外の労働組合です。合同労組は、社員1人からでも加入できます。
加入通知書の内容はシンプルで、「○月○日に○○労働組合に加入した」という事実と、加入した従業員の氏名が記載されることが多いです。通知は会社宛に正式な書面で届き、労働組合の支部や執行委員長の名義で発行されるのが一般的です。
加入通知が届いたということは、労働者がすでに合同労組へ相談し、問題解決のために動き始めている段階です。つまり、会社は初動対応を誤ると大きなリスクを抱えることになります。感情的な対応は避け、速やかに法的な観点を踏まえた準備を進める必要があります。

2. 労働組合結成通知書とは
「労働組合結成通知書」とは、会社内に労働組合が新たに設立された事実を知らせる書面です。
合同労組の支援を受けて「○○ユニオン△△株式会社支部」といった形で支部が立ち上がることが多く、通知書はその成立を正式に伝えるものです。結成にあたっては、合同労組に所属する専従のスタッフが従業員に助言を行い、団体交渉に備えた準備が整えられます。
加入通知書は従業員が1人でも加入すれば送られますが、結成通知書は複数の従業員が既に参加している可能性が高いという特徴があります。さらに、結成通知が届いた時点で、労働組合側は団体交渉に向けて具体的な行動を計画していることが多く、会社にはより迅速かつ慎重な準備が求められます。
また、労働組合の結成を行ったということは、組合員をさらに増やして組織拡大を図る意欲が示されています。実際に、労働組合は結成後も社内で従業員に加入を呼びかけ、継続的に活動を続けることがあります。つまり、結成通知が届いた場合は一過性のものではなく、継続的な労使関係の変化が始まったサインといえます。
経営者・人事担当者は、労働組合結成通知が届いた場合には、事態の重大性を認識し、より慎重に、そして迅速に専門家へ相談することをおすすめします。
3. 会社が取るべき初期対応
労働組合から通知書を受け取ったとき、会社がどのように最初の一歩を踏み出すかで、その後の交渉や紛争の行方が大きく変わります。慌てず冷静に、正しい手順で対応を始めることが重要です。
3.1 通知書を受領する
突然、労働組合が会社に来て「労働組合加入通知書」や「労働組合結成通知書」を手渡してくることがあります。経営者や人事担当者にとっては予想外の出来事であり、驚きや動揺が先に立つかもしれません。
しかし、その瞬間から労働組合との関係は始まっています。書面受領の場面こそ、会社の対応姿勢が問われる重要な局面です。
労働組合に加入したり、結成したりすることは、憲法で保障された労働者の団結権の行使です。これを妨げることはできず、無視や受領拒否などの不誠実な行為は不当労働行為(労働組合法で禁止されている労働者の団結権などを侵害する会社側の行為)と評価され、違法とされるおそれがあります。
合同労組(ユニオン)は、会社が誤った対応をしないかを注意深く観察しています。書面の受領を拒むなど不誠実ととられる対応をしてしまうと、その後の交渉で会社に不利に働く可能性があります。なお、書面を受け取ることは、要求をそのまま受け入れることを意味しません。受領はあくまで形式的な対応であり、今後の交渉で要求に応じるかどうかは別の問題です。
また、労働組合が会社内で騒ぎ立てると、周囲の従業員の目に触れ、加入希望者が増えるきっかけになりかねません。組合員が増えれば団体交渉は複雑化し、紛争が長期化するリスクも高まります。
会社側はできる限り冷静に対応し、冷静に書面を受領することが大切です。もし会社が落ち着いて対応しているにもかかわらず、組合側の態度が著しく乱暴な場合は、警察への連絡を検討することも選択肢のひとつです。
3.2 通知書の内容を冷静に確認する
通知書が届いたら、まずは内容を正しく理解することが重要です。感情的に反応するのではなく、事実を整理し、どのような組合がどんな要求をしているのかを冷静に把握する必要があります。
通知書を適切に把握するチェックポイントは次のとおりです。
3.2.1 ① 通知書の名義人となっている労働組合や上部団体がどこか
通知書を出した労働組合名と、その上部団体の有無を確認します。社名・組合名でウェブサイトやSNSを検索し、これまでの発信内容、活動の規模、交渉のスタイルを把握しましょう。
話し合いを重視して妥協点を探る組合もあれば、ストライキなどの争議行為を辞さない組合、SNSやメディアで積極的に発信する組合もあります。傾向を事前に把握し、交渉の進め方や注意点を見通すための準備を行いましょう。
3.2.2 ② 労働組合に加入したのは誰か
加入者の氏名を確認し、在籍中か退職済みかを区別します。
退職者のみが加入している場合は、過去の労働問題の解決に焦点を絞れます。
他方、在籍中の従業員が加入している場合は、他の従業員とのバランスや今後の労働条件への波及を検討する必要があります。加入者が職場で勧誘を行い、組合員が増えるおそれもあるため、より慎重な対応が求められます。
3.2.3 ③ 組合に「加入」したのか、「結成」したのか
外部の労働組合に個人で加入する場合(以下「加入型」といいます。)、外部組合に加入したうえで社内に支部を立ち上げるパターン(以下「結成型」といいます。)があります。
結成型は、組合員をさらに増やして組織拡大を図る意欲の表れです。消滅しにくく、活動は長期間に及ぶことも多いです。結成後は社内で勧誘が続くのが一般的で、紛争は長期化しやすくなります。
判別は通知書で可能です。加入型は「労働組合加入通知書」などの表題で、名義は「〇〇労働組合」となっているのが通常です。結成型は「労働組合結成通知書」などの表題で、名義は「〇〇労働組合××支部」(××は会社名)となっているのが通常です。
3.2.4 ④ 要求書で求められている事項
加入・結成の区別を確認したら、次に把握すべきは組合から提出される「要求書」の内容です。要求書を確認し、組合が具体的に何を求めているのかを整理しておきましょう。
個別の紛争(異動・解雇の無効、ハラスメントの申告など)が中心であれば、対象となる組合員に関する解決に絞って交渉を進めやすくなります。
一方で、賃金制度の見直しや同一労働同一賃金の是正といった全社的なテーマが含まれている場合には、部署を横断した検討が不可欠です。
その際は、人事・労務・経営の合意形成に加え、最終的な社内周知まで見据えた対応設計が必要になります。
3.3 専門家に相談する
労働組合からの通知書を受け取った段階で、すでに会社と組合との交渉は始まっています。内容を確認したうえで、できるだけ早い段階で専門家に相談することが重要です。
労働組合との対応は、会社にとって経験が少ないことが多く、初動を誤ると交渉が不利に進むだけでなく、後に不当労働行為と指摘されるリスクがあります。たとえ小さな要求に見えても、背景に大きな問題が隠れていることもあるため、経営判断だけで進めるのは危険です。
弁護士に相談すれば、通知書の文面や要求の法的意味を整理し、会社として取るべき方針を冷静に判断できます。また、団体交渉の準備や交渉の場に立ち会ってもらうことも可能であり、会社が意図せず不利な立場に追い込まれるのを防げます。
特に結成型の通知が届いた場合は、今後の活動が長期化する可能性が高いため、早めの相談が重要です。初期の対応を誤らず、法的に適切な手順で進めることで、紛争を長期化させずに解決できる可能性が高まります。
4. 団体交渉日までの注意点
ここでは、団体交渉当日を迎えるまでに会社側が確認・準備しておくべきポイントを整理します。
4.1 日時の調整
団体交渉は、組合の指定した日時に必ず応じる義務まではありません。会社の都合で対応できない場合は、早めに組合へ連絡し、候補日を複数提示しましょう。このとき、組合が指定した日からあまりに離れた日程を提示すると「団体交渉拒否」と受け取られるおそれがあるため注意が必要です。
開始時間については、組合は就業時間中の開催を求めることが多いですが、会社はこれを拒否できます。従業員は就業時間中に労務提供義務を負っているためです。勤務終了後の移動時間を考慮した設定が現実的です。
なお、やむを得ず就業時間中に行う場合には、原則としてノーワーク・ノーペイの考え方(労働者が働かなかった時間分の賃金は会社に支払い義務がないという原則)のことから賃金支払義務はありませんが、実務上は労使慣行や判例により異なる場合があるため、慎重に判断する必要があります。
また、終了時間をあらかじめ明確に決めておくことも重要です。初回の団体交渉であれば、おおむね2時間程度を目安にするとよいでしょう。
4.2 場所の調整
交渉の場所は、会社施設や組合事務所ではなく、会社の費用で外部の貸会議室を利用するのが望ましいです。会社施設で行うと他の従業員の目についたり、業務の妨げになるおそれがあります。また、組合事務所で行うと、想定外に交渉が長引くおそれがあります。
4.3 出席者や出席人数の調整
団体交渉には社長や代表取締役が必ず出席する必要はありません。人事課長や総務課長などでも問題ありませんが、労働条件などについて一定の決定権を持つ人物が参加しなければなりません。権限のない担当者だけで臨むと「不誠実団体交渉」とされ、不当労働行為に該当するリスクがあります。
組合へ回答する際は、協議に応じる姿勢を示すため、開催日時や場所の候補を提示することが一般的です。出席者については、事前に具体名まで伝える法的な義務はありませんが、交渉を円滑に進めるために、責任者が出席する旨などを伝えておくとよいでしょう。
5. してはいけない対応
労働組合から加入通知書や結成通知書、さらには団体交渉申入書を受け取ったとき、会社が感情的に反応してしまうと、かえって事態を悪化させる危険があります。労働組合活動は憲法や労働組合法で保障された正当な権利であり、誤った対応を取ると「不当労働行為」として違法とされる可能性が高まります。ここでは特に注意すべき「してはいけない対応」を整理します。
5.1 団体交渉の拒否
会社は正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。もし正当な理由なく団体交渉を拒否すれば、「団体交渉拒否」という不当労働行為にあたり、労働組合法違反となってしまいます。
団体交渉そのものを拒否するだけでなく、次のような会社側の対応も「交渉拒否」と評価されるリスクがあります。
- ① 団体交渉申入書の受領を拒否する
- ② 団体交渉の場を設けても、誠実に対応しない(使用者の誠実交渉義務違反)
- ③ 労働組合の上部団体の組合員の同席を一方的に拒否する
- ④ 書面や電話での回答のみとし、対面での交渉を行わない
- ⑤ 交渉に必要な資料を開示せず、説明を尽くさない
こうした対応はいずれも会社にとって大きな法的リスクとなります。団体交渉の場では、必ずしも労働組合の要求をすべて受け入れる必要はありませんが、誠意を持って協議に臨む姿勢が欠かせません。
5.2 組合員に対する不利益取扱い
労働組合法は、労働者が労働組合の組合員であることなどを理由として、使用者が解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁止しています。会社がこれに違反すると、法的責任を問われるだけでなく、労使関係の信頼を大きく損なうことになります。
不利益取扱いにあたるのは、労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入もしくは結成しようとしたこと、あるいは正当な組合活動を行ったことなどを理由に、解雇や降格などの不利益を与える行為です。
典型的な不利益取扱いには、次のようなものがあります。
- ① 雇用上の不利益:解雇、退職強要、雇止め、本採用拒否など
- ② 人事上の不利益:降格、配置転換、出向・転籍の命令など
- ③ 経済的な不利益:賃金や賞与の減額、退職金の不支給、昇進査定での差別など
- ④ 労働条件上の差別:特定の組合員に残業を強いる、逆に残業をさせない、仕事の割り振りで差別するなど
また、不利益取扱いかどうかは、組合活動が「正当な行為」であったか、そして会社側に「不当労働行為の意思(反組合的な動機)」があったかが総合的に判断されることになります。労働条件の改善を目的とした正当な活動は保護されますが、業務を不当に妨害するような行為は保護の対象外とされる場合があります。
さらに、会社の経営者や管理職が日頃から組合を嫌うような言動をしていると、不利益な取扱いがあった際に「組合活動が理由だったのだろう」と判断されやすくなるため、注意が必要です。
企業が不利益取扱いと指摘されないためには、解雇や人事異動に関する規定を整備し、客観的に合理的な手続を経ていることを示せるようにしておくことが重要です。また、人事評価や昇進基準を明確にし、差別的な取扱いと疑われないように配慮することも欠かせません。組合活動に関する対応は、必ず法令に基づき、慎重に進める必要があります。
5.3 支配介入
支配介入とは、会社が労働組合の自主性や独立性を損なう行為を指します。支配介入は労働組合法で不当労働行為として禁止されています。特徴的なのは、組合活動が実際に妨げられたかどうかにかかわらず、「そのような行為をしたこと自体」で違法と判断され得る点にあります。
具体的に支配介入とされる行為の例としては、次のようなものがあります。
- ① 労働組合の結成を威嚇・非難する、結成大会当日に就労を命じるなどの行為
- ② 組合員に対する解雇・配転・出向、正当な組合活動への懲戒処分
- ③ 組合幹部の買収・供応、別組合結成の援助
- ④ 団体交渉を回避するため、個別に組合員へ直接働きかける行為
- ⑤ 継続して行っていた便宜供与を一方的に打ち切ることや、合理的理由なく労働協約を更新しないこと
これらは一見すると人事上の権限の範囲に見える場合もありますが、組合活動の弱体化や自主性の喪失につながれば支配介入と判断されます。
また、組合への経費援助も原則禁止ですが、次のような場合は例外として許容されています。
- ① 労働者が賃金控除なく労使協議を行えるようにすること
- ② 福利厚生や災害救済のための基金への寄付
- ③ 最低限度の事務所供与
これらを超える経費援助は、組合の自主性を損なう危険があるため不当労働行為に該当する可能性があります。さらに、一度許容されていた援助を一方的に打ち切った場合には、その行為自体が不当労働行為と評価されることもあります。
つまり、支配介入は会社の意図や実際の結果にかかわらず問題となる可能性があるため、人事や経営判断の場面でも細心の注意が必要です。わずかでも「組合弱体化」と受け取られるおそれがある行為については、弁護士など専門家の助言を得ながら慎重に進めることが望ましいでしょう。

6. よくあるご質問
労働組合への対応では、会社として判断に迷う場面が多くあります。ここでは、特によく寄せられる質問を取り上げ、基本的な考え方と注意点を解説します。
6.1 労働組合を名乗る人が突然会社に来ました。どうすればよいですか?
突然「労働組合」を名乗る人物が会社を訪れることは珍しくありません。まずは慌てず、名刺や通知書などから相手が実在する労働組合かを確認しましょう。対応する際は、その場で安易に回答や約束をするのは避け、後日文書での回答や担当部署から正式に対応する旨を伝えることが望ましいです。
また、訪問の内容が団体交渉の申入れである場合、正当な理由なく拒否すると不当労働行為にあたるおそれがあります。したがって、団体交渉申入書を受け取った際は、必ず受領の事実を記録し、社内で共有したうえで弁護士などの専門家に相談して対応方針を決めることが重要です。
6.2 労働組合に入った従業員を解雇してもよいですか?
労働組合に加入したことを理由に従業員を解雇することは、明確に禁止されています。これは「不利益取扱い」として不当労働行為に該当し、違法行為となります。
もし解雇を検討する場合でも、その理由が組合加入や組合活動とは全く関係のない、客観的に合理的かつ社会通念上相当な事由に基づいていることが必要です。たとえば、重大な服務規律違反や能力不足などです。
ただし、組合加入などと全く関係のない理由による解雇だとしても、組合加入直後で解雇がなされれば、不当労働行為であると主張されるリスクは高いです。会社の判断が不当労働行為と評価されれば、労働委員会による救済命令や裁判リスクが生じるため、慎重な対応が求められます。
解雇の是非について迷うときは、弁護士に相談し、労務リスクを最小限に抑えることが大切です。
7. まとめ:労働組合対応は弁護士に相談
労働組合からの通知や団体交渉の申入れに対して、会社が独自に判断して対応すると、意図せず不当労働行為にあたる危険があります。団体交渉の拒否や不誠実な対応と見なされれば、労働委員会から救済命令を受けたり、社会的信用を損なう結果につながりかねません。
一方で、適切な初動対応と十分な準備を整えれば、会社の立場を守りつつ、交渉を円滑に進めることが可能です。そのためには、労働問題に精通した弁護士へ早めに相談し、具体的な助言を受けながら進めることが重要です。
よつば総合法律事務所では、労働組合との交渉対応や不当労働行為リスクの回避など、企業法務に関する幅広いサポートを行っています。労働組合対応に不安を感じている企業の方は、ぜひ一度ご相談ください。