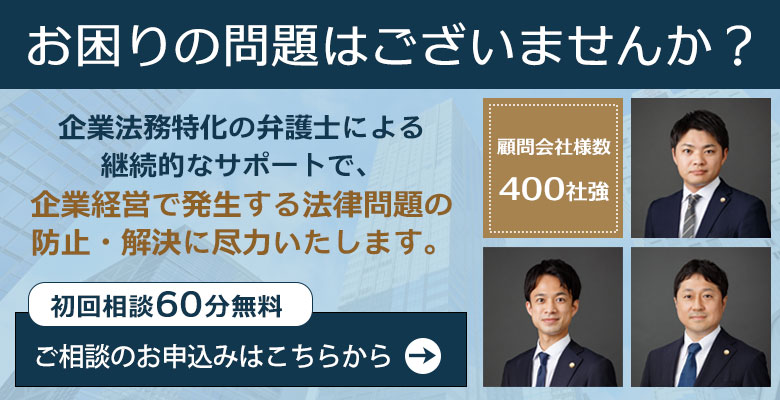労災事故が起きたとき、会社が負う責任は損害賠償にとどまりません。
事故の内容によっては、経営者や管理者が刑事責任を問われたり、労働基準監督署から行政処分を受けたり、さらには社会的信用を失って取引や採用に影響が及ぶこともあります。
本記事では、労災事故が発生した際に会社が負う可能性のある「民事・刑事・行政・社会的責任」の全体像を整理するとともに、解雇制限や保険料負担の増加といった会社側のデメリット、そして避けるべき「労災隠し」の問題についても解説します。
経営者・人事担当者が押さえておくべき基本知識をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 労災での会社の責任
労災事故が発生すると、会社は「民事上」「刑事上」「行政上」の責任に加えて、信用失墜や企業イメージ低下といった「社会的責任」を負う可能性があります。
ここでは、それぞれの責任の内容を詳しく解説します。
1.1 民事上の責任
労災事故において会社がまず直面するのは、被災した労働者やその遺族からの損害賠償請求です。
労災保険では、治療費や休業中の収入の一部は補償されますが、精神的苦痛に対する慰謝料は対象外です。
また、後遺障害や死亡によって失われた将来の収入(逸失利益)なども、労災保険給付だけでは十分にカバーされない部分があります。
そのため、労災認定を受けた場合でも、会社は労働契約上の安全配慮義務違反や民法上の不法行為責任を根拠に、追加の賠償を請求される可能性があります。
特に過労死や過労自殺などの深刻な事案では、1億円を超える高額な損害賠償が命じられた例もあります。民事上の責任は、会社にとって極めて大きなリスクと言えるでしょう。

1.2 刑事上の責任
労災事故が発生した場合、会社や経営者・管理者が刑事責任を問われることがあります。特に問題となるのは、次の3つの法令違反です。
1.2.1 労働安全衛生法違反
労働安全衛生法は、事業者に対して、安全管理者や産業医の選任、危険防止措置の実施、健康診断の実施など、広範な義務を課しています。これらの義務を怠ると、労働安全衛生法違反として刑事処分を受ける可能性があります。
また、会社の代表者や安全管理者などの個人が責任を問われることもあります。その場合、違反行為を行った個人だけでなく、会社も併せて罰金刑を受ける可能性があります。これは「両罰規定」と呼ばれる制度で、個人と法人の双方に刑事責任が及ぶことを意味します。
なお、労災の発生自体が直ちに法違反を意味するわけではありませんが、事故をきっかけに監督機関の調査が入り、安全管理体制の不備などの違反が発覚するケースは少なくありません。
1.2.2 業務上過失致死傷罪
現場の設備に不具合があり、それを認識していながら点検や修理を怠った結果、労働者が死亡・負傷した場合には、管理者や現場責任者が業務上過失致死傷罪に問われることがあります。
刑罰は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。
この罪については両罰規定がないため、会社そのものが直接処罰されることはありません。
しかし、労働安全衛生法違反が併せて認定されれば、両罰規定に基づき会社も罰金刑を受けることになります。
実際に、設備の不具合を放置して死亡事故が発生した事例として、副工場長と従業員が業務上過失致死罪で処罰されるとともに、会社も労働安全衛生法違反で罰金100万円の処分を受けた事例もあります。
1.2.3 労働基準法違反
過労死や過労自殺など、長時間労働が背景にある労災の場合、違法な時間外労働や休日労働が行われていたとして、労働基準法違反が問題となるケースが多く見られます。
この場合、直接の管理責任を負う上司などが6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、労働基準法にも両罰規定があるため、違反を行った個人だけでなく、法人である会社も併せて罰金刑を受ける可能性があります。
なお、36協定を結んでいたとしても、その内容に違反して法定上限を超える労働を命じた場合には労働基準法違反となるため、十分な注意が必要です。
1.3 行政上の責任
労災事故が発生した場合、会社は行政上の責任も負う可能性があります。
1.3.1 是正勧告・行政指導
典型的なのは、労働基準監督署からの是正勧告や指導です。
違反が認められれば、労働基準法や労働安全衛生法に基づき、改善計画の提出や報告を求められます。是正勧告に従わない場合、悪質事案と評価され、送検や刑事責任に発展することもあります。
1.3.2 業務停止・使用制限などの行政処分
労災事故の内容によっては、行政処分が直接的に会社の事業運営を制限することもあります。
たとえば、労働安全衛生法違反が重大な場合には、機械の使用停止や特定作業の中止を命じられることがあり、生産ラインや工事現場がストップしてしまう危険があります。これは単に罰金を科されるよりも大きな経済的損失につながります。
また、特に建設業や運送業など許認可を前提とする業種では、他の法令違反を理由に営業停止や許可取消しを受ける可能性も否定できません。実際に、過労死が発生した建設業者が労働基準法違反を理由に営業停止処分を受けた例も存在します。
このように、労災事故は労働関係法令違反にとどまらず、事業存続そのものを脅かす行政処分へとつながり得るのです。
1.3.3 指名停止・入札除外などの不利益措置
公的契約や公共事業の入札に参加している企業の場合、労災事故を理由に指名停止や入札参加停止措置が取られることもあります。こうした措置は、売上や信用に直接影響し、長期的な取引関係にも悪影響を及ぼします。
1.4 社会的な責任
労災事故が発生すると、会社は法的な責任を超えて「社会的な責任」を問われることになります。
重大な事故や過労死・過労自殺の事案では、新聞やテレビで報道されることが多く、インターネットやSNSで情報が拡散することで、瞬く間に社会的信用が低下します。
また、複数の事業所で違法な長時間労働や労災が確認され、その状態が是正されない場合などには、厚生労働省によって企業名が公表されるという制度があります。この公表がなされてしまうと、いわば「国が公認したブラック企業」というイメージが定着し、より深刻な企業イメージの低下につながります。
社会的信用の低下は、企業経営に長期的な悪影響を与えます。
まず、取引先が安全面の不安を理由に契約を見直したり、新規の取引を控えたりする可能性があります。金融機関からの評価も下がり、融資条件が悪化するリスクもあります。さらに採用活動においては、応募者から敬遠され、若手人材の確保が難しくなることも少なくありません。
こうした社会的責任は、法律に基づく制裁と異なり、回復に時間がかかります。一度「危険な会社」というイメージが定着すると、ブランド価値や企業イメージを取り戻すのは容易ではありません。
2. 会社側から見た制限やデメリット
労働災害が発生すると、法的責任にとどまらず、会社の運営や人事戦略に対して制度上の制約や経済的負担が生じる可能性があります。
特に重要なのが、「解雇に関する制限」と「労災保険料の上昇」です。これらは労災発生直後だけでなく、中長期的な人事・労務管理に影響するため、制度の内容を正確に理解しておく必要があります。
2.1 解雇制限
労働基準法19条1項は、労働者が業務災害によりけがや病気で療養のため休業している期間と、その後30日間は解雇してはならないと定めています。これは、療養中の労働者の生活を守り、安心して治療に専念できるようにするための制度です。従業員の過失が大きい事故であっても、この解雇制限は適用される点に注意が必要です。
ただし、この解雇制限にも「適用外となる場合」や「例外的に解雇が認められる場合」があります。また、定年や契約期間満了などによる身分関係の終了は別枠として扱われます。
2.1.1 解雇制限の適用外
まず、通勤災害による休業は、解雇制限の対象にはなりません。通勤災害で休業している従業員については、私傷病と同様に就業規則の休職規定が適用され、休職期間が満了しても復職できない場合には解雇することが可能です。
2.1.2 解雇制限の例外
次に、業務災害による休業であっても、法律上解雇が認められる例外があります。
① 治癒後30日が経過した場合
1つ目は、治癒後30日が経過した場合です。ここでいう治癒とは、症状固定を意味し、必要な治療が一通り終了した段階を指します。後遺障害が残っていても、症状が固定すれば治癒とされ、30日を過ぎれば解雇制限はなくなります。
② 打切補償を支払った場合
2つ目は、打切補償を支払った場合です。療養開始から3年経過しても治療が続いている場合、会社は平均賃金の1200日分を支払うことで解雇できます。ただし、支払額が高額となるため実務上の負担は大きくなります。
③ 傷病補償年金を受給している場合
療養開始から3年が経過した日以後に、被災労働者が労災保険から傷病補償年金を受給している場合には、会社は「打切補償」を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
④ やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合
4つ目は、やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合です。天災などで事業の存続自体が困難になったときに、労働基準監督署長の認定を受ければ解雇が許されます。ただし、単なる経営難では該当しません。
2.1.3 身分関係の終了にあたる場合
労働契約の終了には「解雇」以外にも、定年退職や契約期間の満了といった形式があります。これらは、解雇制限の対象とは異なる取り扱いとなります。
① 定年退職
就業規則に基づく定年到達の場合は、休業中であっても定年退職扱いとすることが可能です。
② 契約期間満了による雇止め
契約社員については契約期間満了時に雇止めできますが、労働契約法19条の「雇止め法理」による制限を受ける場合があります。実質的に正社員と同視できるような状態であれば、合理的な理由がない限り雇止めは無効とされるリスクがあるため注意が必要です。
2.2 労災保険料の上昇
一定規模以上の企業には、労災保険料に関する「メリット制」が適用されます。
これは、過去に発生した労災事故の件数や給付額に応じて、翌年度以降の保険料率が増減する制度です。
この制度では、直近3年間に労災保険から支払われた給付額の合計が目安となり、それに応じて翌年度以降の保険料率が増減します。事故や給付が多ければ保険料率は引き上げられ、少なければ引き下げられる仕組みです。
具体的には、最大で40%の増減幅が設定されており、重大事故が起きた場合には数年間にわたり高い保険料負担を強いられることになります。

3. 「労災隠し」は厳禁
「保険料の上昇を抑えたい」「労基署の調査で法令違反が発覚するのを防ぎたい」「企業イメージが損なわれるのを避けたい」といった理由から、労災の届出をためらう企業もあります。
しかし、労働災害についての報告を怠る、事実と異なる内容で届け出る、被災労働者に健康保険証で受診させるといった対応はすべて「労災隠し」に当たり、刑事責任の対象となります。
労災隠しとは、本来提出すべき労働者死傷病報告を行わない、あるいは虚偽の内容で提出する行為のことで、労働安全衛生法により禁止されています。違反した場合には50万円以下の罰金が科され、さらに両罰規定により法人自体も処罰されます。
現場では「会社で治療費を立て替えるから申請しないでほしい」「元請や取引先に迷惑がかかる」といった理由で労災申請をさせず、健康保険で処理させる事例が散見されます。
しかし、業務災害に健康保険を使うことはできず、形式的に隠しても、最終的には被災者からの通報や医療機関からの照会、労基署の調査を通じて発覚するケースが多いのが実情です。発覚後は刑事罰に加え、企業名の公表、入札資格の停止、許認可への影響、金融機関や取引先からの信用低下といった深刻な二次被害につながります。
さらに、労災隠しは被災労働者本人にも大きな不利益を与えます。労災保険からの療養補償や休業補償、障害補償などを受けられず、医療費や生活費を自己負担せざるを得なくなるためです。その結果、会社との間で紛争化し、高額な損害賠償請求や刑事告発に発展するリスクが高まります。
労災隠しを避けるためには、従業員や現場に対して「発生した事故は必ず報告する」姿勢を徹底させることが重要です。企業としては、社内の報告フローや責任者を明確にし、必要な教育を行うとともに、就業規則に労災隠しを懲戒事由として定めておくことも有効です。発生した労災は速やかに事実を把握し、適切に所轄労基署へ報告しましょう。
4. まとめ:労災事故の会社の責任は弁護士に相談
労災事故が発生した場合、会社には多方面での責任が生じます。損害賠償請求や刑事罰、行政処分に加え、企業名の公表や取引先からの信用低下など、経営に直結するリスクは決して軽視できません。また、労災隠しなど誤った対応をすれば、問題はさらに深刻化し、企業の存続すら脅かされることもあります。
一方で、労災保険の制度や法的な責任の範囲は複雑であり、誤解や対応の遅れから紛争に発展するケースも少なくありません。
そのため、労災事故が起きた際には、初動の段階から弁護士に相談しておくことが望ましいといえます。
弁護士に相談することで、報告義務や保険手続きの適切な進め方、被災者対応、損害賠償請求への備えなどを専門的にサポートしてもらうことができます。企業としての法令遵守を徹底し、不要なトラブルを回避するためにも、労災事故への対応は一人で抱え込まず、弁護士の力を活用することをおすすめします。