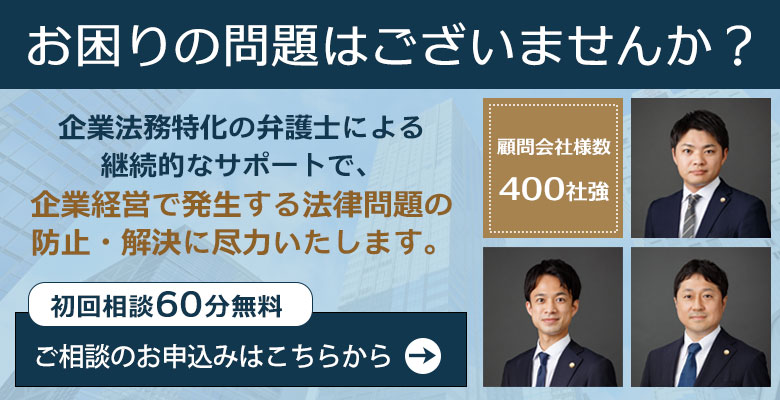労災事故が起きたとき、会社はどこまで責任を負わなければならないのでしょうか。
労災保険があるからといって、すべての補償が自動的に行われるわけではありません。場合によっては、会社が別途、慰謝料や逸失利益を請求されるケースもあり、思わぬ高額の損害賠償に発展するリスクもあります。
本記事では、労災事故に関して会社が負う損害賠償の責任について、経営者・人事担当者の視点から、弁護士が分かりやすく整理します。備えるべきポイントをぜひこの機会に確認しておきましょう。
1. 労災での損害賠償責任の根拠
労災事故が起きたとき、会社に損害賠償責任が発生するかどうかは、法律上の「請求根拠」があるかどうかによって決まります。労災保険の給付はあくまで公的補償であり、会社の責任そのものを免除するものではありません。
会社の責任が問題となる典型的な根拠は、次の3つです。
- ① 従業員の安全を守る義務に違反した場合(安全配慮義務違反)
- ② 他の従業員の過失に会社が連帯して責任を負う場合(使用者責任)
- ③ 設備や建物の欠陥が事故原因となった場合(工作物責任)
ここでは、それぞれの責任がどのような場面で問われるのか、具体的に解説していきます。
1.1 安全配慮義務違反
会社には、従業員が安全かつ健康に働けるよう、必要な配慮を行う義務があります。この義務は労働契約法5条、労働安全衛生法3条、民法415条などを根拠としており、実務上もっともよく問題になります。
安全配慮義務の内容は職場環境や業種によってさまざまですが、典型的には次のようなものがあります。
- 機械や設備を適切に点検・整備して事故を防止する義務
- 長時間労働によって心身の健康を損なわせない義務
- 職場のパワハラやセクハラを防止し、メンタル面の健康を守る義務
これらの対応を怠った結果、労災事故や健康被害が発生した場合には、安全配慮義務違反として会社に損害賠償責任が問われる可能性があります。
安全配慮義務違反があったかどうかは、主に次の2点によって判断されます。
① 予見可能性
事故や健康被害を事前に予測できたかという点です。
② 結果回避可能性
合理的な措置で結果を避けられたかという点です。
たとえば、危険な作業環境が事前に分かっていたにもかかわらず、教育・装備・人員配置などの対応を怠っていた場合、会社の責任が認められやすくなります。具体的な場面としては、次のようなケースが挙げられます。
- 工場で機械に安全装置を付けずに稼働させ、従業員が巻き込まれて負傷した
- 高所作業において足場や安全帯の整備を怠り、墜落事故が発生した
- クレーンやフォークリフトの操作手順を守らせず、荷の落下や接触事故が起きた
- 長時間労働を是正せず、従業員が過労による健康障害を発症した
また、正社員に限らず、下請労働者や派遣社員についても、会社が現場の管理や指揮を行っている場合には、安全配慮義務が及ぶと判断されることがあります。
1.2 使用者責任
労災事故の中には、従業員の不注意や過失によって他の従業員や第三者に損害が生じるケースがあります。こうした場合、事故を起こした本人だけでなく、会社にも損害賠償責任が生じる可能性があります。これが「使用者責任」と呼ばれるものです。民法715条を根拠としています。
使用者責任は、次の3つの要件を満たす場合に成立します。
① 使用関係があること
会社と従業員の間に雇用関係があることが前提となります。正社員に限らず、契約社員やアルバイトも含まれます。
② 従業員の行為が不法行為に当たること
過失や故意によって他人の身体や財産に損害を与えた場合、不法行為(民法709条)に該当します。たとえば、操作ミスで同僚にけがをさせたケースなどが典型です。
③ 損害が「事業の執行につき」発生していること
事故が従業員の私的行為ではなく、業務の遂行に関連して発生したものである必要があります。勤務時間中や会社の業務に直接関連する作業での事故が該当します。
具体的には、次のようなケースで使用者責任が問題となります。
- 十分な操作研修を受けさせないままフォークリフト業務に従事させたところ、従業員が別の作業者に衝突した
- 勤務中の従業員のドライバーが、会社内の駐車場で他の従業員と接触事故を起こした
- 従業員が集中力を欠いて機械操作を誤り、他の従業員にけがを負わせた
もっとも、会社が従業員の選任・監督について「相当の注意を尽くしていたこと」「相当の注意を払っても損害が生ずべき状況だったこと」を立証できれば免責される余地があります。しかし、実務上はこの免責が認められることはまれで、結果として会社が責任を負う場面が多くなります。
1.3 工作物責任
「工作物責任」とは、建物・構造物・設備などの設置や管理に不備があった場合に、その所有者や占有者が損害賠償責任を負う制度です。民法717条を根拠としています。
ここでいう「工作物」とは、土地に継続的に接着して設置されている建物や構築物、備え付けられた設備などを指します。工場、倉庫、足場、階段などです。
従業員がこれらの設備の不具合によりけがをした場合、会社が損害賠償責任を問われることがあります。
具体的には、次の2つの要件を満たす場合に、工作物責任が成立します。
① 工作物に設置または保存の瑕疵があること
「瑕疵」とは、本来備えているべき安全性を欠いている状態を指します。足場の固定が不十分、機械の安全装置が壊れたまま放置されている、といったケースが典型です。
② その瑕疵と損害との間に因果関係があること
瑕疵が原因となって事故が発生し、労働者に損害が生じたことが必要です。たとえば、棚の固定不良による倒壊でけがをした場合には因果関係が認められますが、無関係な理由で倒れた場合には成立しません。
典型的な事例としては、次のようなものがあります。
- 工事現場の足場が崩落し作業員が負傷した
- 重量ラックの設置位置不良で通路がふさがれ、通行中に負傷した
- 老朽化したエレベーターが整備不良で事故を起こした
なお、責任を負う主体については、まず「占有者」(実際に管理している者)が賠償責任を負います。占有者が必要な注意を尽くしていたと認められる場合には、所有者が代わって責任を負うことになります。
建物や設備の管理不備は、事故が起きたときに会社の責任に直結しやすく、損害賠償リスクも高まります。日常的な点検と整備の体制を構築しておくことが、最も確実なリスク対策です。

2. 損害賠償の範囲
労災事故で会社に損害賠償責任が生じる場合、賠償の対象は大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害(慰謝料)」の2つです。
労災保険によって一部の補償は受けられますが、保険ではカバーされない損害について、会社が追加で賠償責任を負うことがあります。
2.1 財産的損害
財産的損害とは、労災事故によって実際に発生した費用や、得られるはずだった収入の喪失など、経済的な損失全般を指します。
主な項目は次のとおりです。
・積極損害(実際に支出した費用)
治療費、入院費、通院交通費、入院雑費、家族の付添看護費、器具・装具の購入費、将来介護費、葬儀費などです。これらのうち、労災保険で補償されない部分について会社が責任を負う可能性があります。
・消極損害(得られたはずの利益の喪失)
休業損害や逸失利益が典型です。
休業損害については、労災保険からは給付基礎日額の約6割しか原則補償されません。
そのため、休業損害の残りの4割は会社に請求される可能性があります。
また、後遺障害や死亡事故が生じた場合には、将来得られるはずだった収入(逸失利益)も賠償の対象となります。労災保険からは障害補償年金や遺族補償年金などが支給され、一部は補償されますが、実際の収入水準に見合った全額が支給されるとは限りません。
そのため、労災保険でカバーされない逸失利益の不足分については、会社が損害賠償責任を問われる可能性があります。
2.2 精神的損害
財産的損害とは別に、事故によって生じた精神的な苦痛に対する賠償も必要となる場合があります。これが「慰謝料」です。
労災保険では慰謝料は支給されないため、会社が直接支払う必要があります。慰謝料には主に次の3種類があります。
① 入通院慰謝料
入院・通院を余儀なくされたことによる苦痛に対する補償
② 後遺障害慰謝料
後遺症が残った場合に、後遺障害等級に応じて支払われる補償
③ 死亡慰謝料
労働者が死亡した場合、その本人の慰謝料に加え、遺族の慰謝料も含めて支払われる補償
慰謝料の金額は、交通事故の損害賠償と同様に裁判例や「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)を参考にして算定されるのが一般的です。
2.3 労災からの給付額の控除
労災事故が発生した場合、まずは労災保険によって治療費や休業補償などの一定額が給付されます。しかし、これはあくまで一部の補償にすぎず、労災給付ではカバーされなかった不足分については、会社に損害賠償義務が残ることになります。
実務上は、「損害全体のうち、すでに労災で支払われた金額を差し引き、その残額について会社が責任を負う」という考え方が基本です。つまり、項目そのものが賠償対象から外れるわけではなく、あくまで「部分的に補償済み」という整理になります。
たとえば、次のような関係が成立します。
| 損害項目 | 労災補償分 | 会社負担分 |
|---|---|---|
| 治療費 | 療養補償給付 | 自己負担分 |
| 休業損害 | 休業補償給付(6割) | 残りの4割 |
| 逸失利益 | 障害・遺族補償給付 | 不足分 |
一方で、労災保険ではまったく支払われない次のような項目については、会社が全額賠償することになります。
- 慰謝料(精神的損害)
- 入院雑費や付添看護費など労災の対象外となる費用
このように、労災保険と損害賠償は「別物」であり、会社は「労災で足りなかった分」について賠償責任を負うという前提で考える必要があります。
2.4 過失相殺と素因減額
労災事故が起きたとき、その原因について労働者側にも一定の不注意が認められる場合、会社の損害賠償額が減額されることがあります。これが「過失相殺」という考え方です。
具体的には、次のようなケースでは労働者にも過失が認められる可能性があります。
- 足場を設けずに高所作業をして転落した
- 命綱を着用せずに作業していた
- 安全確認を怠って機械を操作した
もう一つ関連する制度に「素因減額」があります。これは、事故の発生や損害の拡大に、労働者の持病や既往症などの“個人的な要因”が影響している場合に、賠償額を一部減額できるという考え方です。
たとえば、次のようなケースが該当します。
- 事故前から高血圧・糖尿病などの持病があり、症状が悪化した
- 精神疾患(うつ病など)の影響で損害が拡大した
ただし、減額が認められるためには次の2つの要件を会社側が立証する必要があります。
- ① 「体質」ではなく医学的に認められる疾患であること
- ② その疾患が、労災による損害の発生や拡大に現実に影響したこと
過失相殺や素因減額はいずれも、まず「会社と労働者の責任割合」を決め、その割合に応じて賠償額を調整するという考え方に基づいています。たとえば「労働者30%:会社70%」と判断されれば、会社の賠償責任は7割にとどまることになります。
3. 損害賠償責任の時効
労働災害における損害賠償請求には時効があり、その期間は会社がどのような法的責任を負うかによって異なります。主な責任の形態は「債務不履行」と「不法行為」に分けられます。
3.1 債務不履行の場合(安全配慮義務違反)
会社が従業員との労働契約に基づく「安全配慮義務」を怠った場合、その責任は「債務不履行」となります。たとえば、工場で機械に安全装置を付けず稼働させた、高所作業で足場を整備せず墜落事故を招いた、長時間労働を放置して健康障害を生じさせた、といったケースが典型例です。
債務不履行(安全配慮義務違反)の時効は次のとおりです。
① 労働者が権利を行使できることを知った時から5年
② または、権利を行使できる時から10年
なお、生命・身体の侵害による損害賠償請求については、長期の消滅時効期間が10年ではなく20年とされる特則があります(民法167条)。
3.2 不法行為の場合(使用者責任・工作物責任)
不法行為とは、会社が従業員を使用する立場で負う「使用者責任」や、建物や設備の欠陥に基づく「工作物責任」などのことです。
たとえば、重機の操作を誤った従業員が同僚を負傷させた(使用者責任)、工場の老朽化した床や不備のあるクレーン設備のせいで事故が起きた(工作物責任)、といったケースがこれにあたります。
不法行為(使用者責任・工作物責任)の時効は次のとおりです。
① 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年
② または、不法行為の発生から20年

4. よくあるご質問
ここでは、労災事故と会社の損害賠償責任に関して、経営者や人事担当者の方から寄せられることの多いご質問にお答えします。
4.1 労災からの給付があれば、会社は追加の損害賠償責任を負わないのですか?
労災からの給付があっても、会社は追加の損害賠償責任を負うことがあります。
労災保険から給付があることで、治療費や休業補償の一部は補償されますが、それですべての責任が消えるわけではありません。
たとえば、以下のような項目については労災では補償されず、会社が追加で賠償責任を負う可能性があります。
- ① 精神的苦痛に対する慰謝料
- ② 入院雑費・付添看護費
- ③ 労災給付でカバーしきれない休業損害や逸失利益の一部
したがって「労災保険で給付された部分は会社の負担が免除されるが、それ以外の損害については会社が賠償責任を負う」というのが正しい理解です。
4.2 労災認定がされても、会社が損害賠償責任を負わないことはありますか?
労災認定がされても、会社が損害賠償責任を負わないことはあります。
労災は「業務中の事故や病気かどうか」で判断されるため、会社に注意義務違反や安全配慮義務違反がなくても認定されることがあります。
この場合、労災保険からの給付は行われますが、会社に過失がない以上、損害賠償責任までは負いません。
5. まとめ:労災事故の損害賠償は弁護士に相談
労災事故が発生すると、労災保険の給付に加えて、会社が損害賠償責任を負う場合があります。特に、安全配慮義務違反や使用者責任、工作物責任などが認められた場合には、慰謝料や逸失利益など高額な賠償請求に発展することも少なくありません。
一方で、労災保険から給付される範囲との調整や、労働者本人に過失がある場合の過失相殺など、会社の責任が軽減されるケースも存在します。こうした判断は複雑で、対応を誤ると不必要に大きな負担を抱えるおそれがあります。
そのため、労災事故に関する損害賠償の問題が生じた場合は、早い段階で企業法務に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、会社の法的リスクを正しく見極め、適切な対応策をとれる可能性が高まります。