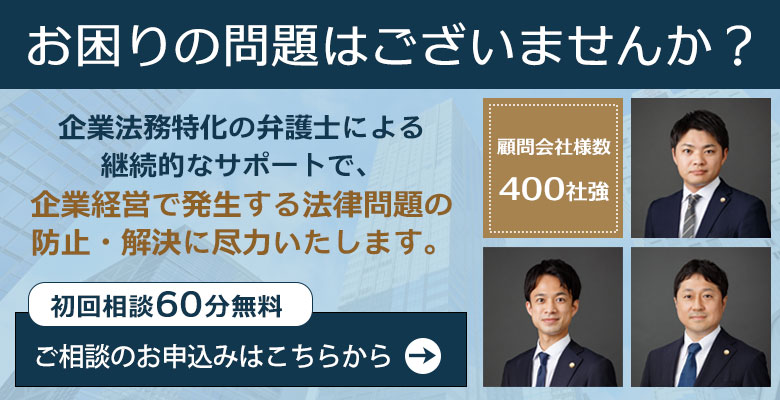「売掛金がなかなか回収できない」
「費用をかけずに債権を取り戻したい」
そんなお悩みをお持ちの経営者や担当者の方にとって、有効な選択肢となるのが「少額訴訟」です。
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に限って利用できる簡易な裁判手続きです。
原則として1回の審理で判決が出るため、債権回収をスピーディかつ低コストで行えるのが大きな特徴です。
しかし、利用にあたってはいくつかの制約や注意点もあり、状況によっては通常訴訟や支払督促といった他の手段のほうが適していることもあります。
この記事では、企業の債権回収に詳しい弁護士が、少額訴訟の基本から手続きの流れ、メリット・デメリット、判決後の強制執行までをわかりやすく解説します。
少額訴訟を検討中の方はもちろん、すでに手続きを進めている方にとっても役立つ内容を網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 少額訴訟とは?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭を請求する際に利用できる、簡易裁判所での特別な裁判手続きです。
通常の民事訴訟とは異なり、原則として1回の期日(裁判の日)で審理が終わり、すぐに判決が言い渡されます。
この判決には「仮執行宣言」が付されるため、判決が確定するのを待たずに、ただちに強制執行に移ることも可能です。
ただし、少額訴訟にはいくつかの制限があります。
たとえば、被告が少額訴訟を望まない場合には、通常の訴訟に切り替えられます。
また、少額訴訟を利用できる回数は1人(1法人)あたり年間10件までと定められています。
少額訴訟は、紛争を迅速かつ手軽に解決したい方に適した制度ですが、利用する際はその仕組みや制限をしっかり理解しておくことが重要です。
1.1 少額訴訟と通常訴訟の違い
少額訴訟と通常訴訟の大きな違いは、手続きの簡易さとスピード感にあります。
通常訴訟では、裁判が複数回にわたって行われ、解決までに何か月もかかることが一般的です。
これに対して、少額訴訟は原則として1回の裁判で審理を終え、即日判決が出されます。
また、証拠の取り扱いにも違いがあります。
少額訴訟では、その場ですぐに確認できる証拠だけが扱われ、専門的な証拠調べや反訴(相手からの逆請求)は認められていません。
控訴(上級裁判所への不服申し立て)もできず、判決に不服がある場合は、同じ簡易裁判所に「異議申立て」を行う形をとります。
1.2 少額訴訟ができる要件
少額訴訟を利用できるのは、次の要件をすべて満たす場合に限られます。
① 請求する金額が60万円以下であること(利息や遅延損害金は除く)
② 金銭の支払いを求める訴えであること(物の返還や行為の請求は不可)
③ 簡易裁判所が管轄する案件であること
④ 当事者1人あたり年10回までの制限内であること
⑤ 被告(相手)が同意していること(同意しないと通常訴訟に移行)
⑥ 裁判所が少額訴訟による解決が相当であると判断していること

2. 少額訴訟を利用するメリット
少額訴訟は、手続きの簡単さやスピード感、費用面での負担の軽さから、債権回収において大きなメリットがあります。
ここでは、債権回収において少額訴訟を利用する3つのメリットをご紹介します。
2.1 手続きが簡単
少額訴訟は、通常の民事訴訟と比べて手続きが非常に簡単です。
一般的な訴訟では、複数回にわたって裁判所へ出廷し、主張や証拠をやり取りする必要がありますが、少額訴訟では原則として1回の期日で審理が終わり、その場で判決が出されるのが基本です。
証拠も、その場で確認できる書類や記録など、即時に判断できる資料に限られるため、複雑な証拠調べは行われません。
そのぶん、当事者の準備の負担も軽くなります。
また、口頭弁論の手続きも簡略化されており、書面のやりとりが少ないため、法律の専門知識がなくても比較的対応しやすい制度です。
2.2 迅速な解決
債権回収の現場では、スピードが命です。
特に、債権者側の資金繰りに影響が出ている場合には、できるだけ早く債権を回収する必要があります。
少額訴訟は、原則1回の審理で結論を出すことを前提としているため、通常の民事訴訟に比べて解決までの時間が大幅に短縮されます。
実際、少額訴訟の平均的な審理期間はおおよそ2か月程度とされており、スピーディな解決が期待できます。
2.3 費用が安価
まず、裁判にかかる費用として必要になるのは、収入印紙代と郵便切手代です。
印紙代は請求金額に応じて変動し、訴額が高いほど高くなります。
一方、郵便切手代は、裁判所が書類を送付するための実費で、裁判所ごとに細かく定められています。
60万円以下の請求であれば、これらの費用は比較的少額に収まることが多く、さらに少額訴訟では原則1回の出廷で済むため、交通費や仕事を休む日数といった間接的な負担も抑えられます。
また、手続きが簡易なため、弁護士に依頼せず自力で対応することも十分可能です。専門家への依頼費用が不要になる点も、大きなメリットといえるでしょう。
このように、少額訴訟は金銭的・時間的なコストを抑えながら、効率よく債権を回収できる制度として活用されています。
3. 少額訴訟を利用するデメリット
少額訴訟は簡便で費用負担が少ない制度ですが、利用にあたっては注意すべき点もあります。
ここでは、債権回収の場面で少額訴訟を選ぶ際に知っておきたい主なデメリットを解説します。
3.1 請求額が60万円を超えると使えない
少額訴訟は、請求額が60万円以下の金銭請求に限って利用できる制度です。
利息や遅延損害金などの附帯請求を除いた元本が60万円を超える場合は、通常の訴訟手続を選ばなければなりません。
そのため、少しでも請求額が基準を超えてしまうと利用できず、制度の対象として制限がある点には注意が必要です。
3.2 金銭請求しかできない
少額訴訟は、金銭の支払いを目的とした請求に限って利用可能な手続きです。
そのため、物の引き渡しや契約の履行など、金銭以外の請求には使えません。
たとえば、賃貸借契約における物件明渡しや、商品の返品・交換といった請求については、たとえ請求額が60万円未満であっても、少額訴訟の対象とはなりません。
こうしたケースでは、簡易裁判所での通常訴訟や調停など、別の手続きを選ぶ必要があります。
3.3 被告が希望すれば通常訴訟に移行する
原告が少額訴訟として訴えを起こしても、被告側が通常訴訟を希望すれば、訴訟は自動的に通常訴訟に移行します。
被告はその理由を説明する必要もなく、形式的な申出のみで移行が認められます。
この場合、せっかく少額訴訟に合わせて1回で終わるように準備を整えていたとしても、その準備が無駄になる可能性があります。
証人を裁判所に同行させていた場合などは、再度の呼出しが必要になったり、日程調整に手間取ったりすることもあります。
さらに、少額訴訟が通常訴訟に切り替わると、手続きが複雑になり、審理回数も増える傾向があります。
その結果、費用や時間、心理的な負担が大きくなる恐れもあるため、被告の出方次第で通常訴訟に発展する可能性があることは、原告にとってリスクといえるでしょう。
4. 少額訴訟の手続きの流れ
ここでは、実際に少額訴訟を行う際の基本的な流れを紹介します。
各段階で何をすべきかをあらかじめ把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
4.1 訴状や証拠書類の提出
まずは、訴状を作成して裁判所に提出します。
訴状には請求内容や理由、証拠の概要などを記載します。
少額訴訟は1回の審理で終了することが原則のため、必要な情報はすべてこの段階で提出する必要があります。
契約書や請求書などの証拠書類も、訴状と一緒に提出するのが一般的です。
4.2 答弁書や証拠書類の受領
訴状が受理されると、裁判所から被告に訴状や証拠の写し、期日呼出状が送付されます。
被告はそれらを受け取り、反論の内容を記載した答弁書を裁判所に提出します。
原告もこの答弁書を受け取り、どのような争点があるのかを事前に確認します。
被告が通常訴訟を希望する場合は、この時点で移行の申出を行います。
4.3 審理期日
通常訴訟に移行しなければ、指定された期日に裁判が開かれます。
少額訴訟は原則として1回の審理で終了するため、この日にすべての主張と証拠の提出を完了させる必要があります。
場合によっては、証人尋問が行われることもあります。
4.4 和解又は判決
審理の途中で裁判所から和解を提案されることがあります。
双方が条件に合意すれば、和解が成立し、訴訟は終了します。
和解に至らない場合には、審理の後にその日のうちに判決が言い渡されるのが一般的です。
4.5 判決後
判決に不服がある当事者は、2週間以内であれば異議申立てが可能です。異議申立てが行われると、通常訴訟と同様の手続きで改めて審理が行われます。
また、勝訴した場合であっても、相手が自発的に支払わないこともあります。
その場合は、債務者の財産に対して強制執行を行う必要があります。
なお、少額訴訟で言い渡される判決には「仮執行宣言」が付けられるのが原則です。
これは、判決が確定していなくても強制執行が可能となる制度で、回収までのスピードを速める効果があります。
強制執行を検討する際には、判決に仮執行宣言があるかどうかを必ず確認しておきましょう。
5. 手数料や必要書類の準備
少額訴訟を行うには、裁判所に提出する書類の準備と、一定の費用が必要になります。
ここでは、訴訟にかかる代表的な費用や書類の記載ポイント、証拠の揃え方について解説します。
5.1 印紙代や郵便切手などの費用目安
少額訴訟には、大きく分けて「印紙代」と「郵便切手代」の2つの費用がかかります。
印紙代は、請求する金額(訴額)によって決まります。
たとえば、請求額が10万円なら1,000円、20万円なら2,000円、60万円なら6,000円となります。
このように、金額が高いほど印紙代も上がっていきます。
印紙は訴状に貼って裁判所に提出します。
一方、郵便切手代は、裁判所から相手に書類を送るために必要な費用です。
金額は裁判所によって異なることもありますが、東京簡易裁判所では被告1人あたり5,200円程度が目安です。
被告が2人以上いる場合は、その分切手代も増える点に注意が必要です。
5.2 訴状の記載方法
訴状は、裁判所に「こういう理由で相手に支払いを求めたい」と伝えるための基本となる書類です。
裁判所のウェブサイト には記載例や書式も掲載されています。
訴状には、次のような情報を漏れなく記載する必要があります。
- 原告(訴える側)と被告(訴えられる側)の名前と住所
- いくら支払ってほしいのか、どうしてその金額を請求するのか(請求の趣旨と原因)
- 請求の内容に関係する事実(たとえば、いつ契約したのか、どんな約束だったのかなど)
- 添付する証拠の一覧(契約書や請求書など)
また、「訴訟費用は被告の負担とする」と書き添えるのが一般的です。
5.3 証拠書類の準備や提出方法
少額訴訟では、審理が原則1回で終わるため、すべての証拠を最初に提出しておく必要があります。
裁判当日になってから新しい証拠を出すことは原則できないため、準備がとても重要です。
証拠としては、次のような書類が挙げられます。
- 契約書や注文書、請求書
- 納品書や領収書
- メールやLINEのやりとり
- 内容証明郵便の写しなど
特に債権があること(お金を払ってもらう理由)と、相手が払っていないことが分かる資料は必須です。
会社が原告となる場合は、会社の登記事項証明書(法務局で取得)も提出が必要です。
なお、提出方法は、訴状とあわせて裁判所に郵送または持参します。
コピーを複数部用意し、裁判所と相手方にそれぞれ渡せるようにしておきましょう。

6. 少額訴訟に関するよくあるご質問
ここでは、少額訴訟に関するよくある3つの質問について、実務的な観点から回答します。
6.1 相手が出廷しなかったらどうなる?
少額訴訟の期日に、被告(相手)が正当な理由なく出席しなかった場合、裁判所は原告の主張が認められるかどうかを、提出された訴状や証拠だけで判断します。
原告側の主張が合理的で証拠もそろっていれば、その場で原告勝訴の判決が出ることも珍しくありません。
ただし、いくら被告が出席しなくても、請求内容に無理がある場合や、証拠が不十分なときは棄却される可能性もあります。
相手が来なかったからといって、必ず勝てるわけではない点には注意が必要です。
6.2 判決までにどの位時間がかかる?
少額訴訟は、原則1回の審理で完了することが大きな特徴です。
訴状提出から第1回期日までには、通常1~2か月程度かかるのが一般的で、審理が予定どおり行われれば、その日のうちに判決が言い渡されることもあります。
6.3 判決に不服があるときはどうする?
少額訴訟では、通常の訴訟のように上級裁判所に控訴することはできません。
ただし、判決に不服がある場合には、原告・被告のいずれも、判決書の送達から2週間以内であれば「異議申立て」を行うことができます。
異議申立てがあると、同じ簡易裁判所で、今度は通常の民事訴訟手続として改めて審理が行われます。
この再審理では、証拠の追加提出や新たな主張も認められます。
なお、異議申立てに基づく通常訴訟の判決に対しては控訴ができないため、その判決が事実上の最終判断となります。
このため、初回の少額訴訟でも、できる限り丁寧に主張と証拠を整理しておくことが大切です。
7. 債権回収はまずは弁護士へ相談
少額訴訟は、コストと時間を抑えながら債権回収を目指せる有効な手段です。
しかし、その一方で、請求金額や手続きの条件に制限があり、事案によっては通常訴訟や支払督促、内容証明郵便の送付といった別の方法の方が適している場合もあります。
こうした判断は、債権の内容や相手方の対応状況、証拠の有無によって変わります。
たとえば、相手が争う姿勢を見せている場合や証拠が不十分なケースでは、いきなり少額訴訟を選ぶと不利になることもあります。
準備不足のまま手続きを進めてしまうと、敗訴リスクや費用倒れの可能性も否定できません。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、債権回収に取り組む際は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、少額訴訟の適否を含め、状況に応じた回収方法を提案し、書類の作成から手続きの代理までトータルでサポートできます。
少額とはいえ、未回収の債権は企業にとって大きな損失です。
迅速かつ確実に対応するためにも、少しでも不安を感じたら、まずは弁護士への相談から始めてみてください。