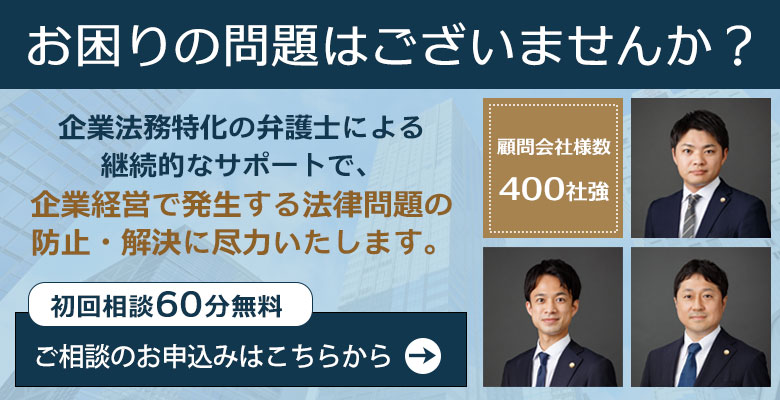「取引先に何度請求しても、支払いに応じてもらえない。このまま泣き寝入りするしかないのか、それとも法的手段に踏み切るべきか。」
そんなとき、まず確認すべきなのが「相手に本当に財産があるのかどうか」です。たとえ訴訟で勝っても、相手に資産がなければ回収はできません。
そこで重要になるのが「財産調査」です。
不動産、預貯金、給料、売掛金など、相手の財産状況を正確に把握することで、回収の可能性を見極め、無駄のない対応が取れるようになります。
本記事では、債権回収の実務に詳しい弁護士が、財産調査の具体的な手続き、メリット・デメリット、調査方法、費用感などをわかりやすく解説します。
目次
1. 財産調査とは?
財産調査とは、債務者がどのような財産を保有しているのかを明らかにする手続きです。
債権を確実に回収するためには、相手の資産状況を正確に把握しておくことが欠かせません。
たとえば、不動産を所有していれば差押えを検討できますし、預金口座が確認できれば強制執行によって回収できる可能性があります。
一方で、調査の結果、資産がまったく見つからなければ、法的手続に進んでも費用倒れになるリスクがあります。
こうした判断を的確に行うためにも、財産調査は債権回収における出発点として、極めて重要な役割を果たします。
2. 財産調査を行うメリット
債権回収を進めるうえで、財産調査を行うことにはいくつものメリットがあります。
どんな資産があるかを調べることで、裁判や強制執行に進むべきか判断しやすくなり、交渉にも有利に働きます。
ここでは、財産調査を行うことで得られる主なメリットを3つご紹介します。
2.1 回収の可能性がわかる
一番大きなメリットは、債務者から実際にお金を回収できるかどうか、目安がつけられることです。
たとえば、相手が不動産を持っていたり、安定した給与所得があったりすれば、差押えを通じて回収の見込みがあると判断できます。
反対に、資産がほとんど確認できなければ、訴訟や執行に進むことでかえって費用や手間がかさむだけの結果になるかもしれません。
事前に財産状況を確認しておけば、「費用対効果に見合うかどうか」を冷静に見極めることができます。
2.2 法的な手続きに実効性があるか判断できる
訴訟や強制執行などの法的手続には、時間も費用もかかります。
もし相手に財産がないまま裁判に進んでしまうと、「勝訴判決が出ても何も取れない」という事態に陥ることがあります。
財産調査によって、差押え可能な資産があるかどうかを事前に確認できれば、こうした無駄な手続を避けることができます。
つまり、
法的手続を「いつ・どの手段で・どの財産を対象に行うか」という実行計画を立てやすくなるのです。
2.3 債務者との交渉がしやすくなる
財産調査をして相手の資産状況がわかれば、話し合いによる解決(任意交渉)を有利に進めやすくなります。
たとえば、「給料があるのに払っていない」「不動産を所有している」など、客観的な情報をもとに交渉することで、相手にプレッシャーを与えることができます。
このように証拠を揃えたうえで、「支払いに応じなければ、差押えの手続きに進む可能性があります」と伝えれば、相手が真剣に支払いに応じるケースも少なくありません。
また、債務者としても強制執行を避けたいと考える人は多いため、分割払いや和解といった柔軟な解決策に応じてもらいやすくなります。
交渉段階での合意が得られれば、訴訟や執行にかかる時間や費用を省くことができ、双方にとって負担が軽くなります。

3. 財産調査を行うデメリット
財産調査には多くのメリットがありますが、実施する際には注意すべき点もあります。
ここでは、財産調査における代表的なデメリットを3つ紹介します。
3.1 費用がかかる
財産調査を行うには、一定の費用がかかります。
たとえば、弁護士に依頼する場合の着手金や報酬金、登記情報や住民票などを取得する手数料、調査会社を使う場合の費用などが挙げられます。
また、民事執行法に基づく情報取得や財産開示の手続を利用する場合も、数千円〜1万円程度の予納金や郵券(切手代)などが必要です。
これらの費用をかけたとしても、相手に差押えできるような財産がなければ、結果として「調査費だけがムダになった」と感じることもあります。
事前に予算を確認し、費用対効果をよく検討することが大切です。
3.2 時間がかかる
財産調査は、すぐに結果が出るとは限りません。
登記簿を取り寄せたり、役所に照会をかけたり、弁護士会を通じて情報を取得したりと、調査の内容によっては数週間から数か月かかることもあります。
特に、民事執行法に基づく情報取得手続や財産開示手続を利用する場合、裁判所での手続や期日の指定などもあるため、時間がかかりがちです。
「早く回収したい」「資金繰りにすぐにでも対応したい」というケースでは、時間的な負担がネックになることがあります。
3.3 財産隠しを誘発するかもしれない
調査を行っていることや、差押えの可能性があることが相手に伝わると、財産を隠そうとする動きが出る場合があります。
たとえば、預貯金を引き出して現金化したり、不動産を家族名義に移したりするなどの行為です。
これを「財産隠し」といいます。事前に差押えが察知されると、回収が難しくなるリスクがあります。
もちろん、弁護士を通じて適切な手順を踏むことで、こうしたリスクを減らすことは可能です。
しかし、調査の進め方を間違えると、相手に警戒されてしまう恐れがあるため、慎重に対応する必要があります。
4. 財産調査をするための方法
では、実際に財産調査をするためには、どのような方法があるのでしょうか。
ここでは代表的な5つの方法を紹介します。
調査の目的や相手の情報の有無によって、適切な手段を選ぶことが大切です。
4.1 インターネットでの調査
財産調査の第一歩として活用しやすいのが、インターネット検索です。
債務者の名前や会社名を検索すれば、運営する事業のウェブサイト、提携先の情報、行政から受けた補助金の記録など、公開情報から収入や資産の手がかりを得られることがあります。
また、裁判所の公開情報や官報、SNSなども、訴訟歴や破産履歴、生活状況などを把握する材料になります。
ただし、ネット上の情報は正確とは限りませんし、最新でない場合もあります。
簡易的な調査として利用しつつ、裏付けは別の方法で取るのが安全です。
4.2 役所への照会
法務局や市区町村役場などの行政機関を通じて取得できる公的情報も、財産調査の有力な手段です。
法務局では、不動産登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得することができ、特定の不動産については、誰でもその所有者や権利関係を確認することが可能です。
登記簿には、不動産の所在や地目、面積、所有者の氏名、抵当権などの担保設定の有無といった情報が記載されており、差押えの可否や実行可能性を判断するうえで重要な資料となります。
なお、氏名や住所だけでは不動産の所有状況を一括して調べることはできないため、対象となる不動産の所在地(地番)を特定したうえで調査を進める必要があります。
一方、住民票や戸籍附票は、債務者の現住所や転居履歴を確認できる重要な資料ですが、個人情報保護の観点から、原則として第三者は取得できません。債権者がこれらを取得するには、弁護士や裁判所を通じて手続きを行う必要があります。
4.3 関係者へのヒアリング
債務者本人が情報開示に応じない場合でも、家族や勤務先、取引先などの関係者から間接的な情報を得られることがあります。
たとえば、債務者がどの会社で働いているか、どこに住んでいるか、どのような生活をしているかといった情報は、勤務先の担当者や近隣住民などを通じて把握できることがあります。
しかし、こうした聞き取りは慎重に行わなければなりません。
不適切な方法で調査を行えば、名誉毀損やプライバシー侵害として法的トラブルに発展するおそれがあります。
そのため、このような調査は弁護士に相談したうえで、法的に問題のない範囲で進めるのが望ましいといえます。
4.4 調査会社による調査
探偵業などの調査会社に依頼することで、債務者の資産状況や生活実態に関する情報を収集することもできます。
依頼の内容によっては、勤務先、居住形態、車両や不動産の使用状況、経済活動の傾向など、幅広い情報が得られる可能性があります。
調査会社には、法律の範囲内での調査が義務付けられており、違法な手段での調査を行う業者に依頼してしまうと、債権者側も法的責任を問われるおそれがあります。
費用については数万円~百万円程度までさまざまであり、依頼前に目的・調査範囲・報告内容を明確にして契約することが重要です。
4.5 弁護士による調査
弁護士に依頼すれば、一般の人では取得できない情報も、法的な制度を活用して入手することが可能です。
もっとも広く使われているのが「弁護士会照会制度」です。
これは、弁護士が職務上必要と認めた場合に、官公庁や金融機関、企業などに対し、債務者に関する情報を開示するよう求める手続きです。
この制度を使えば、預貯金口座の有無、勤務先、保険契約などの情報を得られる場合があります。
さらに、民事執行法に基づく「第三者からの情報取得手続」を利用すれば、裁判所を通じて年金機構、金融機関、自治体などから正式に情報提供を受けることができます。
また、判決や公正証書を取得した後には、債務者本人に財産の内容を明らかにさせる「財産開示手続」を申し立てることもできます。
この手続で虚偽の説明をしたり黙秘したりすると、刑事罰の対象になるため、正確な情報を引き出せる可能性が高まります。
これらの法的手続は、正当な手順で強制執行につなげるうえで非常に有効な手段であり、回収の実効性を高める大きな武器となります。

5. 各財産を調査する具体的な方法
債務者の保有財産にはさまざまな種類があります。
差押えや交渉の準備として、対象となる財産ごとにどのように調査を進めるのかを理解しておくことは、債権回収の成功に直結します。
ここでは、債権回収の現場で頻繁に調査対象となる主要な財産について、調査の進め方を解説します。
5.1 不動産の調査
不動産の保有状況を調べるには、法務局で登記簿(登記事項証明書)を取得する方法が一般的です。
登記簿には、土地や建物の場所、種類、面積、所有者の氏名・住所、過去の売買や抵当権の設定など、権利に関する詳しい情報が記録されています。
これらの情報は、地番さえ分かれば、第三者でも取得することができ、誰でも閲覧可能です。
ただし、注意が必要なのは、登記上の住所表記が「住居表示(◯丁目◯番◯号)」ではなく、「所在」と「地番」で記されていることです。
そのため、実際に見えている住所から地番を特定したい場合は、法務局で備え付けられている「ブルーマップ(住宅地図)」を活用し、住居表示と地番の対応関係を確認する必要があります。
また、現時点で不動産が確認できなくても、過去の登記記録や権利移転の流れを丁寧に追うことで、差押え可能な資産を発見できる場合があります。
そのため、不動産の調査は早い段階で行い、必要に応じて弁護士の協力を得ながら進めていくことをおすすめします。
5.2 預貯金の調査
預貯金は差押えの対象として非常に有効ですが、銀行口座の情報は通常非公開であるため、調査には特別な手続きが必要です。
債権者自身が金融機関に直接問い合わせても、取引の有無や残高を教えてもらうことはできません。
こうした場合には、民事執行法に基づく「第三者からの情報取得手続」を利用します。
この制度を使うと、裁判所の許可を得たうえで、債務者がどの銀行に口座を持っているか、どの支店か、給与の振込先はどこかといった情報を、銀行側から正式に開示してもらうことが可能になります。
さらに、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会制度」を使って、特定の金融機関に照会をかけることもできます。
この照会を通じて、債務者名義の口座の有無や、口座の種類、支店情報などを確認できる場合があります。
ただし、これらの手続を利用するには、ある程度の手がかり(振込先として使われていた銀行名や、以前の請求書に記載されていた取引銀行など)がないと、調査が困難になるケースもあります。
たとえば、金融機関の範囲がまったく絞り込めていない場合には、広範囲に調査をかけることは現実的ではないため、事前の情報収集が重要です。
5.3 売掛金の調査
債務者が取引先から代金を受け取る権利、つまり「売掛金」も差押えの対象になります。
このような売掛債権を把握できれば、債務者に代わって第三者(=取引先)から支払いを受ける形で、間接的に回収を図ることが可能です。
売掛金の存在を調べるには、まず債務者の事業内容や業種、取引先に関する情報を集めることから始めます。
会社ホームページ、決算報告書、公開されている取引先リスト、SNSや業界誌の記事など、複数の情報源をあわせて債務者と他社との取引関係を推測します。
できれば、請求書や納品書などの書類を入手すると、取引額や支払期日なども明確になります。
売掛金の差押えを行うには、第三債務者(=取引先)の名称・所在地などが特定できている必要があります。
そのうえで、裁判所に差押命令を申し立て、取引先に対して「今後の支払いは裁判所経由で行ってください」という命令を出すことになります。
差押えが認められると、取引先からの入金を通じて間接的に債権を回収できます。
5.4 給料や役員報酬の調査
債務者が勤務している会社から受け取る給料や役員報酬も、法的な手続きを通じて差押えることができます。
継続的な収入源であるため、長期的な回収を視野に入れた対応が可能となるのが特徴です。
まずは、債務者の勤務先を特定する必要があります。
SNSの投稿内容や名刺、請求書、納税記録、住民税の特別徴収先などが、勤務先を推測するヒントになります。
住所と職場が一致することもあるため、登記簿や電話帳を利用して調べることもあります。
勤務先が判明した場合には、裁判所に対して差押命令の申立てを行い、債務者の給与に対して差押えの効力を及ぼすことが可能になります。
ただし、差押え可能な金額には上限があり、法律上「ある程度以下の収入の場合には手取り額の4分の1まで」などといった制限が設けられています。
役員報酬についても同様で、法人登記簿や有価証券報告書などから取締役の氏名や報酬の概算が把握できる場合があります。
ただし、会社経営者や役員の報酬は「事実上の裁量」が広いため、報酬が意図的に減額されている場合もあり、実際の回収が難しいこともあります。
6. 弁護士による財産調査サポート
財産調査は専門的な手続きや判断が必要になる場面が多く、弁護士のサポートを受けることで、調査の精度と実効性が大きく向上します。
ここでは、弁護士が提供できる代表的な財産調査の支援内容について解説します。
6.1 全体的な債権回収や調査の戦略の立案
弁護士に依頼することで、単なる財産調査にとどまらず、債権回収全体の戦略を設計してもらうことができます。
相手の支払能力、回収にかかる時間や費用、法的手続の有無などを総合的に判断し、「どの財産を、どの順番で、どの手段で狙うべきか」といった具体的な方針を立てることが可能です。
また、交渉での解決を目指すか、訴訟や強制執行に踏み切るかといった判断についても、リスクと費用対効果のバランスを見ながら提案を受けられます。
調査に加えて、法的措置の実行支援も含めて一貫して対応してくれるのが弁護士に依頼する大きなメリットです。
6.2 弁護士会照会
弁護士は弁護士法に基づき、必要に応じて官公庁や金融機関、企業などに対して情報開示を求める「弁護士会照会制度」を利用できます。
この制度を使うことで、債務者の勤務先、預貯金口座の有無、保険契約の有無など、個人では得られない情報にアクセスできる可能性があります。
たとえば、給与差押えを行う前提として勤務先を確認したい場合や、差押え対象の金融機関を特定したい場合など、実務上重要な局面で大きな効果を発揮します。
この照会は弁護士が職務上の必要性を示し、所定の手続を経て行われます。
6.3 民事執行法に基づく第三者からの情報取得手続き
債権者が裁判所の許可を得たうえで、第三者(銀行、年金機構、市区町村など)から債務者の財産に関する情報を取得できます。
たとえば、銀行に対して「債務者の口座がどの支店にあるか」や、「年金を受け取っているか」といった情報を求めることができます。
この制度のメリットは、強制執行に必要な情報を法的に取得できる点にあります。事前に弁護士が申立書類を作成し、裁判所に申し立てを行う必要がありますが、正規の手段で確実な情報が得られるため、執行手続きの準備がスムーズになります。
6.4民事執行法に基づく財産開示手続き
財産開示手続きとは、債務者本人に対して、裁判所で財産の内容を正直に述べるよう命じる制度です。これは、既に「債務名義」と呼ばれる公的な文書を取得していることが前提となります。
債務名義の例をいくつかご紹介します。
- 裁判所の確定判決(例:貸金返還請求訴訟で勝訴した判決)
- 仮執行宣言付きの判決や和解調書
- 調停調書(民事調停で成立した支払合意など)
- 支払督促が確定したもの
- 金銭債務の支払を約束した公正証書(例:公証役場で作成した養育費支払契約書など)
このような債務名義に基づいて、財産開示手続を申し立てることで、債務者に対して「どのような財産を保有しているのか」を裁判所で明らかにさせることができます。
期日に正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の説明をしたりした場合には、刑事罰の対象になる場合もあります。そのため、心理的な圧力も大きく、債務者にとっては無視しにくい制度となっています。
開示された情報をもとに、不動産、預金、給料などに対する差押えの検討を進めることができるため、強制執行の準備として非常に有効な手段です。
この手続きも、弁護士のサポートを受けることで、申立書の作成、必要書類の収集、裁判所とのやり取りまで安心して任せることができます。
7. 財産調査に関するよくある質問
ここでは、実際に財産調査に関してよく寄せられる質問の中から、特に重要な2つについて解説します。
7.1 どの程度の費用がかかるのか?
財産調査にかかる費用は、調査の方法や範囲、依頼先によって大きく異なります。
たとえば、自分で法務局に出向いて不動産の登記簿を取得する場合には、1通あたり数百円〜600円程度の手数料で済みます。
しかし、弁護士や調査会社に依頼して調査や証拠収集を行う場合には、10万円から30万円程度かかることもあります。
民事執行法に基づく「第三者からの情報取得手続」や「財産開示手続」では、裁判所に対する申立費用として印紙代や郵便切手代などの実費(数千円程度)に加え、弁護士費用(着手金・報酬など)が別途発生します。
費用を抑えたい場合には、まず自分でできる範囲の調査から始め、必要に応じて弁護士へ依頼するという段階的な進め方も検討できます。
ただし、調査が不十分なまま法的手続に進むと、かえって無駄な費用がかかるおそれもあるため、費用対効果を弁護士に相談しながら進めるのが安心です。
7.2 調査期間はどれくらい必要か?
財産調査にかかる時間は、調査の内容や手続の種類によって異なります。
法務局で不動産の登記簿を取得する程度の簡易な調査であれば、当日中に完了することもあります。
一方、弁護士を通じて行う「弁護士会照会」や「情報取得手続」「財産開示手続」などは、準備から結果が出るまでに数週間〜数か月かかることもあります。
たとえば、情報取得手続では、裁判所に対する申立書の作成・提出、審査、許可決定、照会先機関からの回答の到着まで含めると、平均で1〜2か月程度かかるのが一般的です。
照会先が官公庁や大手金融機関などである場合は、回答に時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
また、調査内容によっては、対象となる財産の存在を裏付ける資料を集めるための事前調査期間も考慮する必要があります。
調査内容によって調査期間は異なります。正確な情報を得るためにも、弁護士と連携しながらスムーズに進めることが、全体の調査期間を短縮するポイントになります。
8. 債権回収での財産調査は弁護士へ相談を
取引先や顧客からの支払いが滞ったとき、「本当に回収できるのか」「どこまで調査すべきか」と悩むことは少なくありません。
財産調査は、単に情報を集めるだけでなく、その後の差押えや交渉、訴訟などの法的対応につなげる前提となる、非常に重要なプロセスです。
しかし、調査方法を間違えたり、法律に違反する形で情報を集めてしまったりすると、相手方との新たなトラブルに発展する恐れもあります。
円滑で実効性のある債権回収を実現するためにも、まずは信頼できる弁護士に早めに相談し、方針を立てるところから始めることをおすすめします。