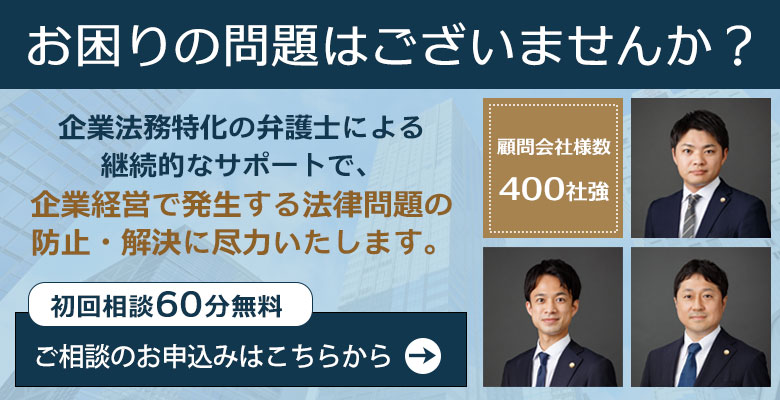仮差押は、取引先が支払いを滞納している場合などに、債務者の財産を保全しておくための重要な手続きです。
「裁判で勝訴したのに、相手の財産がなくなっていた。」という最悪の事態を防ぐため、裁判前に財産を押さえておくことで、債権回収の成功率を高めることができます。
しかし、仮差押は簡単な手続きではなく、申立書の作成や証拠書類の準備、担保金の供託など、慎重な対応が求められます。
また、費用面や手続きの流れを正しく理解しておかないと、思わぬトラブルになることもあります。
本記事では、債権回収を検討している方に向けて、仮差押の基本からメリット・デメリット、具体的な手続きの流れまで、弁護士がわかりやすく解説します。
相手方に財産を隠されるリスクを回避し、確実な回収を目指すために、ぜひご活用ください。
目次
1. 仮差押とは?
仮差押は、債権者が裁判で権利を確定させる前に、債務者の財産を保全するための手続きです。
簡単に言えば、相手が持つ不動産や預金などの財産を、勝手に処分できないように一時的に押さえる措置です。
たとえば、A社がB社に対して売掛金の支払いを請求しているとします。
B社の経営が悪化し、資産を売却して資金を引き上げようとする場合、A社が裁判で勝っても、B社に財産が残っていなければ債権の回収は困難です。
このようなリスクを回避するため、A社は仮差押を申し立て、裁判が終わるまでB社の財産を保全します。
このように仮差押は、将来的な債権回収を確実にするための「保険」として機能します。
1.1 仮差押でできること
仮差押が認められると、債務者は対象となった財産を自由に処分できなくなります。
これにより、債権者は債務者の財産の減少を防ぎ、最終的な回収の見通しを確保できます。
ただし、仮差押は債権を実際に回収する手段ではなく、「債権を守るための一時的な措置」です。
債権を実現するためには、別途裁判を行い、勝訴判決を得る必要があります。
一方で、たとえば不動産が仮差押の対象になっている場合、事実上債務者はその不動産を売却することは困難です。
最終的に債権者が裁判で勝訴すれば、強制執行を行い、債権回収を図ることができます。
これが仮差押の大きな特徴です。
さらに、仮差押は債務者にとって大きな心理的負担となるため、任意の支払いを促す効果も期待できます。
1.2 仮差押の要件
仮差押を申し立てる際には、一定の条件を満たしている必要があります。
大きく分けて「債権の存在」と「保全の必要性」の2つです。
① 債権の存在(被保全権利)
仮差押を利用するためには、まず債権者が「金銭を請求できる権利」を持っていることが必要です。
たとえば、貸付金、売掛金などの権利を持っていることが必要です。
② 保全の必要性
保全の必要性とは、正式な裁判の判決を得るまでに権利の実現が困難になったり、著しい損害や急迫の危険が生じたりするのを避けるため、暫定的な保護を与える必要性を指します。
たとえば、不動産以外に債務者に財産がなく、しかも債務者が事業を止めて不動産を売却しようとしている場合には、保全の必要性があるという判断になりやすいでしょう。
なお、仮差押の申し立てには「証明」ではなく「疎明(そめい)」が求められます。
疎明とは、裁判所が「おそらくこの債権は本当にあるだろう」と思える程度の資料を示すことを指します。
厳密な証拠は不要で、あくまで迅速な手続きを重視する制度です。
1.3 仮差押できる財産
仮差押の対象となる財産は、大きく分けて「不動産」「動産」「債権」の3つに分類されます。
それぞれの特徴を理解しておきましょう。
① 不動産
債務者が土地や建物などの不動産を所有している場合、その不動産を仮差押えすることで、債務者は理屈上自由に売却や担保設定はできますが、買主や担保権者は仮差押の効力を引き継ぐことになります。
仮差押えされると、法務局に仮差押登記が記録され、第三者がその事実を確認できる状態になります。
そのため、最終的に債権者が裁判で勝訴した場合は、たとえ不動産が売却されていたとしても、その不動産に対して強制執行を行うことが可能です。
競売によって得た代金から債権を回収できます。
不動産は価値が安定しており、また登記で保全できるため、仮差押えの対象として非常に有効な資産と言えます。
② 動産
動産とは、自動車、機械設備、宝石、貴金属など、持ち運び可能な財産を指します。
動産を仮差押すると、債務者はその財産を自由に処分できなくなります。
実際の手続きでは、仮差押した動産を物理的に管理下に置く必要があり、保管のコストや管理の負担が発生することがあります。
裁判で勝訴した後は、仮差押していた動産を競売にかけ、その売却代金から債権を回収できます。
ただし、動産は不動産と比べて価値が変動しやすいことを留意しておきましょう。
③ 債権
債権とは、債務者が第三者に対して持っている「お金を請求できる権利」のことです。
たとえば、預貯金、売掛金、賃料債権などがこれにあたります。
債権を仮差押えすると、対象となる債権については支払いが禁止され、債務者は自由にその権利を行使できなくなります。
たとえば、銀行預金が仮差押えされると、銀行がその口座の出金等を停止する(いわゆる凍結される)ため、債務者は預金を引き出すことができません。
裁判で勝訴した後は、仮差押していた債権を正式に差し押さえ、強制的に金銭を回収できます。
たとえば、預金口座なら銀行に命令を出して、そこから直接金銭を取り立てることが可能です。

2. 仮差押を利用するメリット
仮差押は、債権を確実に回収するための有力な手段です。財産隠しを防ぐだけでなく、交渉の場面でも強い効果を発揮します。
ここでは、仮差押を利用する主なメリットを解説します。
2.1 財産隠しを防止したり回収リスクを軽減
仮差押の最大のメリットは、債務者が財産を隠したり処分したりするのを防げる点です。
たとえば、預金が仮差押えの対象となった場合は、銀行がその口座の支払いを禁止するため、債務者は自由に引き出すことができなくなり、実務上は「口座が凍結される」状態になります。
これにより、債権者は預金が減少するリスクを防ぎ、勝訴後に預金を差し押さえて回収できます。
一方、不動産が仮差押えの対象となった場合は、法務局に仮差押登記が記録されます。
債務者はその不動産を売却すること自体は理屈上可能ですが、仮差押登記が付いた状態のまま引き継がれるため、購入者は後に競売などで権利を失うリスクを負います。
つまり、仮差押登記があることで、不動産の価値や流動性が大きく下がり、債権者は裁判で勝訴した際にその不動産を競売にかけて回収できる仕組みです。
2.2 交渉や訴訟を有利に進行
仮差押は、単に財産を押さえるだけでなく、交渉や訴訟の進め方にも大きな影響を与えます。
たとえば、債務者が所有する不動産を仮差押した場合、債務者は第三者に売却できる可能性はありますが、最終的には強制執行で取り戻せます。
このため、債権者としては安心して交渉を進めることができます。
さらに、仮差押がかかると債務者側は心理的な負担が増すため、和解や支払いに応じるケースが増えるのも特徴です。
訴訟を有利に進める「圧力」として機能するのが、仮差押の大きな強みです。
2.3 迅速な手続き
仮差押は、通常の裁判よりもスピード感のある手続きです。
裁判が長引いている間に財産が処分されると意味がないため、裁判所は仮差押の申立てを迅速に審理する傾向があります。
また、仮差押が発令されると、債務者はただちに影響を受けるため、解決への動きも早まることが多いです。
特に、不動産や預金などが対象の場合は、信用問題にも関わるため、債務者側から積極的に和解を持ちかけてくるケースも見られます。
3. 仮差押を利用するデメリット
一方で、仮差押には、いくつかのデメリットもあります。
ここでは、実際に仮差押を検討する際に注意すべきポイントを整理します。
3.1 担保金が必要
仮差押を申し立てる際、裁判所の決定を得るためには担保金を供託する必要があります。
担保金は、債権額のおおよそ1〜3割程度が目安とされ、原則として現金で用意しなければなりません。
この担保金は、仮差押が取り消される場合や手続が終了するまでの間、裁判所に預けたままの状態になります。
そのため、資金繰りが厳しい債権者にとっては、大きな負担になることがあります。
特に、まとまった現金を準備できない場合、仮差押を断念せざるを得ないケースもあります。
3.2 弁護士費用が必要
仮差押を申し立てる場合、手続きが複雑であることから、弁護士に依頼することが一般的です。
そのため、申立手続きにかかる弁護士費用が発生します。費用は案件の内容や対象財産の規模によって異なりますが、通常は着手金と実費が必要です。
また、仮差押は迅速な対応が求められるため、短期間での対応を依頼する場合には追加費用がかかることもあります。
さらに、仮差押だけでなく、その後の訴訟も弁護士に依頼する場合は、別途訴訟費用が発生する点にも注意が必要です。
費用面での負担が想定以上になるケースもあるため、事前にしっかり見積りを取り、弁護士と費用の取り決めを明確にしておくことが大切です。
3.3 手続きが複雑
仮差押は、通常の裁判と比べて手続きが煩雑です。仮差押は原則として書類審査で進められます。そのため、提出する書類の正確性と説得力が非常に重要です。
さらに、仮差押は債務者の財産が失われる前に行わなければ意味がないため、スピードも求められます。
申立書の作成、必要資料の収集、保全の必要性を裏付ける書類など、すべてを短期間で整える必要があるため、法律に不慣れな方が自力で進めるのは難しいのが現実です。
4. 仮差押の手続きの流れ
仮差押を行うには、裁判所に対して正式な申立てを行い、担保金を納付する必要があります。
ここでは、裁判所の仮差押命令が出るまでの手続きの流れを解説します。
4.1 申立書作成と提出に必要な書類について
仮差押の手続きは、裁判所に「仮差押申立書」を提出するところから始まります。通常は、申立書を作成した上で裁判所に郵送または持参して提出します。弁護士に依頼している場合は、書類の作成や提出手続きは基本的に弁護士が対応します。
申立書の提出時には、次のような添付書類が必要です。
- 請求債権目録
- 仮差押対象の財産目録(債権の場合は「仮差押債権目録」、不動産の場合は「物件目録」)
- 債権が存在することを示す疎明資料(※1)
- 債権者が法人の場合:資格証明書
- 債務者が法人の場合:資格証明書
- 債務者の本店所在地の登記簿謄本
- 被保全権利や保全の必要性を説明する債権者の陳述書(※2)
- 弁護士に依頼している場合は委任状
※1 疎明資料の例
「疎明資料」とは、債権が存在することを裁判所に示すための書類です。次のようなものを用意します。
【契約書類】
売買代金の回収なら売買契約書、請負代金の回収なら請負契約書など。
【金額確認資料】
発注書と発注請書、債権額が明記された契約書、債務残高確認書、分割払いの合意書など。
※2 被保全権利や保全の必要性についての陳述書の例
「被保全権利や保全の必要性についての陳述書」とは、仮差押を行う必要性を裁判所に説明するための書類です。一般的には、次のような内容を記載します。
- 契約に至る経緯や契約後の経緯
- 債権の支払期限が過ぎており、未払いが続いていること
- 債務者に対して繰り返し督促を行っていること
- これまでの督促に対する債務者の反応
- 現在も支払いがされていない状況
- 債務者の資金繰りが悪化している兆しがある場合は、その具体的な事情
- このままでは、訴訟で勝っても財産がなくなり、債権を回収できなくなるおそれがあること
この陳述書は、弁護士が依頼者から事実関係を聞き取ったうえで作成の下書きを行い、最終的に依頼者が確認・署名して完成させるのが一般的です。
4.2 担保金の納付と裁判所の発令
申立てが受理されると、裁判所による審理が行われ、その後、担保金の供託を経て、最終的に仮差押命令が発令されます。
① 裁判所の審理
審理では、債権者が提出した申立書や疎明資料(契約書・債務残高確認書など)をもとに、債権や回収リスクの有無を裁判所が確認します。
保全の必要性については、債務者の財産が失われる恐れがあるかを中心に判断されます。
ここで資料が不十分と判断されれば、裁判官から追加資料の提出を求められることもあります。
② 担保金の供託
審理が終わり、裁判所が仮差押を認める方向で判断すると、債権者には担保金の供託が求められます。
これは、万が一仮差押が不当だった場合に備えるための保証金で、通常は債権額の10〜30%程度が相場です。
担保金は、現金で法務局に供託するのが基本ですが、裁判所の許可を得れば銀行保証書などで代替することも可能です。供託が完了したら、供託書の正本とその写しを裁判所に提出する必要があります。
担保金は通常、裁判所から通知を受けてから7日以内に供託しなければならないため、あらかじめ資金を準備しておくことが大切です。
③ 仮差押の決定と発令
担保金が供託されると、裁判所は正式に「仮差押命令」を発令します。
債権者はその決定正本を受け取り、次の段階として実際の執行手続きに移ることができます。仮差押が発令されると、債務者の財産は法的に保全され、勝訴後の回収が現実的なものとなります。

5. 仮差押後の流れ:訴訟提起や和解
仮差押が発令された後も、債権を回収するためには追加の手続きが必要です。
ここでは、仮差押後の基本的な流れとして「訴訟提起」と「和解」の二つのパターンを解説します。
5.1 訴訟提起後の流れ
仮差押を行っただけでは、債権を最終的に回収することはできません。そのため、債権者は速やかに債務者を被告とする訴訟を提起する必要があります。
もし仮差押後に訴訟を起こさずに放置していると、債務者から「起訴命令の申立て」が行われることがあります。裁判所はその申立てを受け、債権者に対して一定の期限内に訴訟を提起するよう命じます。また、訴訟を提起した場合は、その証明書類を裁判所に提出しなければなりません。
債権者がこの命令に従わなかった場合、債務者の申立てにより、すでに出ている仮差押命令が取り消されてしまいます。したがって、仮差押後は速やかに訴訟を進めることが非常に重要です。
訴訟で勝訴した後は、仮差押した財産に対して「本執行(強制執行)」の申立てを行い、正式な回収手続きに入ります。
ここで初めて、仮差押した財産を競売などで換価し、債権を実際に回収することが可能となります。
5.2 和解の流れ
仮差押は、債務者にとって大きなプレッシャーになります。そのため、仮差押が行われた段階で、債務者から和解を持ちかけてくるケースも少なくありません。
特に、仮差押の対象が不動産や預金口座の場合、信用問題に発展することを恐れて、早期解決を希望する債務者が多い傾向にあります。
和解が成立すれば、訴訟を続行する必要がなくなり、解決までの時間や費用も抑えられます。
和解内容としては、分割払いの合意や一括での債務弁済が典型的です。
和解が成立した場合は、仮差押の取下げも検討することになりますが、弁護士と相談しながら慎重に判断することをおすすめします。
6. 仮差押にかかる費用と担保金の相場
仮差押を検討する際には、費用面も重要なポイントです。ここでは、仮差押に必要な費用の内訳と、担保金や弁護士費用の相場について解説します。
6.1 担保金の算定基準
仮差押で最も大きな費用負担となるのが「担保金」です。担保金は、債務者の財産を仮差押する際に万が一不当な損害が発生した場合に備え、債権者があらかじめ裁判所に納める保証金のことです。
担保金の金額は、請求する債権額や対象となる財産の種類によって決まります。一般的な目安は次の通りです。
- 不動産仮差押: 請求額の約10~20%
- 債権仮差押(預貯金など): 請求額の約20~30%
たとえば、1,000万円の債権を仮差押する場合、200万円前後の担保金が必要になることもあります。担保金は、裁判所が提出資料の信頼性や仮差押の影響などを総合的に判断して決定します。
6.2 担保金の返金の有無及び時期
担保金はあくまで「保証金」であり、仮差押が不当だった場合や損害賠償請求が発生した場合を除き、通常はそのまま返還されます。
債権者が訴訟に勝訴した場合、判決確定後に「担保取消」の申立てを行うことで返金されますが、返還にはおおむね1カ月ほどかかるのが一般的です。
一方、万が一敗訴した場合は、担保金に関する「権利行使催告」の手続きを経て、相手方が損害賠償を請求するかどうかを確認する必要があります。この場合は、返還までに2~3カ月程度かかることもあります。
実際には、担保金が没収されるケースは非常にまれで、ほとんどのケースで返還されますが、返還までの期間が長くなるため、資金繰りへの影響も考慮しておくことが重要です。
6.3 弁護士費用その他実費の目安
仮差押を弁護士に依頼する際は、弁護士費用が必要です。目安は次の通りです。
仮差押のみ依頼する場合の着手金
20万~50万円程度
債権回収全体を依頼する場合の着手金
請求額の5~10%程度(例:1000万円の債権で50~100万円程度)
報酬金
回収額の10%~20%程度
その他費用
仮差押を申し立てる際には、次のような実費も発生します。
- 収入印紙代:2000円
- 予納郵便切手代:債権仮差押は約3000円、不動産仮差押は約2000円
※郵便切手は裁判所ごとに組み合わせが異なるため、事前に確認が必要です。
また、不動産の仮差押では登記が必要になるため、登録免許税(請求額の0.4%)も別途かかります。
7. 仮差押手続きで押さえておきたいポイント
仮差押はスピードが重視される手続きですが、その一方で成功させるためには事前準備が極めて重要です。ここでは、特に押さえておきたい2つのポイントを紹介します。
7.1 客観的な証拠の確保が重要
仮差押を申し立てる際は、「債権が存在していること」を裁判所に示す必要があります。
その際、求められるのは客観的な証拠です。
たとえば売掛金の請求であれば、売買契約書、請求書、発注書、受領書などが有力な資料になります。
また、裁判所は「疎明基準」で審査を行いますが、これは完全な証明を求めるものではなく、「おそらく債権が存在するだろう」と裁判所が判断できる程度の資料で足りるとされています。
とはいえ、証拠が不十分だと申立てが却下される可能性もあるため、できるだけ多くの客観的資料をそろえておくことが大切です。
7.2 相手方の財産の把握が必要
仮差押は、対象とする財産が特定されてはじめて実効性が出ます。
どの財産を押さえるかがあいまいなままだと、せっかく仮差押が認められても執行が困難になります。
たとえば預貯金を仮差押したい場合は、相手方の取引銀行や支店まで特定しておく必要があります。
不動産なら、所在地や登記簿情報を正確に把握しておきましょう。
裁判所が職権で財産を調査してくれることはありません。そのため、債権者自身があらかじめ相手方の財産情報を収集しておくことが不可欠です。
必要に応じて、不動産登記簿や商業登記簿、取引先情報などから情報を得るとよいでしょう。
8. 仮差押に関するよくあるご質問
ここでは、仮差押の手続きについて実務上よく寄せられるご質問にお答えします。
8.1 申立から発令までの期間は?
仮差押の申立てから決定が出るまでの期間は、全ての書類がそろっていて順調に進んだ場合は2日から5日程度が目安です。
ただし、書類に不備があったり、追加資料が必要になったりする場合は、手続きが長引くこともあります。
申立の準備段階で、必要書類を過不足なく整えておくことが、スムーズな進行のカギとなります。
8.2 相手方の財産がわからない場合もできますか?
仮差押を申し立てる際、原則として債務者の財産を特定する必要があります。
とくに預貯金の仮差押を希望する場合は、銀行名・支店名まで明確に記載しなければ、執行はできません。
不動産についても、所在地や登記事項が求められます。
一方、動産の仮差押については、財産の特定がある程度曖昧でも申立が可能とされていますが、それでも裁判所が「保全の必要性」を判断するうえで、財産情報の詳細は重要な判断材料となります。
したがって、仮差押を検討する際は、相手方の財産を事前に把握しておくことが不可欠です。
8.3 仮差押と本差押(強制執行)の違いは?
仮差押と本差押(いわゆる強制執行)は、いずれも債務者の財産を差し押さえる手続きですが、その目的と性質には大きな違いがあります。
目的
- 仮差押:財産を処分・隠匿されないよう防ぐ(債権の保全)
- 本差押:財産を差押し、売却して回収する(債権の実現)
根拠法
手続きの性質
- 仮差押:迅速・簡易。債務名義は不要
- 本差押:厳格な審査。債務名義(判決など)が必要
財産の処分
- 仮差押:債務者の処分を禁止するだけで、換価はできない
- 本差押:差押財産を売却して、回収資金に充てられる
優先権
- 仮差押:原則として優先権なし
- 本差押:原則として優先権あり
債務名義の要否
- 仮差押:不要
- 本差押:必要
仮差押と本差押(強制執行)の違いのまとめ
仮差押はあくまで「債権を守るための一時的な措置」であり、本執行(本差押)は「実際にお金を回収する段階」です。
仮差押だけでは債権回収は完了しないため、その後の訴訟と強制執行まで視野に入れる必要があります。
9. 仮差押は弁護士へ相談を
仮差押は、債権回収を確実に進めるための強力な手段ですが、手続きが複雑で、慎重な判断が求められる場面も多くあります。
特に、申立書の作成、証拠資料の収集、財産の特定、担保金の納付など、いずれも専門的な知識と迅速な対応が必要です。
また、裁判所とのやり取りや審理の進め方によって、手続きがスムーズに進むかどうかも大きく変わってきます。
債権者が自身で対応するのはハードルが高いため、仮差押を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
仮差押に詳しい弁護士であれば、債権回収全体の見通しや、費用・リスクの説明も含めてアドバイスを受けることができます。
まずは無料相談などを活用して、自社の状況に合った最適な方法を見つけることが、安心・確実な債権回収への第一歩です。