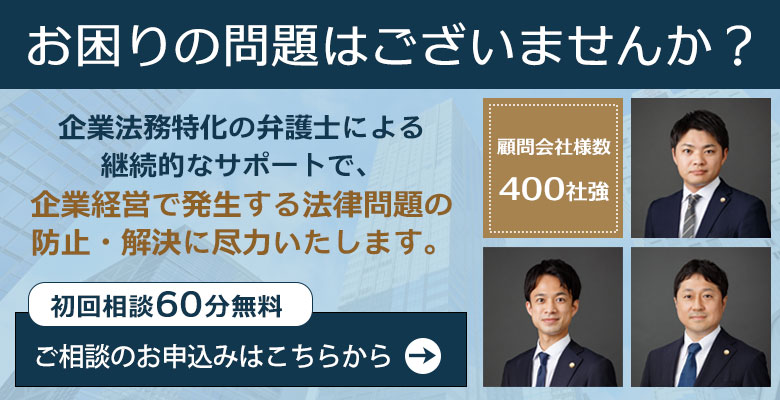「客の立場」を盾に、理不尽な要求や執拗な損害賠償請求を続ける、いわゆる「悪質クレーマー」への対応に、頭を悩ませている企業のご担当者も多いのではないでしょうか。
本来、顧客からのクレームには真摯な対応が求められます。しかし中には、「事実に反する主張」や「過剰な金銭要求」を繰り返し、業務に重大な支障をもたらす悪質なケースもあります。
さらに近年では、SNSや口コミサイトなどを利用して、企業に不当な損害賠償請求を突きつける悪質クレーマーの存在も問題となっています。企業として毅然とした対応をとらなければ、「応じればまた要求される」という悪循環に陥るおそれもあります。
この記事では、よつば総合法律事務所の企業法務に強い弁護士が、悪質クレーマーからの損害賠償請求にどう立ち向かうべきか、具体的な事例と対応方法をわかりやすく解説します。
目次
1. 悪質クレーマー対応は自社のみでの対応は難しい
1.1 担当者のみでの対応は危険
企業にとって顧客からのクレーム対応は日常業務の一部です。しかし、通常の苦情とは異なり、不当な要求を繰り返す「悪質クレーマー」への対応は、現場担当者だけで対処するには限界があります。
悪質クレーマーは、事実に反した主張を根拠に、法外な損害賠償を請求してくることがあります。明らかに商品やサービスに問題がないにもかかわらず、「精神的苦痛を受けた」として高額な慰謝料を求めてくるようなケースです。また、長時間の面談要求や繰り返しの電話、SNSでの企業名の拡散をほのめかす行動などが見られることもあります。
このような対応に、社内の担当者が個別に応じ続けると、精神的にも時間的にも大きな負担となります。対応を誤れば、企業側が本来支払う必要のない損害賠償金を支払ってしまうおそれもあり、経営面でも大きな損失につながりかねません。さらに、一度でも要求に応じてしまえば、「この企業は言えばお金を出す」と認識され、クレームがエスカレートする可能性もあります。
一部の悪質クレーマーは、「説明が不十分だった」「店員の態度が悪かった」といった、一見もっともらしい主張を混ぜて要求をしてくることがあります。
1.2 損害賠償の可否の判断は弁護士が必要
損害賠償請求が法律上認められるためには、次のような民法の要件を全て満たす必要があることが多いです。
- ① 違法な行為があること
- ② 損害が発生していること
- ③ その違法行為と損害に因果関係があること
- ④ 企業側に故意や過失があること
これらの要件の有無を判断するには、法的な知識と経験が不可欠です。
したがって、悪質クレーマーに対しては、社内での対応に限界があることを前提に、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が対応することで、法的に不当な要求であることを明確に伝えることができ、企業担当者が精神的圧力に屈することもなくなります。また、弁護士を窓口にすることで、企業側がクレーマーと直接やり取りする必要がなくなり、社内の業務にも支障が出にくくなります。

2. 悪質クレーマーからの損害賠償請求の具体例
悪質クレーマーによる損害賠償請求には、正当なクレームの域を超えた不当な要求が多数含まれています。企業がこれらに対し適切に判断・対応できなければ、不要な支払いをしてしまうリスクが高まります。
ここでは、企業が直面しやすい典型的な事例の一部を紹介します。
① 「精神的苦痛」を理由とした慰謝料請求
商品やサービスに明らかな不備がないにもかかわらず、「説明が不十分だった」「不快な対応を受けた」といった理由で、精神的苦痛に対する慰謝料として高額な金銭を求められるケースです。
② 繰り返しの来店・面談要求と金銭請求
企業の窓口や店舗に頻繁に来訪し、長時間の説明対応を求めながら、「誠意を見せてほしい」といった抽象的な言葉で金銭の支払いを促すような対応を強いるケースです。現場の担当者が精神的・時間的負担を抱える要因となり得ます。
③ 発言の録音・切り取りによる不当請求
担当者とのやりとりを録音・録画した上で、その一部分のみを取り出して「不適切な発言があった」などと主張し、名誉回復などを名目に金銭を求める形が取られることもあります。SNSなどで拡散すると脅された企業が、和解金を支払ってしまうケースもあります。
④ 名目を変えて繰り返される費用請求
交通費、相談費用、時間の損失など、複数の名目を挙げて、少額ずつ繰り返し支払いを求められるパターンも見られます。一度でも支払うと、「クレームに屈する企業」として見なされ、要求が続く原因になる可能性があります。
これらの請求は、いずれも法律上の損害賠償として認められるかどうかが疑わしいものばかりです。民法では、損害賠償の成立には、「違法行為」、「損害」、「因果関係」、「故意または過失」の4要件が必要とされていますが、多くのクレームはこれを満たしていません。
しかし、法的知識がないまま現場で個別に判断すると、本来支払う必要のない金銭を支払ってしまうおそれがあります。一度応じると、さらに要求が続く可能性も高くなります。
企業の信用や従業員の安全を守るためにも、悪質クレーマーによる損害賠償請求には、慎重かつ専門的な対応が求められます。
3. 弁護士が入った場合の対応
悪質クレーマーからの損害賠償請求に対し、企業が自ら対応を続けることには限界があります。不当な要求を拒みつつ、適切な対処を進めていくためには、弁護士の関与が極めて有効です。
弁護士が介入することで、クレーマーに対し「法的に正当な対応を行う」というメッセージを明確に伝えることができます。また、企業の担当者が直接やり取りをする必要がなくなるため、心理的負担や業務への悪影響も軽減されます。
弁護士が関与することで、次のような対応が可能になります。
3.1 弁護士を窓口とする交渉を行う
まずは、弁護士が企業の代理人として、クレーマーとの交渉の窓口となります。企業側の意向を踏まえつつ、法的観点から妥当な対応を行うことが可能となります。
悪質クレーマーの中には、法律的な根拠を欠いたまま「損害賠償を払え」と主張してくるケースが多くあります。こうした主張に対して、弁護士が適切に反論することで、クレーマーがそれ以上の主張を控える効果も期待できます。
また、弁護士を介することで、企業とクレーマーの間に一定の距離が生まれます。これにより、現場の担当者が繰り返しの連絡や面談を強いられることがなくなり、社内の負担軽減にもつながります。
クレーマーとの連絡手段や交渉内容も記録として残すことができ、万が一将来的に法的手続きが必要となった場合にも備えられます。
3.2 裁判所へ民事調停を起こす
交渉による解決が難しい場合には、簡易裁判所へ民事調停の申し立てを行うことも検討しましょう。調停とは、裁判官と調停委員の関与のもと、当事者間の話し合いによって円満な解決を目指す手続きです。
民事調停のメリットは、裁判に比べて手続きが比較的簡易で、費用や時間の負担も少ない点にあります。また、裁判よりも柔軟な解決が可能となるため、感情的な対立が激しいケースでは有効な手段となることがあります。
調停の場では、弁護士が企業の代理人として対応するため、主張の整理や証拠の提示も適切に行えます。不当な損害賠償請求であることを明確にした上で、第三者を交えた場での解決を図ることが可能です。
ただし、調停はあくまでも当事者間の合意による解決を目的とした手続きです。相手方が一方的な主張を繰り返したり、調停自体に応じなかったりする場合には、調停が成立せず終了となることもあります。
そのような場合には、次のステップとして訴訟の提起を検討します。
3.3 裁判所へ債務不存在確認訴訟を起こす
相手が交渉にも応じず、調停も不成立となった場合には、最終的に債務不存在確認訴訟を提起することが考えられます。
これは、企業側が原告となり、「相手方から請求されている金銭について、法的な支払義務がないこと」を裁判所に確認してもらう手続きです。企業が受け身で対応し続けるのではなく、積極的に法的措置を講じて立場を明確にするという意味で、重要な対応手段となります。
また、訴訟を通じて裁判所の判断が明らかになることで、企業としても今後の対応方針が立てやすくなります。さらに、判決内容を根拠として、他のクレームや風評被害への対応に活用できる場合もあります。
このように、債務不存在確認訴訟は、不当な請求に終止符を打つための有力な法的手段といえます。もちろん、訴訟は調停や交渉よりも手続きや費用の面で負担が増えますが、それでも「企業としての立場を明確にする」ためには、有効な選択肢となり得ます。

4. まとめ:悪質クレーマーからの損害賠償請求への対応は弁護士へ
悪質クレーマーからの損害賠償請求には、法的根拠のない不当な要求が含まれていることが少なくありません。企業がこうした請求に対して適切な判断や対応を行わなければ、不必要な支払いをしてしまったり、同様の請求が繰り返されたりするリスクがあります。
また、企業の担当者がクレーマーと直接やり取りを続けることは、心理的な負担だけでなく、現場業務への支障や他の従業員への悪影響にもつながります。一件一件は小さな対応であっても、放置することでエスカレートし、組織全体にとって深刻なリスクとなり得ます。
こうした問題に対しては、早期の段階で弁護士に相談し、法的観点からの助言と対応を得ることが重要です。弁護士が窓口となることで、直接の接触を断ち、交渉の方針や書面のやり取りも法的に整備された形で進めることが可能となります。
また、交渉が難しい場合は、民事調停や訴訟などの正式な法的手続きによって、企業の立場を明確にすることができます。とくに債務不存在確認訴訟は、「支払義務がないこと」を裁判所に確認してもらうことで、以後の同様の請求を防止する強力な手段となります。
よつば総合法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が、悪質クレーマー対応に関する実践的なサポートを提供しています。クレーマーからの不当な損害賠償請求にお悩みの企業様は、まずはお気軽にご相談ください。法的な根拠に基づいた、冷静かつ確実な対応をご提案いたします。