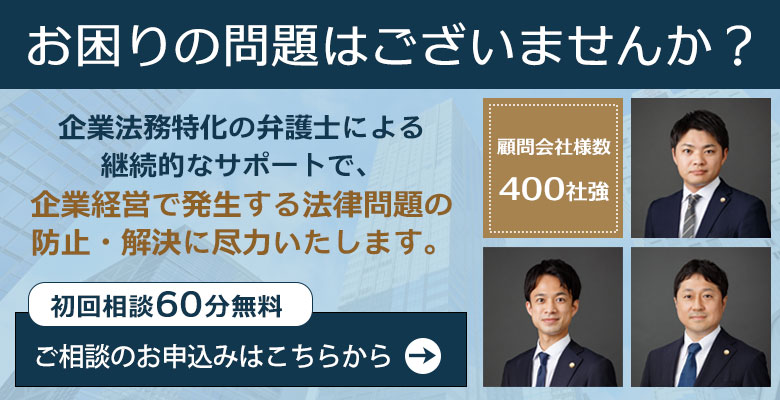「顧客対応を誤ったことで、SNSでの批判が拡散し、風評被害に発展してしまった。」
「連日続くクレーム対応で、ついに社員のメンタルが限界に達してしまった。」
このようなご相談は、私たち弁護士には多く寄せられています。
クレームは、どの企業にとっても避けては通れない問題です。特に中堅・中小企業においては、一つのクレーム対応の誤りが、経営リスクへと直結することも珍しくありません。
こうした事態を未然に防ぐためには、対応の基準を明文化した「クレーム対応マニュアル」を整備することが極めて重要です。
属人的・場当たり的な対応から脱却し、社内全体で対応方針を統一することで、顧客満足度の向上と従業員の心理的安全性の両立が実現できます。
本記事では、企業法務に詳しい弁護士が、中堅・中小企業がクレーム対応マニュアルを作成・運用する上で押さえておきたいポイントを、わかりやすく解説します。
目次
1. クレーム対応マニュアルの必要性
クレーム対応マニュアルは、中堅・中小企業にとって「トラブルの芽を摘む」ための重要な備えです。ベテラン社員が多い企業では、経験に頼って対応ができていたとしても、組織として安定した対応を実現するにはマニュアルの整備が欠かせません。
まず、マニュアルがあれば対応の均一化が図れます。担当者ごとの対応にばらつきがあると、顧客から「前と話が違う」と不信感を持たれたり、対応を誤った担当者がクレームを悪化させる原因になったりします。一方で、マニュアルに沿って対応すれば、仮に前回対応した担当者が不在でも、他のスタッフが同じ基準で対応でき、企業全体として一貫性のある姿勢を示せます。
また、近年では、クレームがSNSなどを通じて即座に拡散されるリスクもあり、対応のスピードも重要になっています。しかし、現場ではクレーマーからの大声や威圧的な態度により、若手社員が冷静な判断力を失ってしまうこともあります。マニュアルは、こうした混乱時における指針として機能します。
とくに新入社員や若手にとっては、経験不足から不安や動揺が生じやすいため、明確な対応手順が記されたマニュアルがあるだけで、精神的な負担を軽減でき、どんな場面でも落ち着いて行動できるようになります。これにより、離職の防止や人材の定着にもつながるでしょう。
さらに、マニュアルの存在は法的リスクの軽減にもつながります。たとえば、クレーム対応に失敗して損害賠償請求を受けた場合でも、「社内に対応マニュアルがあり、一定のプロセスを経て対応した」という事実は、企業の過失を否定または軽減する事情として考慮される可能性があります。何も対策を講じていない企業に比べ、マニュアルを整備・運用していた企業の方が、法的責任の回避や軽減に有利に働くケースは少なくありません。
このように、クレーム対応マニュアルは、対応の質とスピードを保つため、社員の安全と企業の信用を守るため、そして万が一の法的トラブルにも備えるために不可欠な仕組みといえます。

2. クレーム対応マニュアルに入れる内容
クレーム対応マニュアルを作成する際には、単に「丁寧に対応する」「上司に報告する」といった抽象的な表現では不十分です。現場の担当者が迷わずに行動できるよう、具体的な方針や手順を整理しておく必要があります。
ここでは、マニュアルに盛り込むべき主な項目について説明します。
2.1 クレームの定義
クレームとは、一般的に「顧客や取引先などのステークホルダーが、商品・サービス、対応、施設などに対して不満や不便を感じた際に、それを企業に対して申し立てる行為」を言います。ただし、企業活動における「クレーム」の意味は非常に広く、単なる不満の表明から、改善を目的とした建設的な苦情、さらには悪質な言いがかりに至るまで、内容や態様はさまざまです。
企業としては、まず「どのようなものがクレームに該当するのか」という定義を明確にしておく必要があります。これが曖昧なままだと、現場での初期対応に差が出たり、悪質な要求を安易に「お客様の声」として受け入れてしまう可能性もあります。
逆に、正当な意見や貴重なフィードバックを「単なるクレーム」として片付けてしまうと、顧客満足度の低下やブランド価値の毀損にもつながります。
そのため、クレーム対応マニュアルには、まず「それがどのようなクレームなのか」を分類できるよう、明確な判断基準を設け、対応の出発点を社内で統一しておくことが重要です。具体的には、次のような分類が参考になります。
- 正当な要求:製品の不良やサービスの遅延など、企業側に明らかな落ち度がある場合の申し出
- 建設的な意見:改善や提案を含んだ前向きなフィードバック
- 感情的な不満:対応が気に入らない、態度が冷たいといった主観的な不快感
- 悪質なクレーム:繰り返しの過剰要求、暴言、脅迫、金品の強要など
このように、クレームを内容や態度に応じて類型化することで、対応の優先度や方法を整理しやすくなります。特に、悪質なクレーマーに対しては毅然とした対応が求められる一方、正当な苦情に対しては誠意を持って迅速に対応することが顧客信頼を守るために不可欠です。
2.2 基本方針や姿勢の明確化
クレーム対応マニュアルの核となるのが「企業としての基本的な対応方針や姿勢」です。たとえ現場でマニュアルを開いて対応できる状況でなかったとしても、会社としてのスタンスが社内にしっかりと共有されていれば、従業員は落ち着いて対処できます。
クレームに対する基本方針としては、大きく以下の2点が挙げられます。
- ① 顧客に対しては誠実で丁寧な対応を心がけること
- ② 企業や従業員を不当に害するような要求や言動には毅然と対応すること
この2つのバランスをどう取るかが、クレーム対応の最も難しい点です。正当な苦情に対しては、企業の信頼回復の機会として真摯に受け止め、改善に活かすことが求められます。
一方で、暴言・脅迫・威圧的言動や不当な金銭要求など、いわゆる「悪質クレーム」については、過度に迎合せず、法的リスクも念頭に毅然とした態度で臨む必要があります。
この方針が明文化されていないと、現場では「お客様は神様だから」「とにかく謝れ」といった風潮が根強く残り、結果的に社員が過剰に委縮したり、不当な要求を受け入れてしまったりするリスクが高まります。こうした風土は、企業の持続可能性を損なう要因にもなりかねません。
また、企業としての姿勢を明確にすることは、現場社員の心理的安全性の確保にもつながります。クレーム対応は精神的な負担が大きく、特に新人や若手社員にとっては対応に失敗することへの不安がつきものです。しかし、会社としての考え方や優先順位が明文化されていれば、「どうすればよいかわからない」といった混乱を防ぎ、判断の軸を持って行動できるようになります。
具体的には、マニュアルの冒頭または序章部分に、次のような文章を記載することが考えられます。
「当社は、お客様からのご意見・ご要望には誠実に向き合い、より良い商品・サービスの提供に活かします。ただし、社員の安全・尊厳を損なうような不当な要求や違法行為には、毅然と対応します。」
このような文言を明示しておくことで、社内の判断基準が統一され、クレーム対応に対するブレが少なくなります。また、外部に対しても、企業の姿勢を明確にすることができます。
クレーム対応において重要なのは、すべてのクレームを「お客様の言い分だから」と受け入れることではありません。企業として守るべき信頼、社員の働く環境、そして法的な正当性を総合的に考慮したうえで、「受け入れるべき意見」と「拒絶すべき要求」を冷静に見極める姿勢こそが求められます。
2.3 苦情受付の体制の整備
クレーム対応マニュアルを有効に機能させるためには、そもそも苦情を「受け付ける」段階の体制を整備しておくことが欠かせません。適切な受付体制がなければ、どれほど立派なマニュアルを作成していても、現場で機能せず混乱を招いてしまいます。
まず前提として、企業に寄せられるクレームは、電話やメール、ウェブフォーム、SNSなど、さまざまな方法で寄せられるようになっています。したがって、苦情対応マニュアルにおいては、どこからのクレームであっても迅速かつ正確に受け止められる体制を整えておく必要があります。
特に電話でのクレーム対応は、第一声の受け答えがその後のトラブル拡大を防げるかどうかを左右するケースが多くあります。たとえば、「あいまいな態度」や「対応の属人化」が原因で、対応が後手に回り、相手の怒りをさらに増幅させてしまうといった事態が発生しがちです。
そのため、苦情の受付業務においては、次のようなポイントを明確にしておくことが重要です。
- ① クレーム受付の窓口(担当部門や担当者)をあらかじめ明確にしておく
- ② 誰が受付をしても、最初に何を聞き取り、どう引き継ぐかをマニュアルで統一する
- ③ 特定の担当者に業務が集中しすぎないよう、引き継ぎのルールやフローを整備する
- ④ 対応履歴や記録を残すためのシステム(Excel、CRM等)を活用する
たとえば、クレームを受け付けた際には、「いつ」「誰が」「どのような内容で」「どのような口調で」連絡を受けたのかを記録し、可能であれば音声やスクリーンショットなどの一次情報も保存しておくと、後々の対応でトラブルを未然に防ぎやすくなります。
また、属人的な対応にならないよう、基本的な初動の応対文言や、よくある質問に対する一次対応案などをテンプレートとしてまとめておくことも有効です。これは、新人社員やパート・アルバイトであっても、一定の水準で対応できる環境を整えるために役立ちます。
さらに、SNS経由でのクレームについても、対応部門や手順を定めておかないと、放置されたことで炎上に発展する可能性もあるため、リスク管理の一環として受付体制の中に組み込んでおくべきです。
このように、受付体制を整備することで、初期対応の精度が上がり、結果としてクレームの深刻化やエスカレーションを防ぐことができます。企業全体としての対応品質を高めるには、受付段階からの整備が不可欠といえるでしょう。
2.4 苦情対応の手順の確立
苦情対応に関しては、社内で共通の「対応手順(フロー)」もあらかじめ確立しておく必要があります。
特に、カスタマーハラスメントや悪質クレームの増加により、現場の判断にすべてを任せるのは危険な時代になっています。どのような状況でも、組織として一貫した判断と対応ができるよう、苦情処理の標準化は企業防衛の観点からも非常に重要です。
一般的には、以下の3ステップが苦情処理フローの基本になります。
2.4.1 ① 事実の確認
クレームの背景や内容、発言の詳細を時系列に整理し、事実関係を正確に把握します。顧客が何に不満を感じているのか、どのような要求をしているのかを明確にし、感情的な反応を避けて冷静に対応する姿勢が求められます。
カスタマーハラスメントの可能性がある場合には、さらに以下の2段階の検討が必要です。
- 要求内容が社会的に妥当かどうかを検討する
- 要求の手段(怒鳴る・脅すなど)が社会通念上、適正な範囲かどうかを判断する
これらを踏まえた上で、記録を取りながら、次のステップへ進みます。
2.4.2 ② 情報共有・全社的な対応
個人で対応できる範囲を超えていると判断された場合は、速やかに上司や法務部門などに報告し、組織全体で対応方針を検討します。ここで重要なのは「誰が」「どの段階で」上司に報告したり指示を仰いだりするのか、あらかじめ基準を明確にしておくことです。
さらに、法務・総務・カスタマーサービス部門などが連携し、社内的な視点から問題の重大性と対応の方向性を検討します。対応を複数の目でチェックすることで、感情的な判断ミスや対応漏れを防止できます。
2.4.3 ③ 再発防止に向けた取り組み
クレームの処理が完了した後は、関係部署で振り返りを行い、問題の背景や社内の改善点を洗い出します。再発防止策を策定・実行し、必要に応じてマニュアルや教育内容もアップデートします。
また、マニュアルには過去に寄せられたクレームの事例や対応記録も含めておくと、現場担当者が迅速に適切な対応をするための判断材料となります。
なお、クレーム発生時には必ず対応記録を残す仕組みを整えておくことも重要です。対応履歴があれば、万が一法的トラブルに発展した場合にも、企業側の正当性を裏付ける証拠として活用できます。
このような対応手順の整備は、苦情対応の品質向上のみならず、従業員のメンタルケアや企業防衛の面からも、大きな効果を発揮します。

3. クレーム対応マニュアルの作成や運用の注意点
クレーム対応マニュアルは、一度作って終わりではありません。現場で実際に使われるものである以上、「分かりやすく、使いやすく、常にアップデートされている」ことが求められます。この章では、マニュアルの作成や運用における具体的な注意点について解説します。
3.1 現場の担当者がわかりやすい表現で作成する
クレーム対応マニュアルは、最前線で対応する現場の担当者がすぐに理解し、行動に移せる内容でなければ意味がありません。専門用語や法律用語を多用すると、内容が正確でも現場では「読みにくくて使えない」文書になってしまうおそれがあります。
たとえば、「カスタマーハラスメントに該当するか検討する」などの表現は、「お客様の要望が過剰・不当でないか判断する」など、より平易な言い回しに置き換えるのが望ましいでしょう。ポイントは、マニュアルを読む人が新人であっても迷わず対応できるような内容にすることです。
また、想定されるクレーム事例とその対応例をあわせて記載することで、より実用的で現場に即したマニュアルになります。対応の「型」があれば、現場担当者は心理的負担を軽減しながら冷静に行動できます。
3.2 マニュアルを従業員全員に共有する
マニュアルは、作成しただけでは不十分です。現場で実際に使用されることが目的である以上、全従業員に適切に共有され、内容が周知されている必要があります。クレーム対応は、特定の担当者だけで完結するものではなく、受付や営業、カスタマーサポート、店舗スタッフなど、あらゆる部署で発生しうる業務だからです。
共有の方法としては、社内イントラネットへの掲載や、定期的な研修・ミーティングでの読み合わせ、シミュレーション(ロールプレイング)研修などが効果的です。また、マニュアルの一部を印刷してすぐ手元で見られるようにしたり、FAQ形式でまとめたハンドブックを用意したりするなど、使いやすさの工夫も重要です。
誰もが同じマニュアルを参照し、同じ対応方針で動ける状態をつくることが、組織全体での一貫したクレーム対応につながります。属人的な対応ではなく、企業としての判断・対応であることを示すうえでも不可欠な取り組みといえるでしょう。
3.3 マニュアルは定期的に更新する
社会の変化や消費者の価値観の多様化に伴い、クレームの内容や傾向も常に変化しています。たとえば、SNSの普及により、顧客からの不満が一気に拡散されるリスクが高まっています。そのため、過去に作成したマニュアルが現在の状況に合っていない可能性もあります。
マニュアルは一度作ったら終わりではなく、定期的に見直して更新することが大切です。具体的には、次のようなタイミングでの見直しを推奨します。
- 実際のクレーム対応後に課題が明らかになったとき
- 新しい媒体(SNSやチャットボットなど)からのクレームが増えてきたとき
- 法改正や行政指針が発表されたとき(例:厚生労働省のカスハラ対策マニュアル)
- 重大クレーム・トラブルが発生したとき
こうした見直しを重ねることで、マニュアルが「現場に生きたツール」として機能し続け、時代に即した実効性を保てます。更新作業の責任者を明確にし、定期点検のサイクルを組み込んでおくことも実務的なポイントです。
4. 外部弁護士に相談できる体制の重要性
クレーム対応において、企業の内部努力だけでは対応しきれない場面も少なくありません。特に、悪質クレーマーによる過度な要求、脅迫まがいの言動、損害賠償請求、ネットでの風評被害など、対応を一歩誤ると重大なトラブルに発展するおそれがあります。
こうしたリスクに備えるには、社内の対応だけでなく、外部の法律専門家、特に企業法務に詳しい弁護士と連携する体制を構築しておくことが重要です。弁護士に相談することで、法的に許容される対応の線引きや、相手の要求に対する可否の判断を適切に下すことができます。
また、必要に応じて「弁護士名での通知書」や「内容証明郵便」の送付など、法的手段に移る準備があることを相手に示すことで、クレーマー側の態度が軟化するケースもあります。
弁護士と平時から相談関係を築いておけば、実際に問題が起こった際にも迅速に相談でき、被害拡大を防ぐことが可能になります。いざというときに備え、クレーム対応の一環として「法的支援の選択肢」も社内で明確にしておくべきです。
5. まとめ:クレーム対応マニュアルの作成や運用は弁護士へ
クレーム対応マニュアルは、企業にとってリスクマネジメントの重要な武器となります。現場が混乱せずに迅速かつ適切な対応ができるよう、分かりやすく実用的な内容で設計されていることが求められます。
また、対応の一貫性を保つためには、マニュアルを全従業員に共有し、運用体制を社内に根づかせることが必要です。さらに、クレームの傾向や社会情勢に応じて、マニュアルの内容を定期的に更新することも不可欠です。
とはいえ、マニュアルの作成や運用には、法律や顧客対応に関する深い知見が求められます。悪質クレーマー対応では、法的な判断が必要となる場面も少なくありません。そのため、マニュアル整備や運用にあたっては、企業法務に精通した弁護士に相談することを強くおすすめします。
よつば総合法律事務所では、企業の業種や規模に応じた実践的なマニュアル作成支援や、クレーム対応の法律相談に対応しています。現場で本当に使えるマニュアルを整え、従業員と企業を守る体制を整えていきましょう。