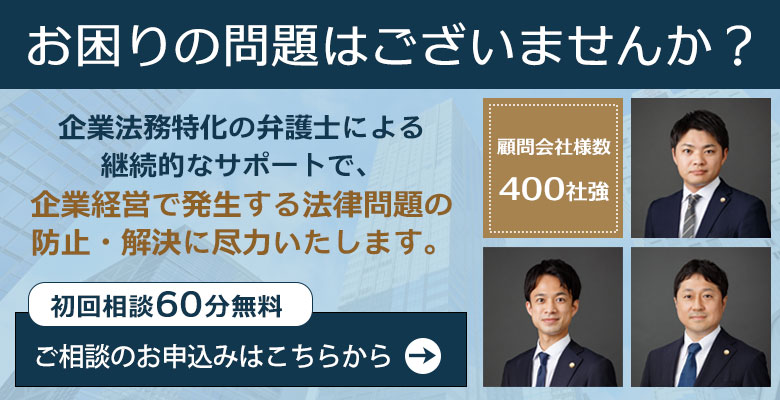クレーム対応は、企業にとって常に向き合わなければならない重要課題のひとつです。
対応を誤ると、企業の信用が損なわれるだけでなく、従業員のメンタルヘルスを損なったり、業務の停滞、法的リスクにもつながります。
「この程度なら社内で処理できると思っていたクレームが、いつの間にか収拾のつかないトラブルに発展していた」という事例は少なくありません。
では、どの段階で弁護士に相談すべきでしょうか?クレーマー対応に「限界」を感じたときでしょうか?それとも法的な脅し文句が出てきたときでしょうか?
本記事では、クレーム対応において弁護士に「相談すべきとき」と「依頼すべきとき」の判断ポイントを、実例に触れながら解説します。
目次
1. クレームが発生したら早期に弁護士に相談
クレーム対応は、初期対応を誤ると、大きなトラブルの火種となりかねません。問題がこじれると長期化し、対応にかかる時間や労力も増大します。
しかし、クレームが発生した直後に弁護士へ相談するだけでも、社内対応の方向性が明確になり、不要なトラブルを未然に防げるケースもあります。
「弁護士に相談するのはハードルが高い」と感じる企業も少なくありませんが、クレームの内容によっては、早い段階で法的観点から状況を整理することが不可欠です。
ここでは、早期相談のメリットや、相談先の選び方について具体的に解説します。
1.1 相談だけで解決の指針が見えることも多い
クレームが発生した初期段階で、「弁護士に相談してもよいのだろうか」と迷う企業担当者は少なくありません。
しかし実際には、相談するだけでも状況を整理でき、対応の方向性が見えてくるケースが多くあります。
たとえば、以下のようなポイントを検討するだけでも、冷静な判断材料が得られます。
- 相手の要求に法的な根拠があるかどうか
- 書面や録音などのやり取りに違法性があるかどうか
- 今後の展開として想定されるリスクやトラブルの可能性
また、複数の対応方針が考えられる場合でも、それぞれのメリット・デメリットを整理して比較することで、社内での意思決定がスムーズになります。
実際「一度相談して全体像がつかめたことで、弁護士に依頼せず社内対応で収束できた」というケースも多く見られます。
まずは状況を共有し、法的な視点で整理してもらうだけでも、クレーム対応の見通しがぐっと立てやすくなるはずです。

1.2 無料相談を利用する
クレーム対応に悩んでいても、「費用がかかるのでは」と相談をためらう企業担当者は少なくありません。
しかし近年では、企業向けに無料相談を提供している法律事務所も増えており、初動の不安を解消する手段として活用する企業が増えています。
無料相談では、クレームの概要を共有するだけでも、法的な見立てや初期的な対応方針について弁護士の助言を得ることが可能です。相手の主張に法的根拠があるのか、自社でどこまで対応できるのかといった点を整理することで、判断ミスやトラブルの拡大を防ぐためのヒントが得られます。
ただし、通知書の作成や相手との交渉など、実務対応に踏み込む場合には正式な「依頼」となり、費用が発生します。
一方で、「まずは状況を把握したい」「どこまでが社内対応の限界か知りたい」といった初期段階の判断であれば、無料相談は非常に心強い制度です。
1.3 顧問弁護士が入れば顧問弁護士に相談する
すでに顧問弁護士と契約している企業であれば、まずその弁護士へ相談するのが基本です。
顧問弁護士は、会社の事業内容や過去の対応履歴を把握しているため、一から事情を説明する手間が省け、迅速かつ的確な助言を得やすくなります。
また、緊急対応が必要な場面でも、顧問契約があれば優先的に対応してもらえるケースが多く、対応文書のチェック、社内記録の残し方、やり取りの注意点など、実務に即したアドバイスをスピーディーに受けることができます。
さらに、継続的な関係を築いていることで、担当者が萎縮せず、気軽に相談しやすい環境が整っている点も大きなメリットです。
なお、顧問弁護士がいない場合でも、クレーム対応を機に、顧問契約の必要性を感じて導入を検討する企業も少なくありません。
2. 弁護士へ依頼するタイミング
弁護士への「相談」は早ければ早いほどよいといえますが、具体的に「依頼」すべきタイミングはいつなのか。その判断は難しいところです。
ここでは、企業が弁護士に正式に依頼すべき典型的なケースを6つ取り上げ、なぜその段階で依頼すべきかを具体的に解説します。
2.1 従業員が暴力を受けた
クレーマー対応がエスカレートすると、単なる言葉のやり取りでは済まなくなるケースがあります。
怒鳴る、机を叩くといった威圧的な態度にとどまらず、従業員に対して物理的な暴力や威嚇行為に及ぶ例も少なくありません。
たとえば次のような事例が実際に見受けられます。
- 受付対応中、クレーマーが怒りに任せて机を叩いたり、壁を蹴ったりする
- 他の従業員の目の前で、「こいつのせいだ」と肩を押したり、距離を詰めて威嚇する
これらの行為は、もはや苦情の域を超えており、刑法上の暴行罪や、民事上の不法行為(損害賠償請求の対象)に該当する可能性があります。
また、企業には従業員の心身の安全を守る「安全配慮義務」があり、このような暴力的行為を放置することは、企業側の責任問題にも発展しかねません。
このような場面では、ただちに弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が介入することで、相手に対して警告文書を送ったり、必要に応じて警察との連携や保全措置(接近禁止の仮処分など)を講じることが可能になります。
2.2 脅迫・恐喝と取れる言動がある
クレームの内容がエスカレートすると、相手がプレッシャーをかけるために「脅し」と取れる言動を交えてくることがあります。この段階に入ると、企業としては単なるクレーム対応では済まず、法的な視点からの判断と対応が必要になります。
たとえば、次のような言動は要注意です。
- 「謝罪しなければ、SNSで会社のことを晒してやる」
- 「家族や取引先にもばらすぞ」
- 「おまえの名前をネットに書いてやる」
- 「金を払えば黙っておいてやる」
このような発言は、刑法上の脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
特に金銭を要求された場合は、明らかに恐喝と見なされるリスクが高く、企業として刑事告訴や損害賠償請求を視野に入れるべき場面です。
また、相手がこのような言動を繰り返すと、対応担当者が強いストレスを受け、社内全体の士気や業務効率にも悪影響を与えます。
このような状況に陥った場合は、速やかに弁護士に依頼し、以降の連絡窓口を一本化することが重要です。弁護士が代理人として介入することで、相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。
さらに、脅しに屈せず、正当な法的手段をもって対応する姿勢を示すことで、その後のトラブル拡大を防止する効果も期待できます。
2.3 業務妨害行為が続く
クレーム対応が長引くと、クレーマーの行動が本来の苦情の域を超え、企業の業務そのものを妨害するケースに発展することがあります。このような状態に至った場合、自社だけでの対応には限界があると判断すべきでしょう。
以下のような行為は、明らかに業務妨害と見なされる典型例です。
- 電話を1日に何十回もかけ続ける
- 同じ内容のメールを何日も連続して送りつける
- アポイントなしで何度も来社し、長時間にわたり居座る
- 店舗や事務所内で大声を出して騒ぎ、他の顧客に不安を与える
これらは単なる迷惑行為ではなく、刑法上の偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪に該当する可能性があります。
放置すれば、業務効率の低下や従業員の精神的負担の増大にとどまらず、他の顧客からの信頼を損なうリスクも避けられません。
このような状況では、弁護士に依頼し、警告文書の送付や刑事告訴の検討といった具体的な対応を速やかに講じることが重要です。
弁護士が介入することで、「これ以上の行動は許されない」という強いメッセージを相手に伝えることができ、再発防止にもつながります。

2.4 相手の要求が不当に高額である
クレーム対応を続けていると、相手からの要求額が常識の範囲を超えてくることがあります。
本来であれば返金や謝罪で収束するはずの問題が、法的根拠のない高額な損害賠償請求にまで発展するケースもあります。
たとえば、次のような要求には注意が必要です。
- 商品に小さなキズがあったことを理由に、10万円以上の慰謝料を請求された
- 店舗での接客対応に不満を持ち、「精神的苦痛を受けた」として100万円の支払いを要求された
- 「この件をネットに書かれたら損害が出るだろう」と言いながら、和解金の名目で50万円を求められた
このような請求は、金額の妥当性や法的根拠に疑問があることが多く、慎重な対応が求められます。不用意に応じてしまうと、「この会社には要求を通すことができる」と見なされ、さらなる不当な請求を繰り返されるおそれもあります。
また、相手が金銭を得る目的でクレームを繰り返している場合、社内だけで対応し続けるのは困難です。
こうしたときは、弁護士に依頼して法的な観点から妥当性を精査し、必要に応じて反論や拒絶の意思を明確に伝える対応が重要になります。場合によっては、相手に「これ以上の要求は通らない」というメッセージを伝えるために、内容証明郵便での回答や、反対に損害賠償請求の準備を進める必要もあります。
企業としての立場と正当性を守るためにも、高額請求を受けた時点で弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
2.5 相手が法的措置を示唆している
クレーム対応の過程で、相手から「法的な手段に出る」といった発言が出てくることがあります。こうした言動があった場合、たとえまだ訴訟に至っていなくても、企業側としてはすぐに弁護士対応に切り替えるべきタイミングといえます。
特に、次のような発言があった場合は注意が必要です。
- 「裁判を起こすつもりだ」
- 「弁護士を立てて対応する」
- 「法的措置を取ることになるかもしれない」
- 「消費者センターにも訴える」
これらの発言は、単なる感情的な言い回しではなく、本格的なトラブルへ発展する前兆ととらえるべきです。相手が実際に弁護士を立てて交渉をはじめた場合、企業担当者が個人で対応を続けるのはリスクが高くなります。
特に、訴訟に発展した場合には、次のような法的知識と専門的対応が求められる作業が一気に増えます。
- 裁判所への書面提出
- 主張・証拠の準備
- 出廷への対応
- 和解交渉
このような場面では、早い段階で弁護士に依頼し、対応の主導権を失わないことが重要です。
相手の言葉を「脅し」だと軽視せず、具体的な動きが見えた時点で法的対策を講じることで、余計な損害やレピュテーションリスク(評判リスク)を防ぐことができます。
2.6 SNSでの誹謗中傷が始まった
近年のクレーム対応では、SNS上での発信を通じた「攻撃」が深刻な問題になりつつあります。従来のような個別対応の枠を超えて、企業の評判そのものを損なう行為に発展するケースも少なくありません。
特に次のような行為が確認された場合には、早期に弁護士へ依頼し、対策を講じることをおすすめします
- X(旧Twitter)やInstagramなどで、企業名や担当者名を挙げて非難する投稿
- Googleレビューや食べログなどに、虚偽または誇張された悪評を投稿する
- 「内部告発」や「被害者の声」として、YouTubeやTikTokに一方的な主張を投稿する
- ハッシュタグを使ってクレーム内容の拡散を図る
これらの行為は、単に不快というレベルではなく、名誉毀損・業務妨害・信用毀損などの違法行為に該当する可能性があります。
また、SNSは拡散力が高いため、1件の投稿が数日で何千・何万回も閲覧され、企業イメージの低下や取引先からの信頼喪失につながるおそれもあります。
こうした被害を防ぐためには、弁護士に依頼して法的措置を含む対応を早急に検討することが極めて重要です。
弁護士が対応することで、次のような法的手段を講じることができます。
- サイト運営会社への投稿削除請求
- 投稿者の身元特定(発信者情報開示請求)
- 名誉毀損・信用毀損に基づく損害賠償請求
- 拡散防止に向けた注意喚起やメディア対応のアドバイス
特にインターネット上の情報は、一度拡散されると完全に消し去ることが難しいため、初動のスピードが対応の成否を左右します。
「炎上」が始まった時点ではなく、兆候が見えた段階で弁護士に依頼しておくことが、最悪の事態を回避するポイントとなります。
3. まとめ:早めに弁護士への相談や依頼を
クレームの対応は、その内容や相手の出方によって、必要な対策が大きく変わってきます。「このくらいなら自社でなんとかなる」と考えて動き出したものの、気付けば対応が手に余るような状況になっていた。そんなケースは決して珍しくありません。
初期の段階であれば、まずは弁護士に相談することで、法的にどんなリスクがあるのか、どこまで社内で対応できるのかが見えてくることがあります。実際、話を整理するだけでも「何を優先すべきか」がはっきりする場面は少なくありません。
一方で、相手の言動がエスカレートしている場合や、従業員への影響、業務への支障が出ているような状況では、実際に弁護士に依頼することも選択肢として考えるべきです。
代理人として弁護士が入れば、相手との連絡をまかせることができ、企業としての対応負担も大きく軽くなります。また、法的な立場からしっかり対応することで、これ以上のトラブルを抑える効果も期待できます。
「まだ依頼するほどではないかもしれないけれど、少し不安だ。」
そう感じたときには、まず弁護士に相談してみることがひとつの備えになります。
そして、相談のなかで「このまま自社で対応し続けるのは難しい」と感じたときには、依頼も視野に入れて具体的な対応を検討するタイミングかもしれません。