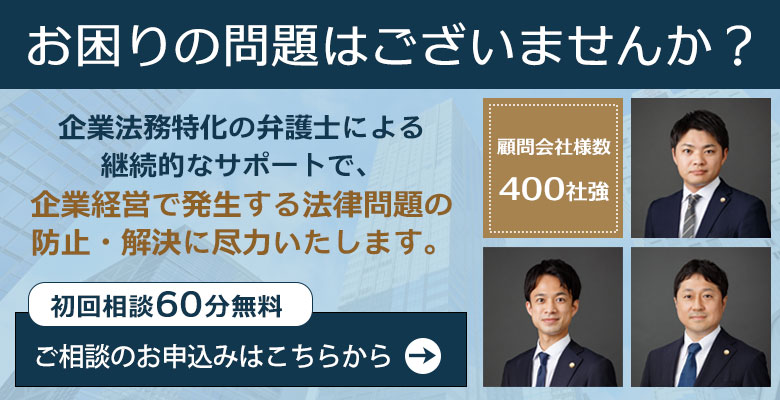「担当者の対応が悪いとSNSで叩かれ、店舗の評判が急落した」
「クレーム対応を誤ったせいで、取引先からの信用まで失った」
私たちよつば総合法律事務所には、こうした深刻なご相談が寄せられています。
クレームは、どの企業にとっても避けて通れないものです。特に中堅・中小企業では、ひとつの対応の成否が経営に直結することもあります。
クレーム対応で何より大切なのが、「初動対応」です。
最初の一手を間違えると、相手の怒りがエスカレートし、社内にも多大なストレスや混乱をもたらします。逆に、正しい対応ができれば、相手の不満を早期に収め、関係の修復や信頼の維持につながることもあります。
この記事では、企業法務に強い弁護士が、クレーム対応で絶対に押さえておきたい初動対応のポイントと、やってはいけないNG対応をわかりやすく解説します。
1. クレームは初動対応が重要
クレーム対応で最も大切なのは、「最初の対応」を間違えないことです。
この初動対応しだいで、クレームが早期に収束するか、それとも深刻なトラブルに発展するかが決まると言っても過言ではありません。
とくに重要なのが、相手が感情的になっている場面での接し方です。
むやみに反論したり、「自社は悪くない」と強く否定したりすると、かえって相手の怒りに火をつけてしまいます。かといって、事実確認をしないまま安易に謝罪すると、誤った責任を認めたと受け取られ、後の対応が難しくなることもあります。
まずは冷静に話を聞く姿勢を見せることが、初動対応の基本です。
さらに、対応の正確さだけでなく、「スピード」も重要です。返答までに時間がかかると、相手は「無視された」「誠意がない」と感じて、怒りを増幅させるおそれがあります。
たとえすぐに回答できなくても、「ご意見は確かに承りました。〇日までにご連絡いたします」など、一次対応を早めに行うだけでも、相手の不安や不満をやわらげる効果があります。
中堅・中小企業では、社長や現場責任者がクレーム対応の最前線に立つ場面も多く、その一手が企業の信頼を左右するといっても過言ではありません。
初動対応の重要性を社内で共有し、「誰が」「どのように」対応するかをあらかじめ定めておくことが、トラブルをこじらせない第一歩です。

2. クレームの初動対応で押さえるべきポイント
クレーム対応をこじらせないためには、初動の段階で意識しておくべき4つのポイントがあります。
これらのポイントを無視して、やみくもに謝罪したり、マニュアル通りの受け答えに終始してしまうと、かえって相手の怒りを強め、問題が長期化・深刻化するおそれがあります。
ここからは、初動対応の質を高めるために押さえておきたい各ポイントについて、順に具体的に解説していきます。
2.1 相手の話に耳を傾けてお詫びする
クレームを受けた直後は、相手の話を途中でさえぎらず、丁寧に最後まで聞きましょう。不満を抱える顧客の多くは、「まず話を聞いてほしい」「自分の気持ちを理解してほしい」と感じています。
その思いに正面から向き合わなければ、どんなに正しい説明をしても、かえって反感を買う結果になりかねません。
話を聞くときは、相手が怒っている「内容」だけでなく、「感情」にも注目します。
理不尽な要求に思えても、背景には対応への不信感や、説明不足への不満があることが少なくありません。事実と感情を切り分けながら、相手の気持ちを受け止める姿勢を持つことが大切です。
そのうえで、最初の段階では感情に寄り添うお詫びの言葉を伝えましょう。たとえば、次のような言い回しが有効です。
「ご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありません」
「お怒りはごもっともです。お話をしっかり伺います」
ここで注意が必要なのは、事実がまだ確認できていない段階で責任を認めてしまわないことです。
たとえば、「こちらのミスでした」と言ってしまうと、後に事実が異なったときにトラブルが拡大するおそれがあります。
あくまで、相手の気持ちに寄り添う姿勢と誠実な対応の意思を示すことが、初動で求められる対応です。
2.2 事実関係を具体的かつ正確にヒアリングする
相手の話に耳を傾け、お詫びの姿勢を示したら、次に行うべきは事実関係の確認です。
ここを曖昧にしたまま対応を進めてしまうと、社内調査に齟齬が出たり、顧客との認識にズレが生じたりして、対応がさらに混乱するおそれがあります。
まずは、相手の話の中から5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)に関する情報を丁寧に引き出すことが大切です。この6つの要素を意識しながら聞き取りを行うことで、クレームの背景にある事実関係をより正確に把握できます。
たとえば、次のような点を具体的に確認しましょう。
- いつ(When):その出来事が起きた日時や時間帯
- どこで(Where):店舗名、支店名、担当部署などの場所
- 誰が(Who):関係する社員やスタッフの氏名・特徴
- 何を(What):どのような対応や言動が問題とされたのか
- なぜ(Why):顧客がその行為を問題だと感じた理由や経緯
- どのように(How):対応の態度、説明の仕方、やり取りの流れなど
これらをヒアリングする際には、あくまで冷静かつ丁寧な姿勢を心がけましょう。相手が感情的になっているときほど、こちらが落ち着いて聞くことで、信頼感を得やすくなります。
また、聞き取りの内容はできるかぎりその場でメモを取り、記録として残すことも重要です。後日、警察や弁護士など第三者に相談する場合や、社内で事実確認を進めるうえでも、正確な記録が大きな助けになります。
事実関係のヒアリングは、クレームの「本質」を見極めるための基礎です。表面的な怒りや言葉に左右されず、冷静に情報を整理することが、適切な対応への第一歩となります。
2.3 相手が希望する内容を把握する
事実関係を整理できたら、次に確認すべきなのが、「相手がどのような対応を求めているのか」という点です。
この「希望内容の把握」を誤ると、対応の方向性がずれてしまい、かえって相手の不満を強めることにつながります。
相手の要望には、たとえば次のようなパターンがあります。
- 謝罪の言葉がほしい
- 担当者の交代や指導をしてほしい
- 商品の交換・返金に応じてほしい
- 今後同じことが起きないように改善してほしい
ここで重要なのは、「相手の希望を決めつけないこと」そして「先回りして対応を提示しないこと」です。
相手の意向を確認する前に「返金をご希望ですね?」などと持ちかけると、本来そこまでの対応を求めていなかった相手にも期待感を抱かせてしまい、かえって要求が大きくなる可能性があります。
相手の希望を正確に把握するには、相手自身の言葉で要望を語ってもらうことが大切です。
しかし、相手が明確な希望を言葉にしない場合もあります。そのような場合には、相手の話の内容や語気、感情の動きに注意を向けながら、「何を大切にしているのか」「どこに納得がいっていないのか」といった背景をくみ取り、最終的に“自分の言葉で要望を表現してもらえるよう促す”ことが重要です。
このように、相手の希望を丁寧に聞き取り、言葉として明確にしてもらうプロセスをつくることが、クレームの収束に向けた第一歩となります。こちらが決めつけず、あくまで相手の立場に寄り添って対応することで、信頼関係の構築にもつながります。
2.4 法的な責任の有無・程度を理解する
相手の希望が明らかになったら、自社に法的な責任があるかどうか、あるとすればどこまでがその範囲かを冷静に判断する必要があります。
すべてのクレームに企業側の法的責任があるとは限りません。説明がやや不足していたとしても、直ちに損害賠償や返金義務が発生するわけではない場合もあります。
法的責任がないにもかかわらず、必要以上の補償をしてしまえば「過剰対応」となり、社内に余計な負担をかけることになります。
一方で、実際にミスや契約違反があり、企業側に明確な落ち度があるケースでは、誠実に謝罪し、適切な補償を行うことが求められます。本来あるべき対応を怠れば、「過少対応」となり、相手の怒りを増幅させてトラブルが深刻化するおそれがあります。
法的責任の有無や範囲を見極めるためには、次のような視点を持つとよいでしょう。
- 事実関係や契約内容に照らして、企業側に法的責任があるか
- 相手に具体的な損害が生じているか
- 社内の規程や過去の対応事例と整合しているか
こうした判断には、専門的な視点があると安心です。現場だけで結論を出そうとせず、法務部門や弁護士に相談することをおすすめします。

3. クレームについてのNG対応
クレーム対応においては、やってはいけない対応、いわゆる「NG対応」も数多く存在します。
ここでは、企業の現場でよく見られるNG対応の例を5つ挙げ、それぞれの問題点と注意点を解説します。
3.1 感情的に反論する
クレーム対応でもっとも避けるべきなのが、感情的な反論です。
たとえば、相手の発言にイライラして「それは事実ではありません」「そういう言い方は困ります」と即座に言い返してしまうと、相手の怒りに油を注ぐ結果になりかねません。
クレームを申し立てている側は、多かれ少なかれ不満や怒りの感情を抱いています。
そのため、感情的に言い返されると「やはり誠意がない」「真剣に対応する気がない」と受け取られやすく、クレームがこじれる原因になります。
また、対応者自身が冷静さを欠くと、本来の対応方針を見失い、誤った判断や発言をしてしまうリスクも高まります。
感情的な反論を防ぐためには、以下のような意識を持つことが重要です。
- 相手の言葉に即座に反応せず、一呼吸おいて対応する
- 相手の主張の背景や感情を理解しようとする姿勢を持つ
- 不快な表現があっても、まずは落ち着いたトーンで話を受け止める
クレーム対応では「相手の感情を受け止める姿勢」が信頼の土台になります。冷静な対応は、トラブルの早期収束だけでなく、企業イメージの維持にもつながります。
3.2 クレームを放置したり、対応を遅延させたりする
クレームに対して適切な対応を取らず、放置したり連絡を後回しにしたりする行為も、重大なNG対応のひとつです。
「忙しくて後回しにしてしまった」「どう対応すればよいか分からないので様子を見ていた」といった対応の遅れは、相手にとって「軽視されている」「誠意がない」と受け取られやすく、事態をさらに悪化させてしまいます。
特に注意すべきなのは、相手が返答を待っている状況で何の連絡もせずに時間が経過することです。このような「沈黙」は、企業側の責任を認めたくない態度、あるいは逃げている印象を与えてしまい、感情的な反発を招きます。
対応の遅れが原因で、SNSや口コミサイトなど外部への不満発信に発展するケースも少なくありません。小さなクレームが、企業の評判に大きなダメージを与えるリスクにつながります。
対応がすぐにできない場合であっても、たとえば次のように「連絡が遅れる理由」と「今後の見通し」を丁寧に伝えることが重要です。
- 「現在、社内で事実確認を進めており、〇日までにご連絡いたします」
- 「ご指摘の点について調査中ですので、改めてご説明させていただきます」
このように、継続的なコミュニケーションを保つことで、「対応されている」という安心感を相手に与えることができ、クレームの沈静化にもつながります。
3.3 回答期限や対応内容などの約束を守らない
対応の遅延を避けるために「〇日までにご連絡します」「〇〇の対応を行います」といった見通しや対応方針を伝えることは、相手に安心感を与えるうえで重要です。
しかし、それを実行しなければ、かえって信頼を損ねてしまいます。
たとえ小さな約束でも、守られなければ「また裏切られた」と受け取られ、相手の不満が一気に膨らんでしまいます。「誠意がない」「適当な対応で済ませようとしている」といった印象を与え、初期対応の効果が台無しになることもあります。
だからこそ、「一度伝えた約束は守る」という意識を徹底することが重要です。
しかし、やむを得ず対応が遅れてしまう場面もあるかもしれません。そのような場合には、約束した期限の前に事情を説明し、新たな対応予定をしっかり伝えることが大切です。
たとえば、次のような表現が考えられます。
- 「当初の予定より確認に時間がかかっております。〇日までに改めてご連絡いたします」
- 「ご案内した内容に追加事項が判明しましたので、正確な情報を整理してからご報告いたします」
このように、丁寧な説明と今後の見通しをあわせて伝えることで、相手には「真摯に対応している」という印象を持ってもらえる可能性が高まります。
たとえ対応が予定より遅れた場合でも、こうした誠実なフォローがあるかどうかで、相手の心象や信頼度には大きな違いが生まれるものです。
3.4 過大な要求をすぐ受け入れてしまう
クレーム対応の現場では、「早く終わらせたい」「これ以上こじらせたくない」といった心理から、相手の要求をそのまま受け入れてしまうケースが少なくありません。たとえば、次のような対応です。
- 「全額返金しろ」「二度と担当者を出すな」といった強い要求に即座に応じる
- 「謝罪文を掲示しろ」「SNSで公式に謝れ」と言われ、その場で対応を約束する
このような対応は、一時的には事態を沈静化させるように見えても、実際には新たなトラブルの火種になりかねません。
一度でも過大な要求を無条件に受け入れてしまうと、「この会社は押せば譲歩する」と認識され、要求がエスカレートしていくおそれがあります。
また、他の顧客から同様のクレームが発生した際に、整合性を欠いた対応を取ることにもなりえます。
過大要求への対応では、まず内容の正当性を慎重に見極めることが重要です。要求が過度なものであれば、安易に受け入れるのではなく、丁寧に説明した上で断る、もしくは社内での検討が必要である旨を伝えましょう。
たとえば次のような表現が適切です。
- 「大変恐縮ですが、現時点ではすぐにお約束できませんので、社内で確認した上で改めてご連絡いたします」
- 「貴重なご意見として受け止め、今後の対応について社内で協議させていただきます」
過剰な要求を毅然とした態度で受け止めつつも、相手を否定しない丁寧な伝え方が、今後のやり取りの円滑化につながります。
3.5 根拠なく法的責任がないと断定する
クレームの初期対応において、「こちらに責任はありません」「それは法的に問題ないと認識しています」といった断定的な発言を、根拠の確認もないまま行ってしまうのは非常に危険です。
事実関係の把握や契約内容の確認を経る前に、一方的に「責任はない」と言い切ってしまうと、「取り合う気がない」「逃げようとしている」と受け取られ、相手の不信感や怒りをさらに強めてしまいます。
しかも、万が一あとから自社に法的責任があることが判明した場合、最初の「責任はない」とする発言が、クレームの悪化・長期化につながるおそれがあります。責任があるのにそれを否定してしまえば、誠意を疑われるだけでなく、「嘘をつかれた」「隠蔽された」と受け取られ、企業イメージや信頼に大きな打撃を与えかねません。
そもそも、法的責任の有無を正確に判断するには、契約内容や社内規程、提供サービスの状況、損害の有無と範囲など、複数の視点からの冷静な検討が必要です。こうした確認を怠ったままの断定は、たとえその場をしのげても、結果として大きなリスクを抱えることになります。
対応のポイントは、「現時点で断定せず、事実確認のうえ判断する」という姿勢を丁寧に伝えることです。たとえば、次のような言い回しが適切です。
- 「まずは状況を確認させていただき、必要な対応について社内で検討いたします」
- 「契約内容や社内の対応方針を確認のうえ、あらためてご連絡差し上げます」
根拠に基づかない否定ではなく、事実の調査と検討を前提に対応する姿勢こそが、信頼を守る対応の基本です。
4. まとめ:弁護士への相談や依頼も選択肢の1つ
クレーム対応では、「初動対応」が最も重要なポイントです。①相手の話に耳を傾け、②事実を正確に把握し、③希望内容を引き出し、④法的責任の有無を冷静に検討するという4つのプロセスを丁寧に積み重ねることが、トラブルの長期化や深刻化を防ぐポイントとなります。
一方で、初期対応を誤ってしまえば、たとえ小さなトラブルであっても、大きな損害や評判リスクへと発展しかねません。とくに、感情的な対応・遅延・不用意な発言・過剰な妥協といったNG対応は、信頼関係を壊し、二次被害を招く原因となります。
中堅・中小企業では、専任のクレーム対応担当者や法務部門が十分に整備されていないことも少なくありません。そのような環境では、「何が正しい対応か」を判断するのが難しい場面も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、企業法務に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
「このクレームは法的責任が生じるのか」「過剰な要求ではないか」「どのように対応すれば二次被害を防げるか」など、専門的な視点からアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えた対応が可能になります。
クレームは、企業にとって確かにリスク要因ですが、一方で社内体制の見直しや信頼回復の機会にもなり得ます。そのためには、場当たり的な対応ではなく、適切な初動と一貫した対応方針が欠かせません。
万が一に備える意味でも、日頃から弁護士と連携しておくことは、企業のクレームリスク管理における強力な備えとなります。