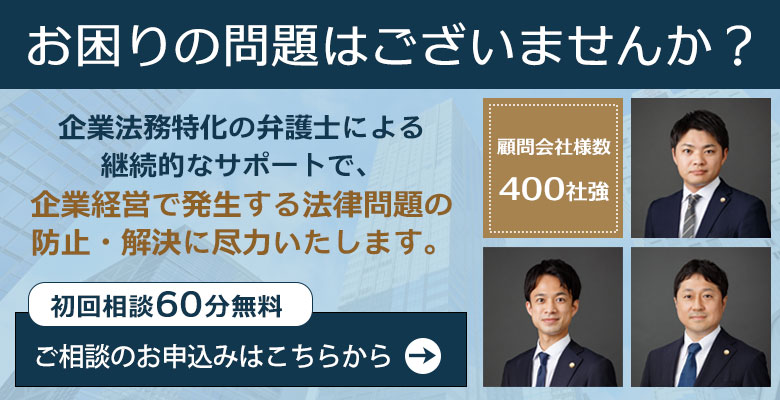目次
1. 安易な解雇は厳禁
「仕事ができない」
「ミスが多い」
「頻繁に遅刻欠勤をする」
従業員を解雇したいと思ったことはありませんか?
解雇をしたいと思うご事情はよく理解できますが、日本には解雇規制が存在し、解雇のハードルは非常に高いのが現実です。
無理に解雇に踏み切ると、会社にとって様々なリスクが生じます。そのため、弁護士は解雇を避けて別の手段を検討することが多いです。
今回は、解雇のハードルとリスクを解説します。
2. ハードルが高い解雇~こんな事例でも解雇無効!?
まず、「これだけひどくても解雇できないのか…」という裁判例をご紹介します。
自社路線で痴漢したことを理由に諭旨解雇したところ、諭旨解雇が無効と判断された事例(東京地方裁判所平成27年12月25日判決)
事案の概要
- Aは、痴漢行為の撲滅に積極的に取り組む鉄道会社の駅係員として従事していた。
- Aは、勤務中ではないものの、自社路線の電車内で痴漢を行い、罰金20万円の略式命令を受けた。
- 会社はAを論旨解雇にした。
普通の感覚としては、「鉄道会社に勤めている従業員が、いくら勤務中ではないとはいえ、自社の路線で痴漢したら、流石に解雇」というものかと思います。
しかし裁判所は、次のような理由で会社の行った諭旨解雇は無効と判断しました。
- Aの行為は、勤務時間中に行われたものではなく、私生活上の非行であること
- Aの行為は略式命令で罰金20万円の支払を命じられるにとどまったこと
- Aの行為が許されないものであることは当然であるものの、Aの行為は条例の規定による処罰の対象となり得る行為の中でも、悪質性の比較的低い行為であること
- マスコミによる報道はされず、報道により会社の評判が下がった事実はないこと
- 本件以外のAの勤務態度に問題はなく、これまでに懲戒処分を受けていないこと
諭旨解雇とは、従業員に一定期間内に辞表を提出することを求め、これに応じない場合には解雇を行う懲戒処分と言われています。
自発的な退職の余地を認める点で、懲戒解雇より少しだけ軽い懲戒処分と位置付けられています。
この事例では、(懲戒解雇よりも軽い)諭旨解雇ですら無効ですから、仮に懲戒解雇をしていた場合でも同様に無効でしょう。解雇のハードルは極めて高いです。

3. 揺れる解雇有効性の判断~こんな事例でも無効になり得る!?
「第一審は解雇有効だったものの、控訴審で解雇無効になった」というように、裁判所によって解雇の有効性の判断が分かれることもよくあります。それくらい、解雇有効性の判断は難しいです。
解雇有効性の判断の難しさが分かる裁判例を2つ紹介します。
(1) 旅費等の不正受給を理由に懲戒解雇したところ、解雇有効性の判断が分かれた事例(札幌高等裁判所令和3年11月17日判決)
事案の概要
- Aは1年6か月の間に、100回にわたって旅費の不正請求を繰り返した。
- 不正受給の総額は約54万円であった。
- Aは広域インストラクターという営業インストラクターの中でも特に模範となるべき立場にあった。
- 会社はAを懲戒解雇した。
この事案で、裁判所は、第一審では懲戒解雇を有効と判断したものの、控訴審では懲戒解雇を無効と判断しています。
第一審は次のような理由で懲戒解雇を有効と判断しました。
- Aは不正請求の事実を認めて全額返納したが、回数、金額などを踏まえると、悪質性が高いこと
- Aはこれまで懲戒処分歴がなく極めて優秀な業務実績を上げてきたものの、その結果得られた立場は、他の者に模範を示すべき立場であったこと
一方で、第二審は次のような理由で懲戒解雇を無効と判断しました。
- Aと同様に、他のインストラクターも同様の不正受給を繰り返していたなど、会社の旅費支給事務にずさんともいえる面がみられること
- Aに懲戒歴はなく、営業成績は優秀で会社に貢献してきたこと
- Aと同程度の不正受給をした者は最も重くて停職3か月になっているところ、懲戒処分を受けた他の従業員との関係で、Aの懲戒解雇は均衡を失するといわざるを得ないこと
他の裁判例を見ると、会社内の横領や窃盗行為は、比較的解雇有効と判断されているケースが多いです。本件で解雇無効となったのは、「処分のバランス、平等さ」が欠けていた点が大きな理由です。
解雇をするときは、その行為の重大さだけではなく、他の労働者(過去の労働者も含みます)との処分のバランスも慎重に検討する必要があります。
(2) パワハラを理由に分限免職処分をしたところ、免職処分有効性の判断が分かれた事例(最高裁判所令和4年9月13日判決)
事案の概要
- Aは消防職員として勤務をしていた。
- Aは5年を超えて、以下のようなパワハラを80件余り繰り返した。
- 訓練中に蹴ったり叩いたりする、羽交い絞めにして太ももを強く膝で蹴る、顔面を手拳で10回程度殴打する、約2kgの重りを放り投げて頭で受け止めさせるなどの暴行
- 「殺すぞ」、「お前が辞めたほうが市民のためや」、「クズが遺伝子を残すな」、「殴り殺してやる」などの暴言
- トレーニング中に陰部を見せるよう申し向けるなどの卑わいな言動
- 携帯電話に保存されていたプライバシーに関わる情報を強いて閲覧した上で「お前の弱みを握った」と発言したり、プライバシーに関わる事項を無理に聞き出したりする行為
- Aを恐れる趣旨の発言等をした者らに対し、土下座を強要したり、Aの行為を上司等に報告する者がいた場合を念頭に「そいつの人生を潰してやる」と発言したり、「同じ班になったら覚えちょけよ」などと発言したりする報復の示唆
- パワハラにあった消防職員らのうち、Aが復帰した後の報復を懸念する者が16人、Aと同じ小隊に属することを拒否する者が17人に上った。
- 消防長は、分限免職処分(≒解雇)を行った
裁判所は、第一審と控訴審では、免職処分を無効と判断しました。しかし、最高裁では一転して、免職処分は有効と判断しました。
第一審と控訴審は、次のような理由で分限免職処分を無効としました。
- 組織として、パワハラ行為の防止の動機付けをさせるような教育指導や研修等を行わなかったこと
- Aに更生の機会を与えなかったこと
- A以外の者によるパワハラ行為と処分の均衡が図れているか疑問であること
一方で、最高裁は次のような理由で分限免職処分を有効としました。
- Aの性格を簡単に矯正することはできず、指導の機会を設けるなどしても改善の余地がないと考えて不合理ではないこと
- Aのパワハラにより消防組織の職場環境が悪化するといった影響は、公務の能率の維持の観点から看過し難いものであり、特に消防組織においては、職員間で緊密な意思疎通を図ることが、消防職員や住民の生命や身体の安全を確保するために重要であること
- Aの言動には報復を示唆する発言等が含まれており、現に報復を懸念する消防職員が相当数に上ることなどから、配置転換が困難であること
なお、分限免職処分とは、懲戒免職処分よりも軽い処分のことを指し、一般企業でいう普通解雇にあたります。
(3) 裁判官でも判断が分かれること
解雇をめぐる裁判では、裁判官の判断が分かれる事案も比較的多いです。
しかも、解雇のリスクも考えると、簡単に解雇を選択できないことがお分かりいただけるかと思います。
4. 解雇が無効となったときのリスク
では、解雇が無効になったときのリスクには具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?
解雇無効と判断された場合、①金銭的リスクや②従業員を復職させなければならないリスクが生じます。また、裁判に対応するための費用や労力もかかります。
(1) 金銭的リスク
解雇が無効になると会社はどのような金銭的リスクを負うことになるのか、次のケースで考えてみましょう。
従業員の月収:額面30万円
令和6年4月 従業員を解雇
令和6年7月 従業員から解雇無効の訴訟提起
令和7年9月 第一審での口頭弁論終結
令和7年11月 第一審で解雇無効の判決
この事案で、仮に従業員が令和6年4月1日から令和7年9月30日まで丸々18か月間働けなかった場合、会社に540万円+α(遅延損害金など)の支払が命じられる可能性があります。
内訳は次のとおりです。
① 解雇後の賃金(バックペイ)
月額30万円×18か月=540万円
② 遅延損害金(年3%)
約12万円
~解雇後の賃金(バックペイ)とは~
「バックペイ」とは、解雇時点までさかのぼって、会社が賃金を支払うことを言います。
解雇が無効と判断された場合、雇用契約が継続していることになるので、解雇から現在までの賃金を支払う必要があります。過去にさかのぼって(バック)賃金を支払う(ペイ)から「バックペイ」と呼ばれています。
上記のケースでは、解雇から口頭弁論終結時まで18か月の期間があります。したがって、会社は従業員に18か月分の賃金を支払う必要があります。
仮に従業員の月収が額面50万円だとした場合、月額50万円×18か月=900万円+遅延損害金の支払いが命じられます。
これに加えて、賃金規定などで、支給時期及び支給金額が具体的に算出できる程度に賞与の算定基準が定められている場合には、賞与の支払いも命じられる可能性があります。
解雇が無効と判断され、1000万円を超える支払が会社に命じられる事例も珍しくありません。たとえば、次のような裁判例があります。
- 約3560万円のバックペイが命じられた事例(東京地方裁判所平成29年2月23日判決)
- 約1200万円のバックペイが命じられた事例(さいたま地方裁判所令和3年1月28日判決)
- 約1050万円のバックペイが命じられた事例(福岡地方裁判所令和5年12月12日判決)
金銭(バックペイ)を支払うことができない場合、預金口座や不動産などの財産を差押えられる可能性があります。
預金口座の差し押さえがなされた場合、その金融機関から借り入れを行っていると、差押えにより借入の一括返済を求められることがあります。
特に中小企業においては、借入を一括返済できる企業は多くなく、今後の信用にも関わるため、金融機関から融資を受けている会社は大きなダメージを被ることとなります。
(2) 従業員が復職するリスク
解雇が無効になると、判決には次のような記載がされます。
主文
- 原告が、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
- ・・・・・・
この主文の意味は、「解雇無効である以上、原告は会社の従業員だからね。これからも雇用を継続する必要があるからね。」というものです。
要は、金銭(バックペイ)を支払うだけでなく、解雇した労働者が会社に戻ってくることになります。
もちろん、事案により異なりますが、「これ以上雇用できない」と思ったからこそ、会社は解雇という手段を採ったはずです。
にもかかわらず、その従業員が会社に戻って来る、しかも多額の金銭を支払うのでは本末転倒です。
(3) 解雇の有効性が争われた場合の裁判費用や労力のコスト
解雇無効の裁判を起こされた場合、第一審だけで1~2年かかることも珍しくありません。
弁護士に対応を依頼する場合、弁護士費用が必要になります。また、弁護士に依頼しても、証拠の収集、相手方の主張の確認、書面の打ち合わせを行う必要があります。実際に裁判所に行って証言をしていただくこともございます。
本業の合間を縫ってこれらの対応を行う必要があるため、業務への影響は非常に大きいでしょう。
5. 解雇に代わる手段~退職勧奨~
従業員を有効に解雇するためのハードルは高く、また解雇にはさまざまなリスクがあります。
そのため、弁護士として「これは解雇で行きましょう」とアドバイスできる事案は、非常に少ないのが実情です。
とはいえ、従業員の問題行動や勤務態度を理由に解雇を考えていた場合、その従業員を野放しにしておくことはできません。できれば、円満に退職してもらいたいところです。
そこで、解雇よりリスクの少ない手段として、退職勧奨をまずはアドバイスすることが多いです。
退職勧奨とは、労働者に対して退職を勧めることです。労働者が退職勧奨に応じれば、合意退職となります。
解雇との一番の違いは、「退職について、労働者の同意があるか」です。
解雇は、「労働者との雇用契約を会社が一方的に解消する行為」で、労働者の同意は存在しません。一方、退職勧奨は、あくまでも労働者の同意により退職の効果が生じることとなります。
どちらも「退職」という効果を生じさせるものですが、解雇と退職勧奨を比較した場合、紛争になるリスクは圧倒的に異なります。
退職勧奨の方が圧倒的にもめづらく、かつ紛争になっても、会社が敗訴する可能性は相応に低いです。
そのため、解雇に先立ち、まずは退職勧奨をしたほうが良いケースも多くあります。
なお、退職勧奨でも注意しなければいけない点はあります。たとえば次のような点です。
- 退職「強要」と評価されてもおかしくない態様で、退職勧奨を行った
- 実際には解雇できない事案なのに「応じなければ解雇」と発言してしまった
- 本人が退職を拒否しているのに、何度も退職勧奨を行った
退職勧奨が違法と評価されたり、退職合意自体が無効と判断されたりすることもあるので、注意が必要です。
6. まとめ:事前の弁護士への相談が重要
今回の記事では、解雇のハードルやリスクと、解雇に代わる手段を解説しました。
一番重要なのは、「解雇を選択する前に、弁護士などの専門家に相談すること」です。
解雇を選択する前であれば、退職勧奨などリスクの少ない手段を選択することも可能です。
よつば総合法律事務所では、多数の企業様より顧問契約を締結いただいております。
会社側の労働事件を専門に扱う団体に所属している弁護士や、社会保険労務士としても登録している弁護士も複数所属しており、解雇・従業員対応については、多数の取扱い・解決実績がございます。
解雇前の方針策定・アドバイスから、解雇後の紛争対応まで、幅広くサポートを行うことが可能です。
従業員対応でお悩みの企業様や、従業員の解雇をご検討されている企業様は、お気軽にご相談ください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。