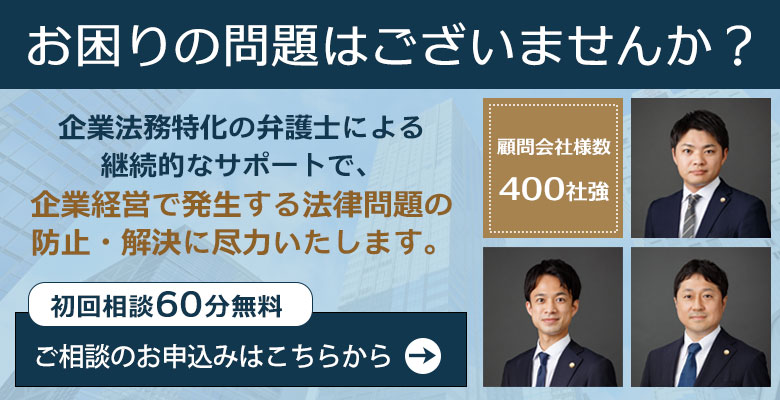1. M&Aとは

まず、M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略で、資本の移動を伴う企業の合併と買収を指した言葉です。
そして、M&Aのスキームとしては、①株式譲渡、②事業譲渡、③会社分割、④合併、⑤株式交換、⑥株式移転等各種存在しますが、一般的には①~④の手法で行われることが多いです。
今回は、M&Aを行う際にどの手法で行うかを検討する前提として知っておくべき、一般的によく用いられる①~④の各手法のメリット・デメリットをご説明します。
2. 株式譲渡
株式譲渡とは、売主が有する対象会社の株式を買主に譲渡する形で行われるM&A手法になります。
すでに発行されている株式を譲渡するだけでなく、第三者割当の形で新たに対象会社の株式を発行して行う場合もあります。
(1) メリット ⇒ 簡易・迅速
原則として、売主と買主との間で株式譲渡契約書を締結すれば完了してしまいます。
会社法で規定されている組織再編は、後でご説明するとおり、官報公告や債権者保護手続き等の複雑で時間がかかる手続きが必要になりますが、株式譲渡の形を取る場合はこれらの手続きが不要になります。
(2) デメリット ⇒ 部分的な譲渡ができない、シナジー効果が発生しにくい
株式譲渡の手法を取る場合、買主は、対象会社全体の支配権を有することになるため、会社の一部の事業を譲り受けることを目的とする場合はこの手法を用いることができません。
また、株式譲渡の手法を取った場合、対象会社は社名も変わらず、従業員からすると他社に売却されたという意識を持ちにくく、シナジー効果(相乗効果)が発生しにくいと言われています。
3. 事業譲渡
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を他の会社に譲渡する手法になります。
(1) メリット ⇒ 簡易迅速、資産の一部を譲渡可、負債の移転が原則なし
事業譲渡は、株式譲渡と同じく、会社法上の組織再編行為ではないので、官報公告や債権者保護手続等の複雑で時間のかかる手続きが不要で、簡易迅速に手続きを行うことができます。
また、株式譲渡と異なり、会社の一部分だけを譲渡することができる点もメリットの一つです。
(2) デメリット ⇒ 契約の移転が原則なし
これはメリットにもなることですが、事業譲渡を行った場合、債務については原則として移転しません。
その他にも、個別の契約や、従業員との雇用契約についても移転しないため、これらの契約を移転させるためには個別の対応が必要になり、手間と時間がかかってしまいます。
4. 会社分割
会社分割とは、会社が行っている事業を既存の会社に承継させる手法になります(吸収分割)。また、会社の事業を分割して新たな会社を設立する手法もあります(新設分割)。
(1) メリット ⇒ 事業の一部を譲渡可、契約関係も原則移転
事業譲渡と同様、会社の事業の一部を譲り渡しの対象とすることができます。
また、契約関係についても、原則として、利害関係人の同意なく移転させることができます。
(2) デメリット ⇒ 手続きが複雑、詐害行為として取消しのリスクあり
会社分割は、会社法上の組織再編手続きであるので、利害関係人の保護を図るために官報公告や債権者保護手続等の手続きを取る必要があり、その手続きが煩雑で時間がかかることになります。
また、会社の優良部門だけを分割させると、不良部門の債権者が債権の回収をできなくなる可能性があるため、場合によっては、それを理由として詐害行為取消権等を根拠に会社分割が取り消されてしまうリスクが残ります。
5. 合併
合併とは、対象会社を存続会社に包括的に承継させる手法になります。対象会社の株主には、株式などの財産を交付することになります。
(1) メリット ⇒ シナジー効果が期待できる、組織のシンプル化
株式譲渡と異なり、合併を行った場合、対象会社は消滅し、会社名や社内のルールが存続会社のものに統一されることになります。
それにより、従業員の意識変化が起こってシナジー効果が期待できます。
株式譲渡の手法によると、子会社等の数が増えることになり、グループ全体が複雑化してしまうことになりますが、合併の場合は会社を包括的に承継することになりますので、合併後の組織をシンプル化することができます。
(2) デメリット ⇒ 手続きが複雑、一部の譲渡ができない
合併は、会社分割と同様、会社法上の組織再編になりますので、官報公告や債権者保護手続等の煩雑な手続きを行わなければなりません。
また、会社を包括的に承継することになりますので、会社の一部を譲り受けるということができません。
本ブログの内容に関わらず、企業様の法律問題でお困りの際は、下記よりお問い合わせください。
※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。